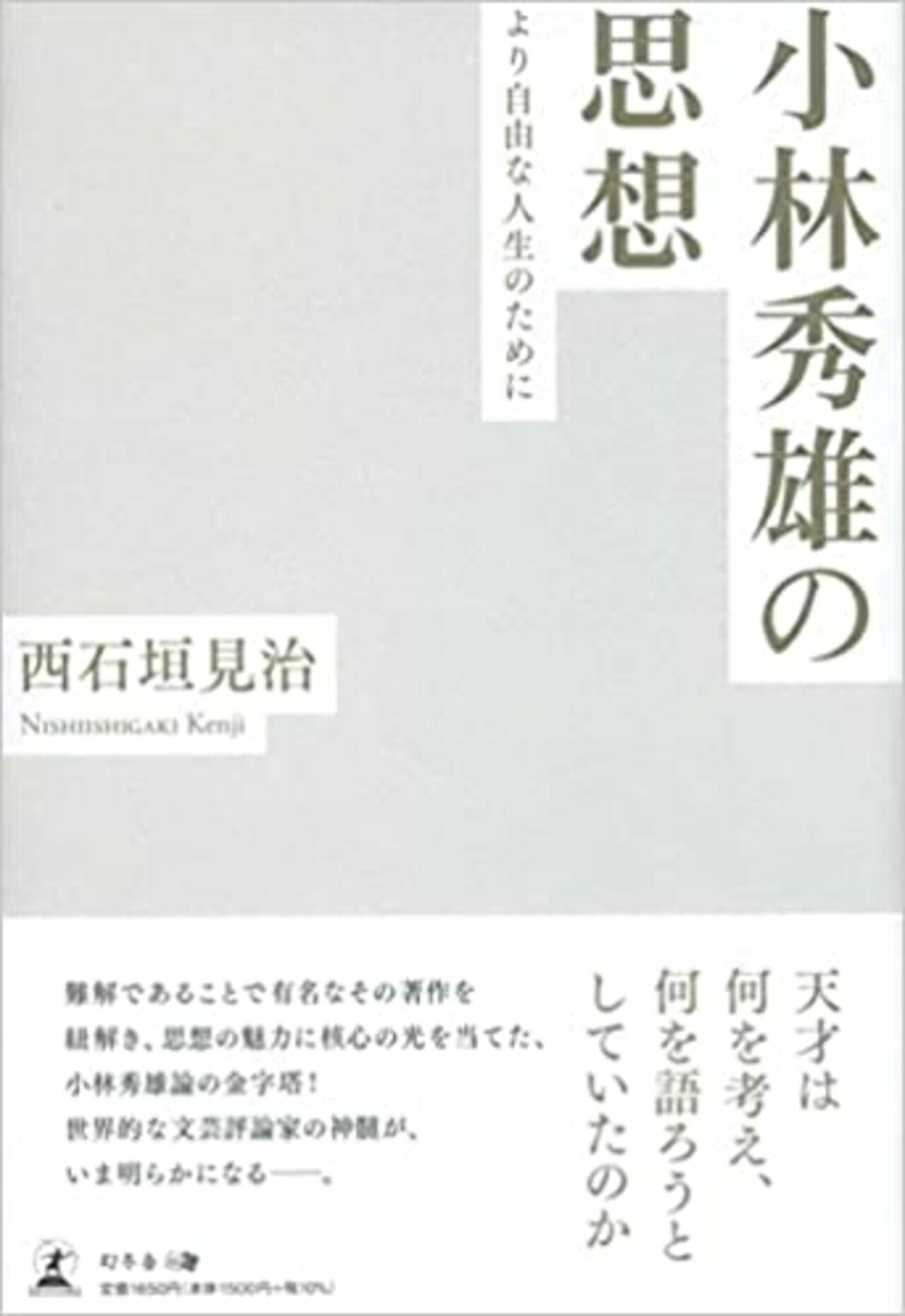このことからも、正しく考えるためには、少なくとも次のことが求められるのである。それは、言葉の日常的な所与性を鵜呑みにせずに、批判的距離を取って、いわば言語以前の経験に多少なりと思考の軸足を置くことである。しかし、それも、いざ実践となると、現実の大きな困難にぶつからざるを得ないのである。
それは、言葉の持つ、コミュニケーションの道具としての役割を否定さえするからである。社会的な意志疎通の道具としての、その本質的機能と衝突さえするのである。
実際、言葉は、その意味の日常的な所与性が自明であればこそ、会話を基調とした社会的コミュニケーションに役立つのである。そして自明さとは、ほかならず、言葉の意味を鵜呑みにすることなのである。
例えば、コップという言葉は、“飲む道具”としての意味ないし概念が自明なものとして与えられているのである。仮にも、それが自明でない場合には、意味の確認が、その都度必要となって、日常会話自体が成り立たなくなるのである。
しかし、コップはもともと、実用的なモノとして、人為的に制作され、存在するのであろう。そうであればこそ、コップとの関係に入る行為においても、“飲む道具”としての実用性を超えては、言葉の意味経験は一般に求められないのである。
そこでは、経験の意味は、対象の実用性と等価で、置換的な関係にあるのである。それゆえに、「便利なコップ」の経験を、まるごと「コップの便利さ」という言葉に置き換えても、先の「花の美しさ」をめぐる経験とは異なって、言葉のバブルに陥る恐れはないのである。
言葉と現実との同視は、実用的領域以外では成立しないこと
ところで、コップの例のように、その意味経験が、その一般性において実用的にあらかじめ規定ないし充足された─それゆえに、それ自体に透明な─事物や存在は、世界経験においてむしろ例外に属するのであろう。
自然や歴史にしろ、社会的、政治的問題にしろ、あるいは人生論や芸術文化にしろ、そこにあるのは、言葉の意味経験について、コップを相手にするのとは、まるで勝手の違う世界なのである。かえってそのほとんどは、意識の経験への懐疑の力が相応に成熟、発達していれば、ソクラテスのいわゆる「明晰なる無知」の自覚に照応する世界なのである。