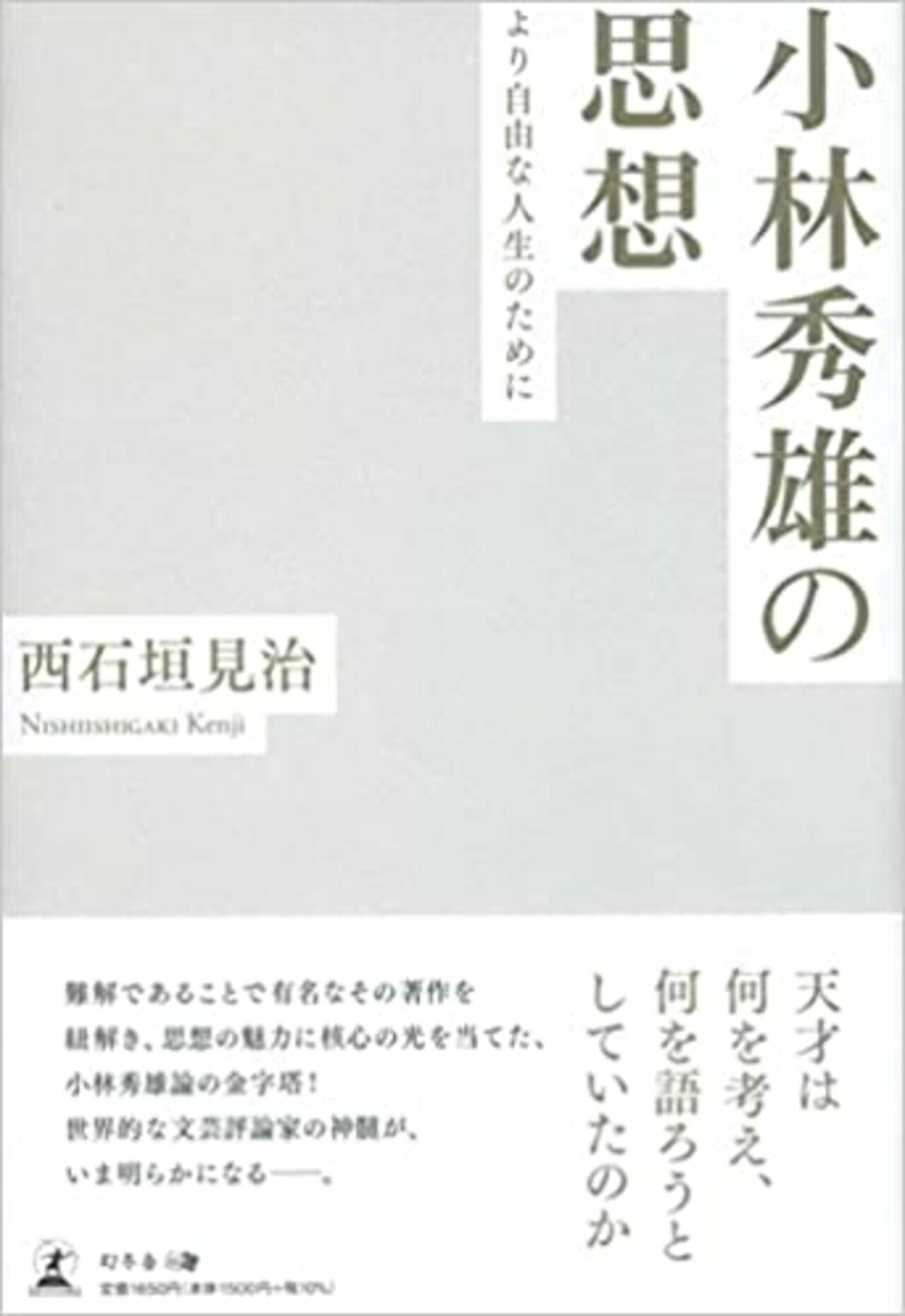「明晰なる無知」とアインシュタインの科学の仮説の位置づけ
なるほど、近代自然科学は、「折り紙付きの知」を世界にもたらしたかに見えないわけではない。そのいわば常に成功する方法が、自然の分野における知を飛躍的に進歩させてきたのであろう。しかし、それも、周知のように、いわゆる自然を操作し、再現する能力としての知の獲得にとどまるもので、”物同士の”関係の域を出ないのであろう。
それは、すでにカントの批判が明らかにしたように、物自体としての知ではない。その知としての地位も、”再現性”と言う行為の手続き能力に担保されているだけで、自体的な対象知に根差しているわけではない。それは、自然科学の最先端の知が、自然という名の実在と、深く、鋭く交わるほどに、いよいよその認識の相対性を露わにしつつあることにもうかがわれるのであろう。
そして、重要なことは、このような知や無知といい、あるいは両者の関係の相対性といい、その自覚や認識の内実には、雲泥の差があり得ることなのである。
例えば、アインシュタインは、カントの「世界の永遠の神秘はその了解可能性である」という認識の偉大さに、全面的な賛同を表明する。これはしかし、裏がえ返していえば、世界は、その了解可能性自体が、「永遠の神秘」とならざるを得ないまでに、その所与性の普遍的な深みにおいて、思惟との間に根源的な分裂を有しているということでもある。
そして、その分裂の意識の深さは、─あたかも、その深さに応じて、創造の困難や大きさが決まるもののように─アインシュタインの認識においてはよほど徹底していたのである。そのため、思惟が、その分裂のうちに横たわる深淵を超えて、言葉や論理の世界に投げ掛ける、科学の仮説の架橋行為は、次の奇怪な比喩をもって、実在との関係性を位置づけられるのである。
「両者の関係に類似しているのはビーフにたいするスープの関係ではなく、むしろオーバーコートにたいする衣装戸棚の番号の関係なのです。」(『物理学と実在』世界の名著第66巻「現代の科学Ⅱ」、井上健訳、中央公論社)