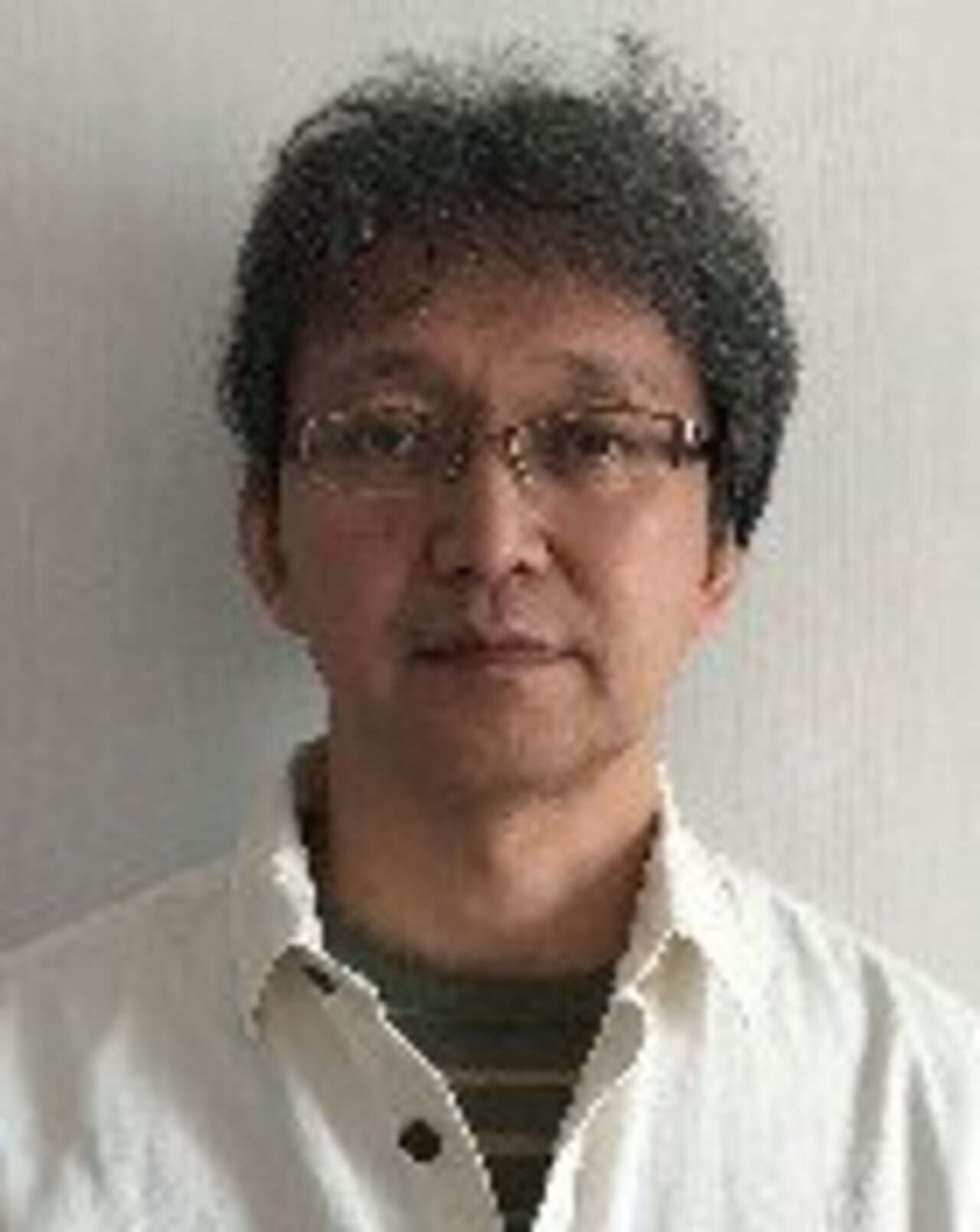【前回の記事を読む】【小説】講演の最中に感じる、闘病中の妻からの献身とは…
液晶の「幸せ」
教室の空気が温まってきたところで、廉は「名見出し」の話をした。
「ここで編集記者の教科書とも言える、この『新編 新聞整理の研究』という本に載った、優れた見出しをご紹介したいと思います」
廉は一冊の本を聴講者の前に掲げた。
「まず新聞記事の本文から読みますね。ちょっと古いのですが一九八八年十月二十四日付の読売新聞朝刊社会面に載った、『闘病中の昭和天皇と十三夜』の記事です。原文はとても長いので私の方で少し端折らせていただいています。
《ご容体が比較的安定している天皇陛下は23日夜、皇居吹上御所の寝室で十三夜の月見をお楽しみになった。午後9時20分過ぎ、皇居の森を照らしながら月が雲間から姿を現した。陛下のベッドからは、御所のひさしに遮られて直接ごらんになれないため、側近が寝室の明かりを消し、鏡に月を映してごらんに入れたという。
側近によると、陛下はベッドの背もたれをやや起こした状態で、ご愛用の眼鏡をかけて月見を楽しまれ、『少し欠けているね』とおっしゃって、ご満足の様子。窓外の月明かりに照らし出された吹上御所の木立も、よくおわかりになったようだったという》
この記事に編集記者が付けた見出しとは……」
ここまで一息に喋った廉の頰を、不意にポロリと涙が伝った。
自分でもわけがわからなくなり、咄嗟に聴講生に背を向けると、そこにあったホワイトボードにその記事の見出しをゆっくり書き始めた。
家での予行演習では、ここはただ読むだけの予定だったが、こうして板書しながら気持ちを鎮めるよりほかなかった。
【 ご病床 鏡に映す十三夜
──「少し欠けてるね」と陛下 】
ボードに書き終え、息を整え、ゆっくり読み上げてから廉は振り返った。
「すみませんでした、花粉症でしょうか」。小声で言うと、最前列の女性が「花粉症って先生、いま八月ですよ」と、ポケットティッシュを手渡してくれた。
教室中が明るい笑いに包まれ、難を逃れた廉は話を続けた。
「この見出しは読者の反響も大きく、都内の医師からは『昭和史に残る名句』との投書まで寄せられたそうです。しかしこの見出しを書いた編集記者には俳句の心得は全くなく、『五七調にして俳句らしく整えただけ』というのが実態だったそうです。
これを俳句と見るか新聞の見出しと見るかの議論は置いておいて、私などは、病床にあっても尽きぬ探究心というか、科学者でもあった昭和天皇の横顔までうまく写し取っているなと感じました。俳句と見出し、どちらも無駄な要素を削っていって言葉のパワーを高めるという点では、つくるプロセスに共通点はあるのかもしれませんね」
不覚の涙に襲われた理由は、さっき、この見出しを板書し始めたときに腑に落ちていた。
記事を読み進めるうちに廉の想いは夜の病室に飛んでいたのだ。
大勢の前で話す緊張感も手伝ってか、ある映像がまぶたにくっきり浮かんだ。
そこは皇居ではなくK大病院五階の病室だった。窓際のベッドに腰かけて、相模原の澄んだ空に浮かぶ十三夜の月を眺める和枝がいた。
「講演、無事終わったよ。会いたいな、今すぐ会いに行きたいな」
公民館の玄関で廉はメールした。
スリッパを脱ぎ、靴に履き替えるのさえもどかしかった。