【前回の記事を読む】早くに母を失った閔損は、義母にいじめられていた。それに気付いた父は別れようとするが…〇支那史(しなし)13晋書(しんじょ)(晋書八十八・列傳巻(れつでんかん)第五十八・李密(りみつ))【13】「李密」晋の時代(西暦200年頃)の頃のお話です。晋の李密は父を早くに亡くしました。母もまた、何氏(かし)の名を改め他に嫁いでいきました。密の年齢が、まだ数歳の頃でした。密の両親を恋しく…
明治時代の記事一覧
タグ「明治時代」の中で、絞り込み検索が行なえます。
探したいキーワード / 著者名 / 書籍名などを入力して検索してください。
複数キーワードで調べる場合は、単語ごとにスペースで区切って検索してください。
探したいキーワード / 著者名 / 書籍名などを入力して検索してください。
複数キーワードで調べる場合は、単語ごとにスペースで区切って検索してください。
-
健康・暮らし・子育て『『幼学綱要』を読む』【第10回】河野 禎史

国の役職を勧められたが断った男。「陛下に尽くす出来る月日は長くありますが…」
-
健康・暮らし・子育て『『幼学綱要』を読む』【第9回】河野 禎史
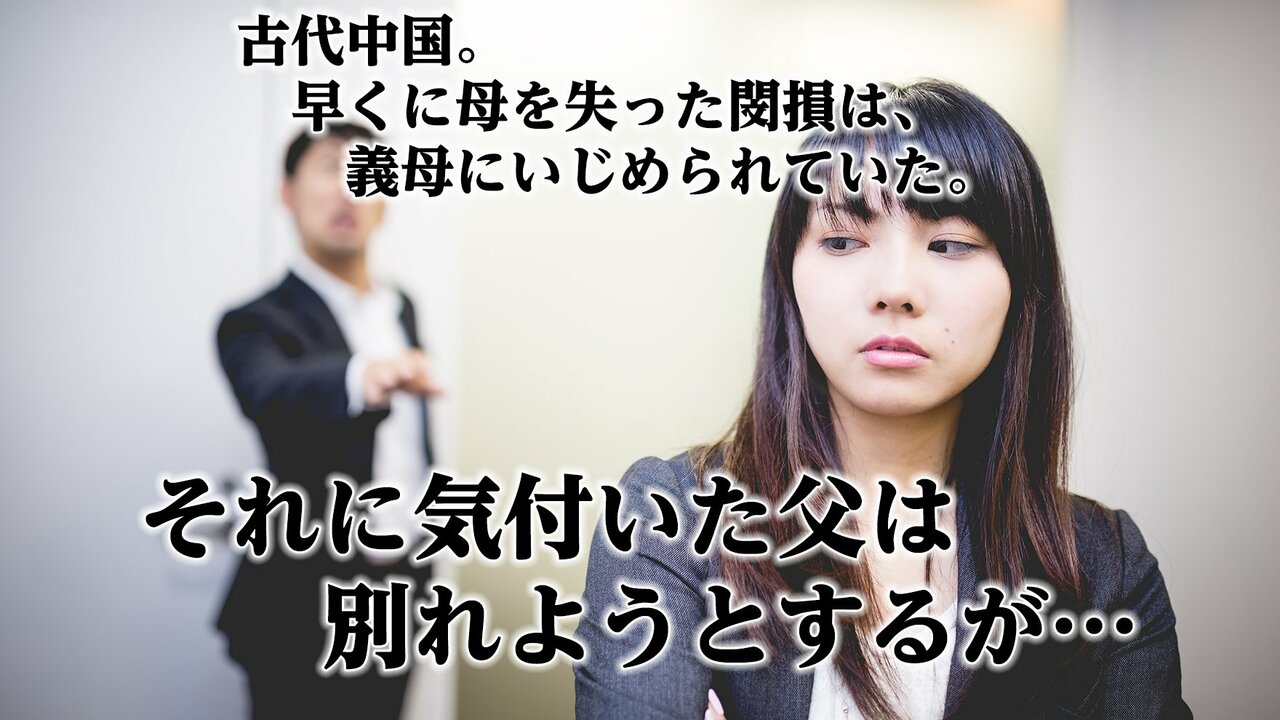
早くに母を失った閔損は、義母にいじめられていた。それに気付いた父は別れようとするが…
-
健康・暮らし・子育て『『幼学綱要』を読む』【第8回】河野 禎史
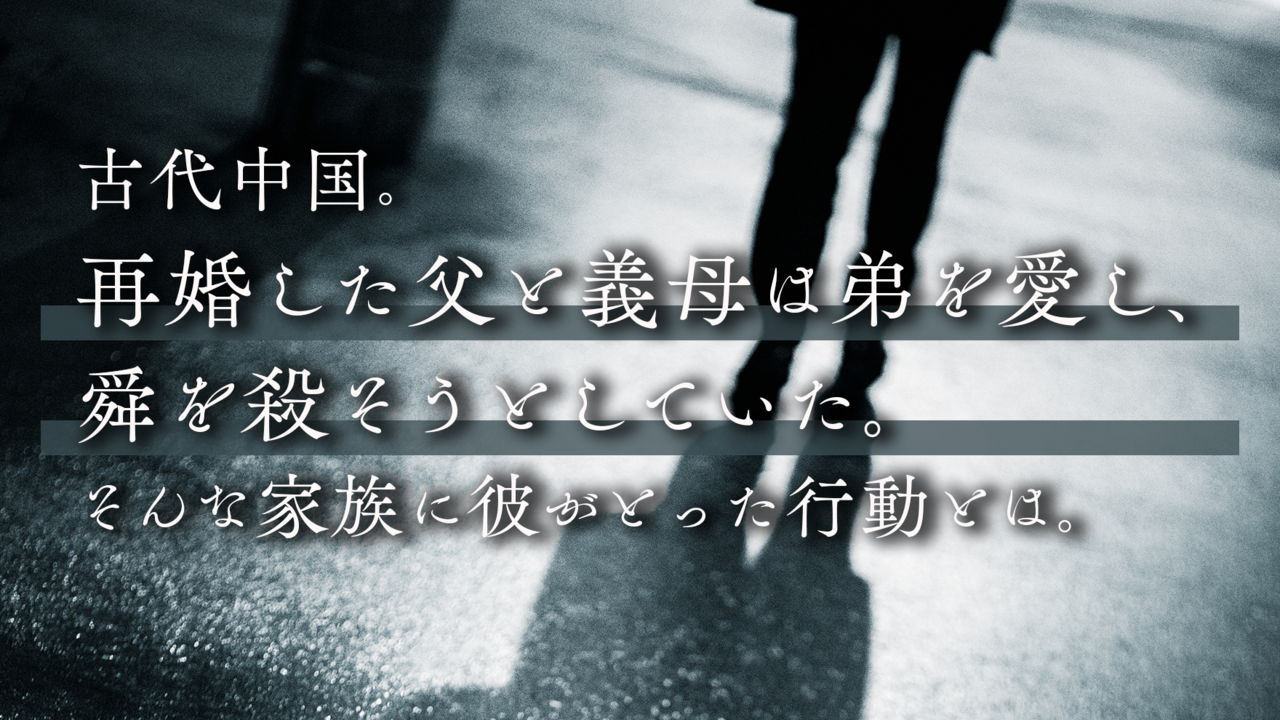
古代中国。再婚した父と義母は弟を愛し、舜を殺そうとしていた。そんな家族に彼がとった行動とは。
-
健康・暮らし・子育て『『幼学綱要』を読む』【第7回】河野 禎史
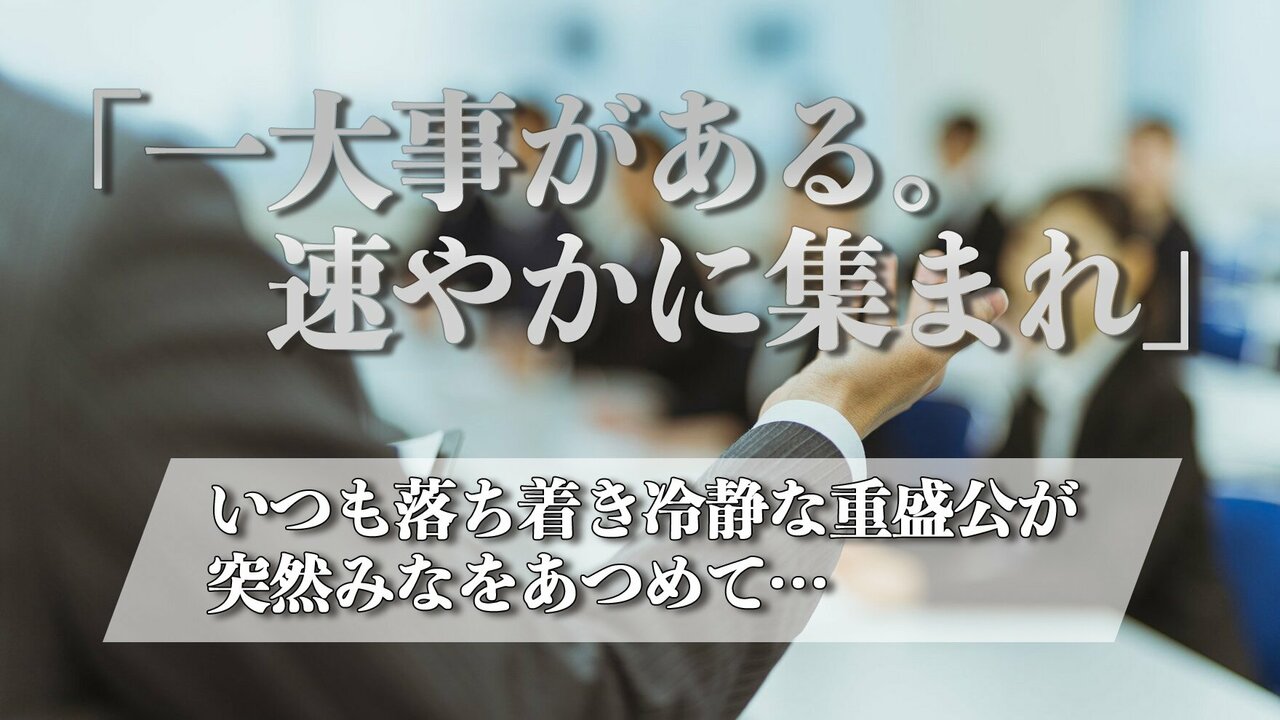
「一大事がある。速やかに集まれ」いつも冷静な重盛公が突然皆をあつめて…
-
健康・暮らし・子育て『『幼学綱要』を読む』【第6回】河野 禎史
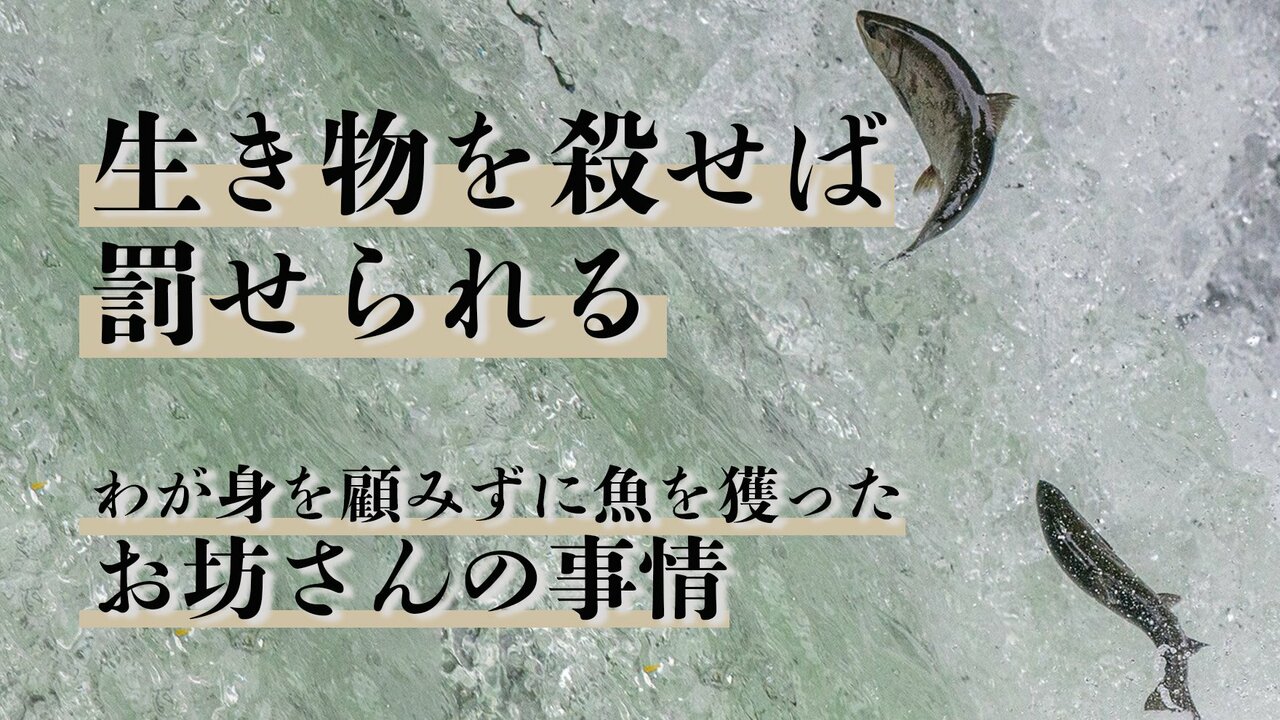
生き物を殺せば罰せられる…わが身を顧みずに魚を獲ったお坊さんの事情
-
健康・暮らし・子育て『『幼学綱要』を読む』【第5回】河野 禎史
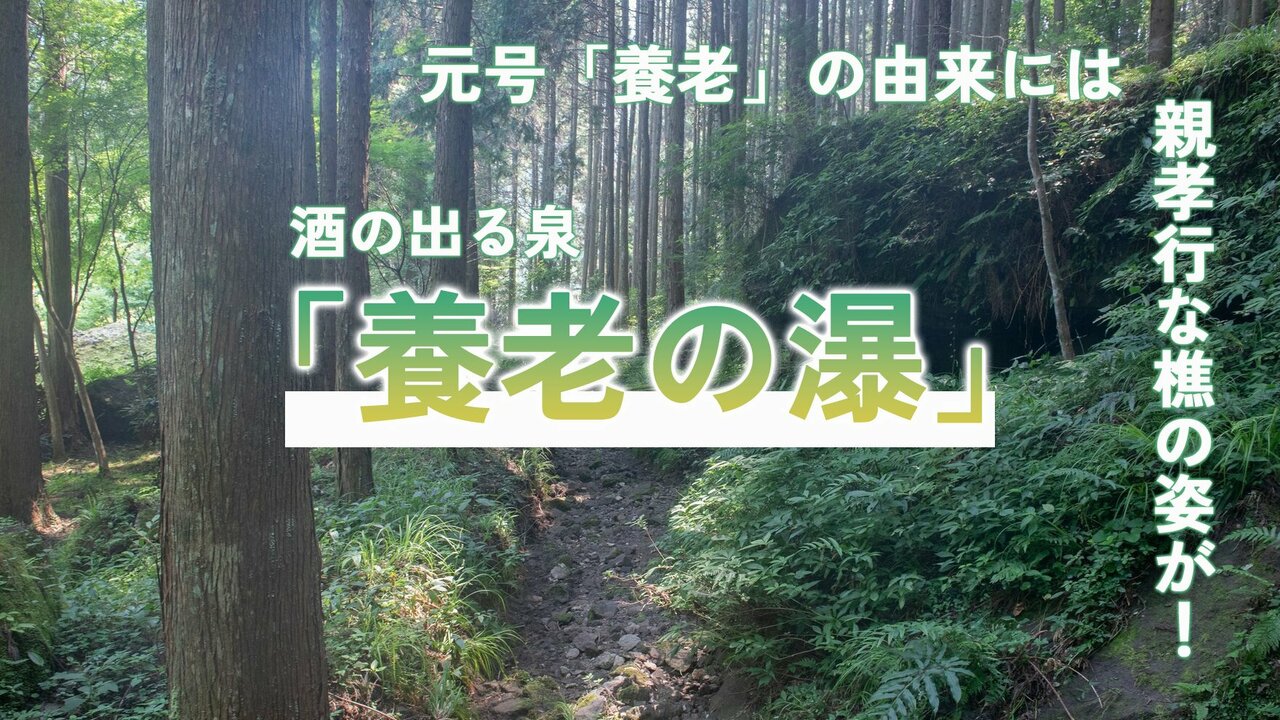
元号「養老」の由来には親孝行な樵の姿が…!酒の出る泉「養老の瀑」
-
健康・暮らし・子育て『『幼学綱要』を読む』【第4回】河野 禎史
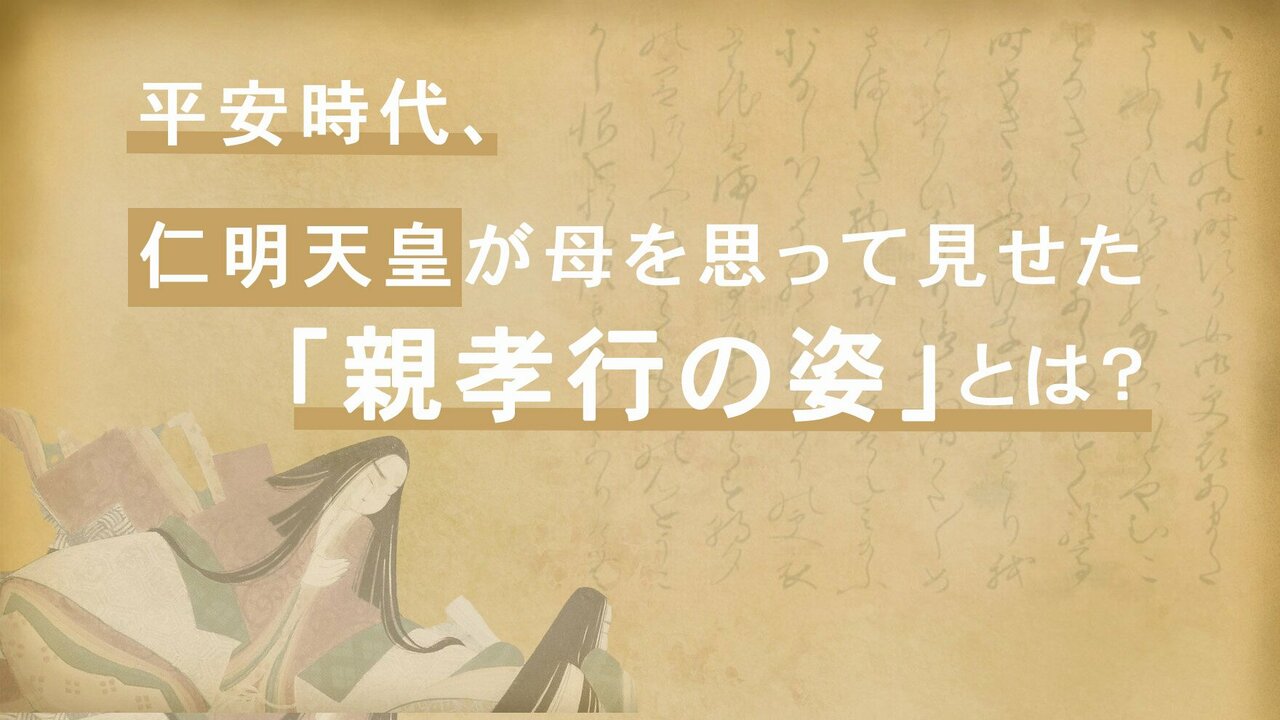
平安時代、仁明天皇が母を思って見せた「親孝行の姿」とは?
-
健康・暮らし・子育て『『幼学綱要』を読む』【第3回】河野 禎史
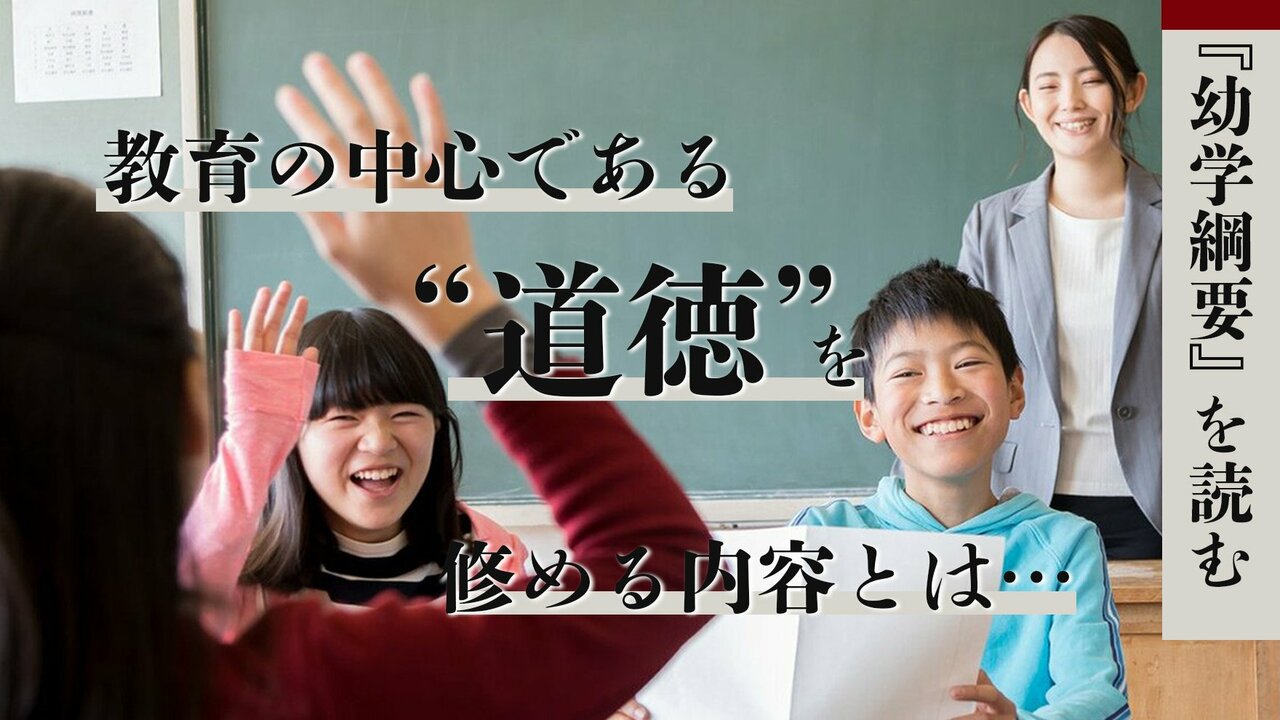
教育の中心である“道徳”を修める内容とは…『幼学綱要』を読む
-
健康・暮らし・子育て『『幼学綱要』を読む』【第2回】河野 禎史

現代の子供は「黄色」を言葉で表現できない!? 感性は言葉から
-
健康・暮らし・子育て『『幼学綱要』を読む』【新連載】河野 禎史
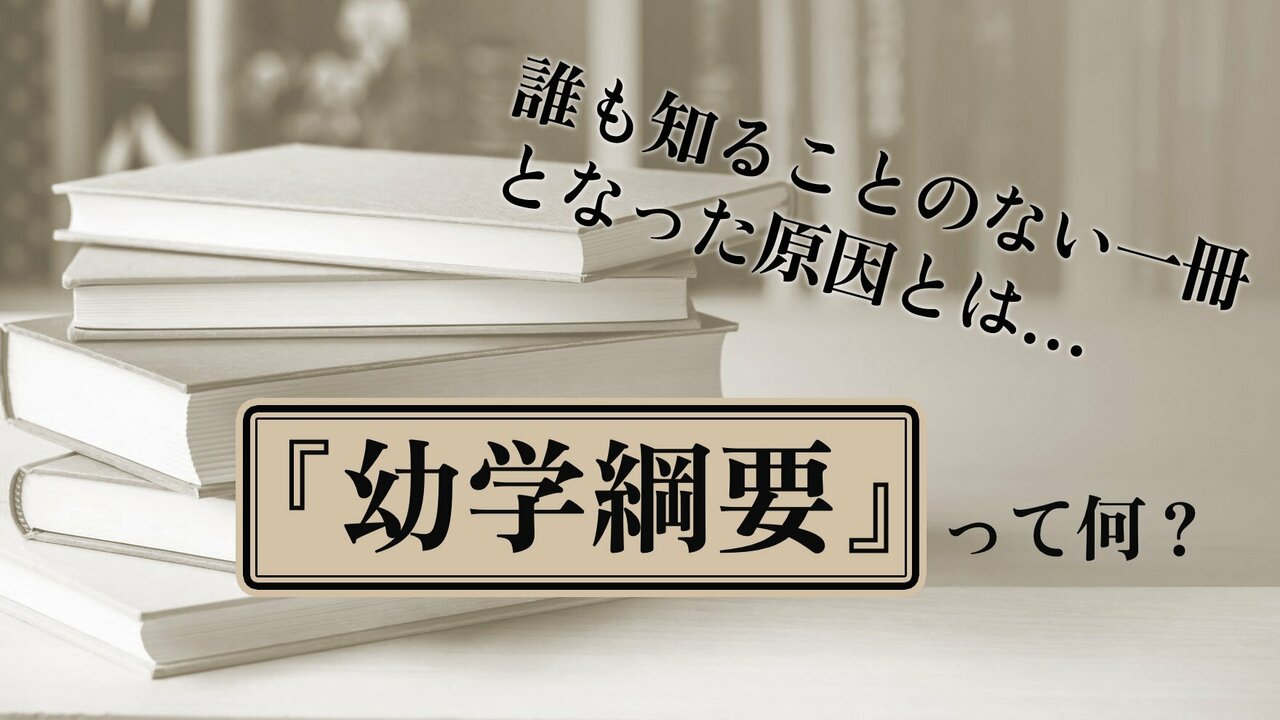
誰も知ることのない一冊となった原因とは…『幼学綱要』って何?
- 1
- 2






