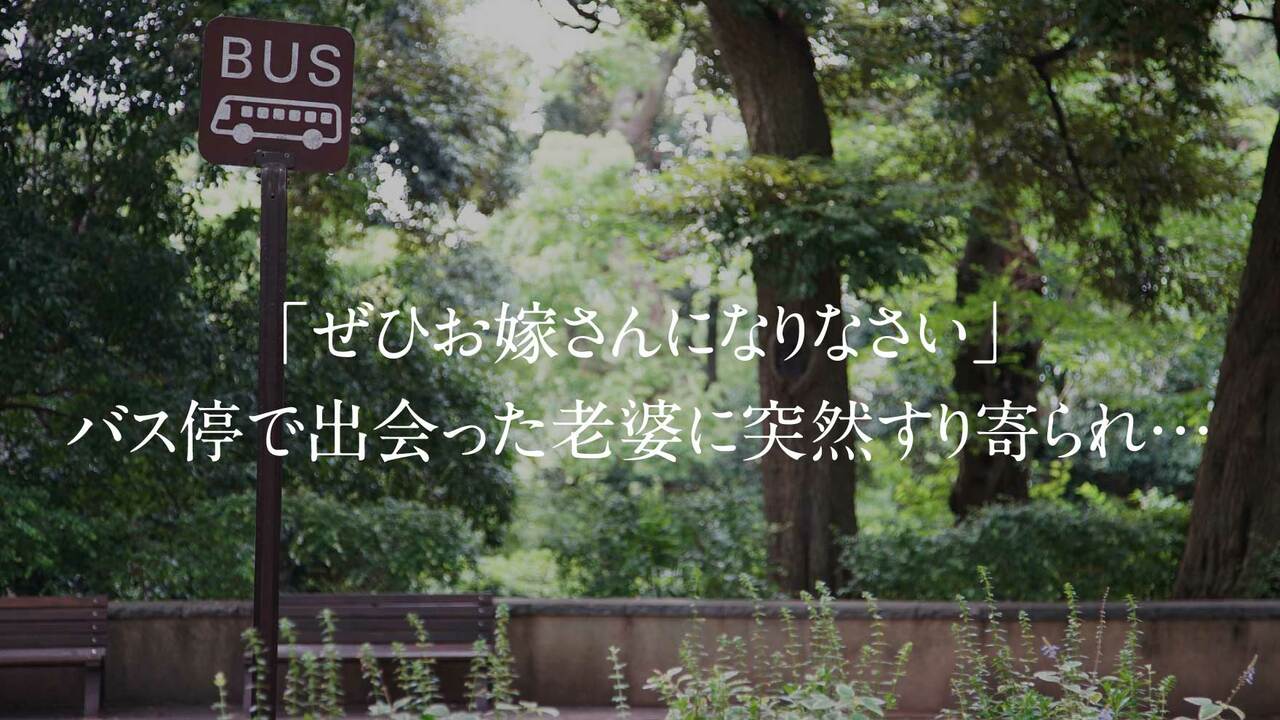【前回の記事を読む】恐怖!何気なく参加した宗教合宿。仲間の精神が崩壊していき…
森有正――星と月と悲しみ
出会いは喜びだけど、怖さも伴う。
私の内部にそっと隠れていた裡なる影の部分がうごめいたような怖さを感じた。でも言葉の魔力にはかなわない。言葉が胸の奥で鳴り響いている。「人間とは悲しみなのだ」と。
それは偽りのない本当のことのように思われ、引き込まれている私がいる。
いや、そんなことではない。もうとりこになっていた。
その中の一つは、ライナー・マリア・リルケの存在が大きい気がした。
「人々は生きるためにこの都会へあつまってくるらしい。しかし、僕はむしろ、ここでみんなが死んでゆくとしか思えないのだ」で始まる『マルテの手記』は、ドイツ文学者大山定一先生の訳である。いいようのないマルテの深い悲しみと森有正が重なった。
それにしても若き日、私はリルケの何に惹かれたのだろう。何も知り得ていなかった。そして今も。ただ寄りかかった樹木の内部からわずかに伝わる流れに心を奪われた流転の詩人の深い悲哀が感じられる詩集を読み、「何もわからなくていいんだよ。でも読んでごらん。いつか少しわかる時がくるかもしれないよ」といった声が聞えたような気がして、導かれるように全集を購入したのだった。
初秋の深夜は、厚着をして出たのに、寒くて体がガタガタと震えていた。
その時、はっと思った。急いで家に戻り、リルケの詩集を手にして、「鎮魂歌(レクイエム)」を読んだ。そして見つけた。
「ヴォルフ・フォン・カルクロイド伯爵のために」の中の五行を。
悲しみの流れに溶かされ心を奮われて、なかば無意識のまま遥かな星々をめぐる運動のなかにあの喜びを見いだすがいい あなたがこの地上からとりはらって自分の夢想していた死のなかに置きかえた喜びを。
深夜の空を眺めていると、「鎮魂歌」の五行から漂う一滴が、何だか体に溶け込んだ気がした。
その日長い時間、神秘な空の星々と、私の中に居場所を占めた、「人間とは悲しみなのだ」「悲しみの流れに溶かされ」の言葉を繰り返しながら、白い雲を通って現れる月の光と青の移行を眺め続けた。