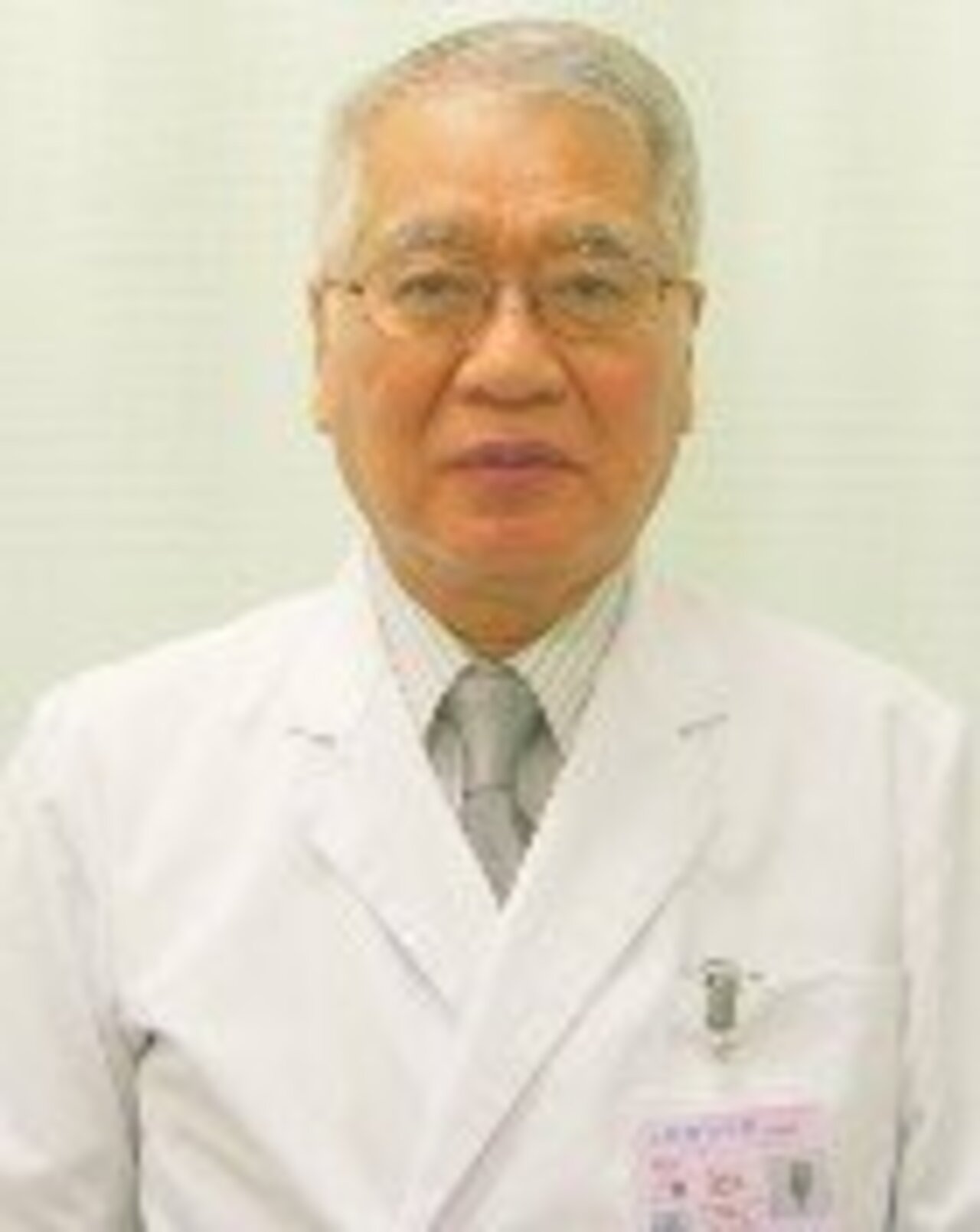「ところで、国田さんのご両親はまだ健在?」
「私は三歳の時に伯父夫婦と養子縁組みをしましたので、生みの親のことはわからないのです。ただ、育ての親はまだ元気ですよ。今の父はゴルフ好きで倉田カントリークラブのメンバーですのよ」
「そうですか、倉田カントリークラブは中国地方では名門のゴルフ場だよ。ということは裕福な家庭で育ったということだね」
「いいえ、中の上の家庭ですよ。ウッフッフ……。伯父夫婦は親としてよく可愛がってくれて、中高一貫校の私立進学校に通わせてくれたし、とても感謝しています」
「なるほど、それで今の優秀な国田さんがいるわけだ」
時間とともに国田と村山の距離が近くなっていくのをお互いに感じていた。しかし、国田の生みの親は気性が激しく決して弱みを見せない母親がいることは絶対に喋らなかった。
この学校で若くして教務主任になることは、国田にとっては出世街道を歩むということになるからである。ということはこの学校に就職して、いずれは副学校長となり、骨を埋めることを将来像に描いているのである。
村山はまだ案内したいところはあったが、時間の都合上、大阪に帰らねばならない国田を送るため新幹線新尾因駅までタクシーで行くことになった。タクシーの中で国田は、
「今日は、尾因市の古刹を案内していただきありがとうございました。どちらのお寺も真言宗でしたね。いろいろな宗派がありますが、浄土宗などと比較すると真言宗の方が格が上のような気がしますわ」
「仏教の宗派に格差などがあるもんですかねぇ〜。尾因市は中世の室町時代から急に発展し、豪商が各宗派に寄進してお寺が増えたとか、現在、尾因港周辺に二十数カ寺残っているよ。真言宗が好きならば有名な西国寺に案内したいところだが、この次にしよう」
どうも国田は真言宗らしいと村山は思った。一方の国田は村山が教師であったことを初めて知り、二人が教師という資格を持っていることから、何となく親しみを感じ、この先生は私の味方になってくれると思った。
タクシーが新尾因駅に着いた時に村山は昼食をした日本料理屋に手配させた地元で有名な蒲鉾を土産品として手渡した。国田は破顔してこれを受け取って帰路に就いた。