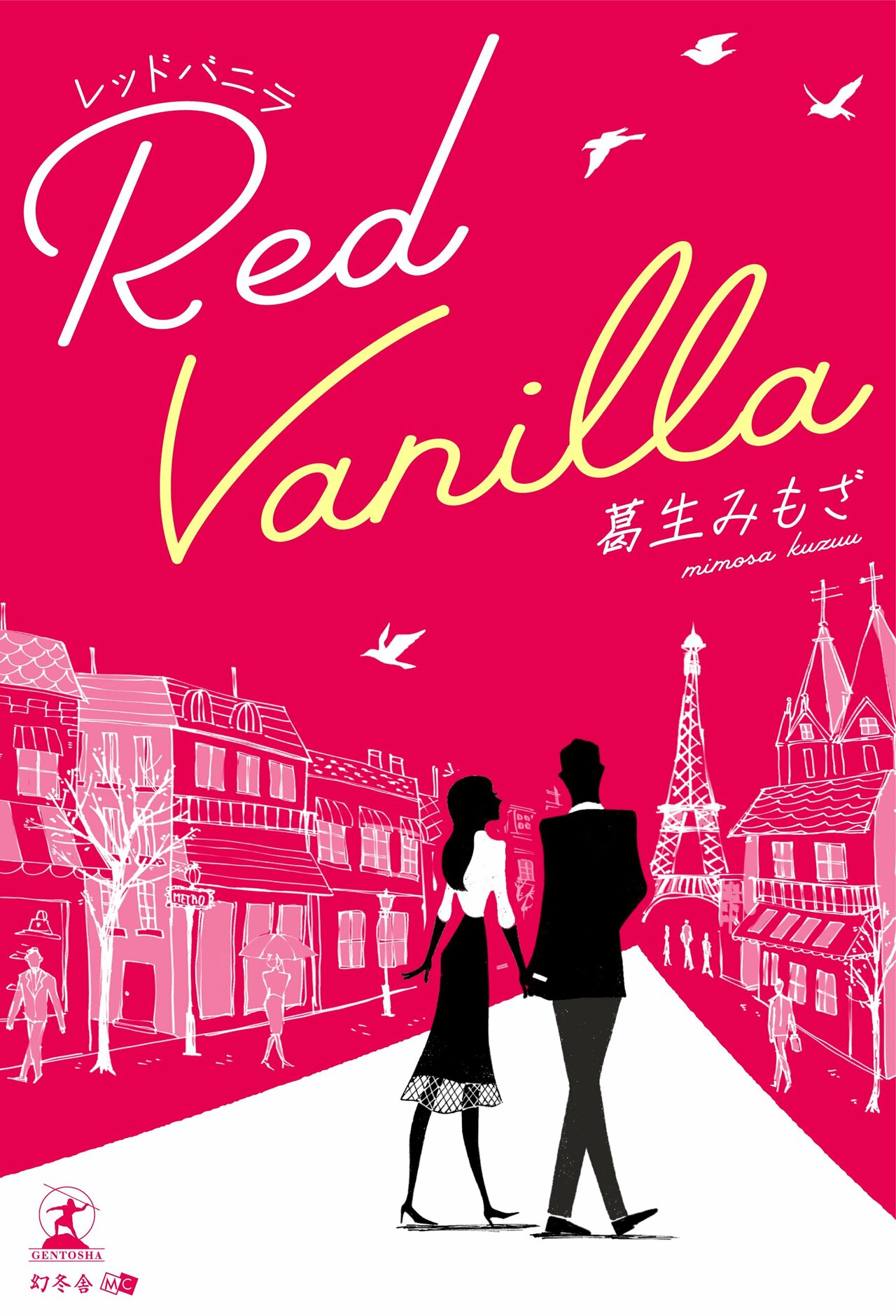【前回の記事を読む】「I Love You」繋がった国際電話、ようやく通じ合う2人の心
遠いドフィーヌ通り
年が明けて二〇一八年、四月初旬にパリに行こうと思っていた。生徒の学年進級で仕事の区切りがつくのが四月だからだ。
しかし、ことはうまく運ばなかった。お正月松の内も過ぎた一月十日、娘の父親が長野の自宅アパートで亡くなったという連絡が入ったのだ。真冬の厳寒期、私の仕事柄一番忙しい時であったが、葬儀やもろもろの後始末に長野まで出かけて荼毘に付すことになった。
戸籍を抜いているため、元妻である私は、ほんの何時間か保険金詐欺を疑われてしまった。病院で臨終を迎えれば、そんな事件性も発生しないのだが、このご時世では警察が介入するのも致し方ないことだった。警察もこちらの事情を察して心配りを見せてくれたものの、面倒な思いは娘の彩子が全部背負って、我が子ながら健気だと私は頭の下がる思いだった。
彼女はこの件については何かと私に敬語を使う。その敬語は、経済的理由で籍を抜いた私が葬儀を上げることはないとの彼女なりの理屈なのか、私が何も言わずに動いていることへの気遣いなのか。そんな水くさいことをしなくてもいいのにと何度も思ったが、口に出すと悲しくなるので私はつとめて気丈に振舞った。
もろもろのことを終わらせ、北陸新幹線東京行きのホームに立っていると、底冷えの身を切るような寒さのなかを風花が舞ってくる。限りなく寂しい思いだったが、それでもあの白さを美しいと思った。そして私は「淡雪」と題した七句を作品として仕上げることができた。思えば私も俳人になった。後日、俳句の師匠が私にこう言ってくれた。
「娘さんが敬語を使う。それはすごいね。それがすべてを物語っているね。えりかさんがどのように結婚生活をおくり、またその後ご主人と別れて、どのように娘さんと生活してきたか、そのことですべてがわかる。一つのドラマが書けるね」
私はそれを聞いたとき、先生が脚本家でもあることを実感すると同時にその言葉が心の底から嬉しくまた価値のある言葉だと信じ、弟子にしてもらってよかったとつくづく思った。