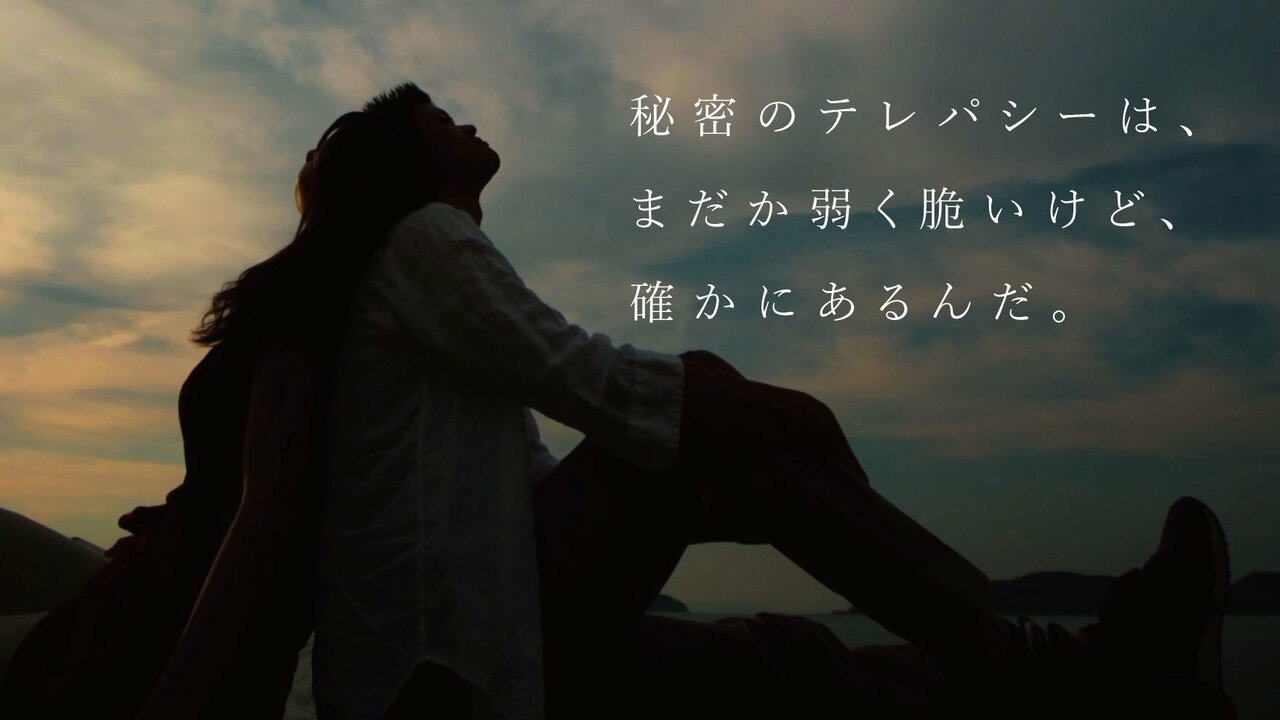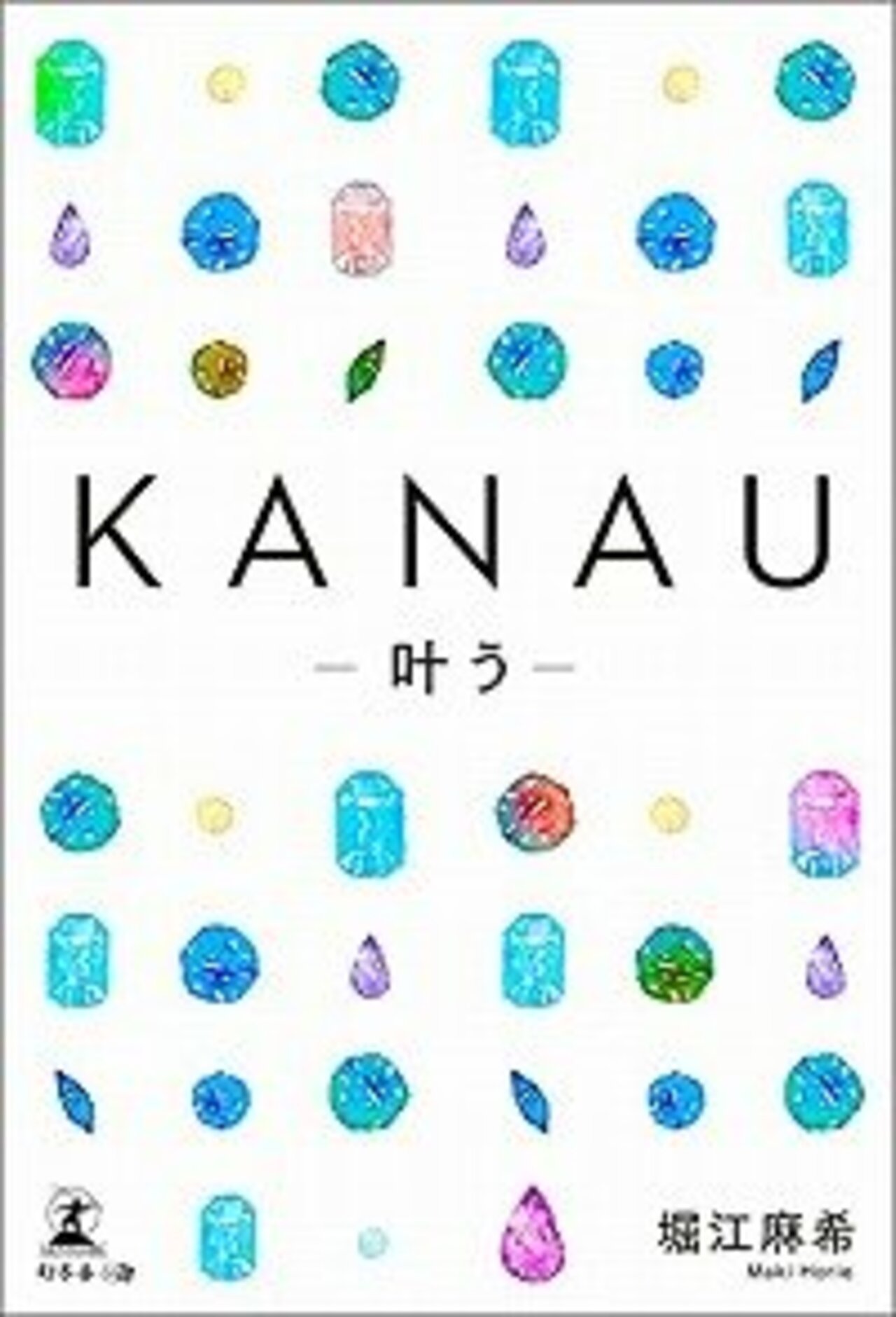【前回の記事を読む】一目ぼれの相手と再会、突きつけられた埋められぬ年の差…
KANAU―叶う―
二階のバンドブースのテーブルには、料理が並んだ。マルゲリータ、カルボナーラ、コンソメスープ、しゃぶしゃぶサラダ、煮込みハンバーグ、おにぎり……。どれも大盛り。まかないのように用意された食事を、武士、大地、優理が男の子らしく食べている。
優理と大地が、おにぎりをとりあっている。ねぎみそ、明太子、しらすのオイル漬けのような少しスパイスのきいたもの、他にも数種類あって、二人ともあと一個残ったねぎみそのおにぎりを食べたいらしい。いつものくだらない感じが可愛くて、その男の子らしさが、望風は大好きだった。
武士は、望風に「デザートいる?」とたずねる。望風が「うん!」と言うときの笑顔が、武士は好きだった。「あとで、コーヒーと一緒に持ってきてあげんな」と言って、望風にピザを取ってあげた。この構図は、いつもの四人のスタイルだった。
望風は、しばらく日向のことを忘れられた。午後十時になる頃、優理が望風に「帰るぞ」と言うので、解散することになった。四人で一斉に階段をおりた。日向に四人で遠くから頭をさげて、外へ出た。
日向は、その四人の後ろ姿を見ていた。日向はスマホをスーツのポケットからとりだして、チャットアプリを開く。望風とのトーク画面へと進んだ。そこから指が動かない。日向は、何をやってるんだと葛藤して、とどまった。
望風と日向は、それぞれ立場上のコミュニケーションのとりづらさを感じていた。事務的ではなく、男と女としての会話を意識したからこそであろう。二人の秘密のテレパシーは、まだか弱く脆い光線ではあったけれども、確かにあった。その光線は、その夜の空間で夜空の星座のように美しくつながり続けたのではないか。とぎれないように。人の人を想う純粋な気持ちは光となって、醜く美しく輝いた。