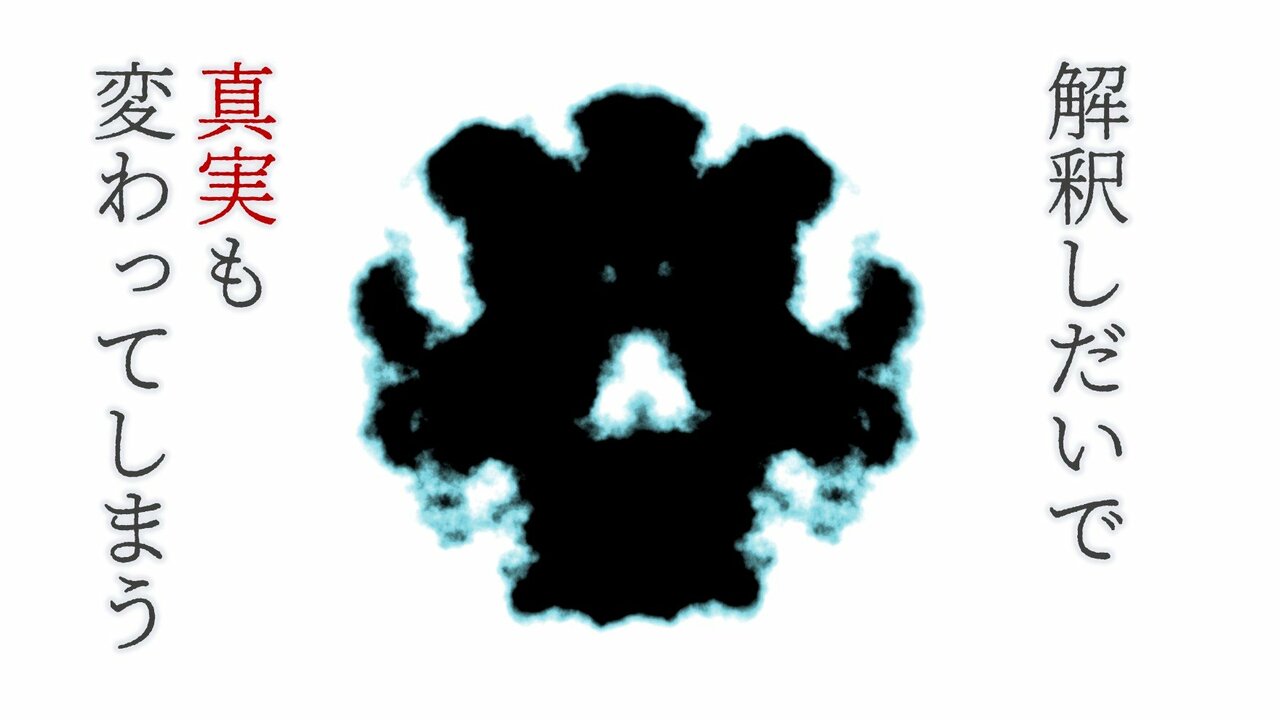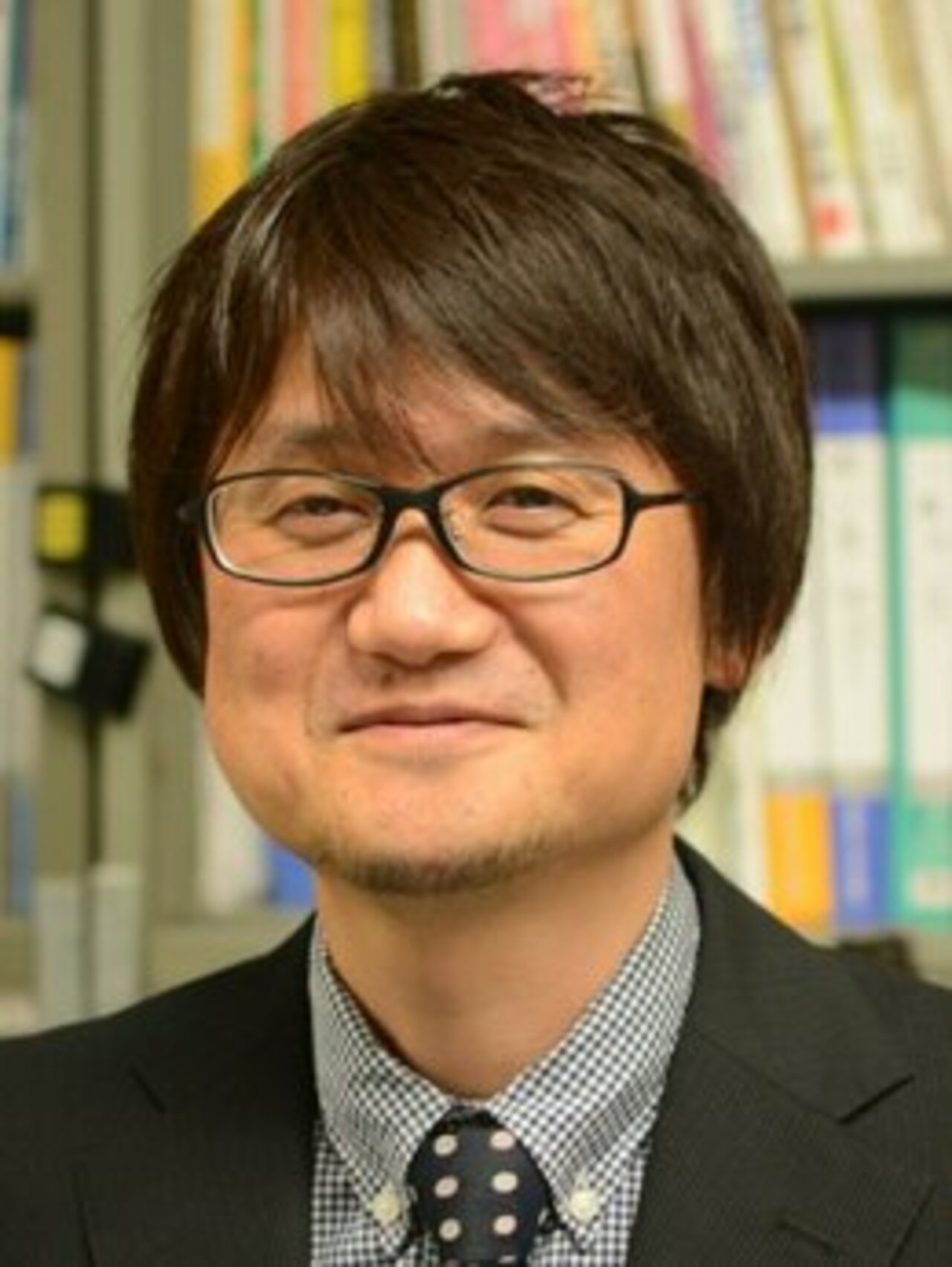第2章 解釈
2
多くの社員が夏休み休暇を終え、活気が戻った9月下旬、由美が慌てたように新聞を持ってケントのところに走ってきた。
「ケントくん。どう思うこの記事」
ハラール認証の危うさ
2020年東京オリンピックに加え昨今のインバウンドブームにより、世界の目が日本に向けられている。格安航空スカイアジアの就航も追い風となりインドネシア、マレーシアなどイスラーム教徒が多く住む東南アジアからの観光客が増加している。イスラーム教の戒律は厳しく豚肉やアルコールは禁忌とされるため、それらを含まないハラール食品の開発は必須である。
食品会社各社は熱い視線をなげかけている。しかしハラール認証には注意も必要だ。「20年ほど前にインドネシアでハラール偽装事件がありました。ハラールと認められていない豚由来のゼラチンを製造工程で使用したことを隠していた現地の工場責任者が逮捕されました。イスラーム教の充分な理解なくして正しいハラール食品は作れません」(国立宗教資料館・イスラーム研究室・佐伯宏教授)(文責 佐藤明)
なぜ今、注意喚起するような記事が出たのか分からなかった。開いてあった記事を閉じ、表紙を見た。食興業新聞社だ。記者会見で執拗に細かく質問した記者の顔を思い出した。「知ってますよ。裏の裏まで」みたいな顔をした記者だ。
「どうしたのケントくん。大丈夫?」
由美が顔を近づけてきた。優しい眼をしていた。スリーファイブだけで見せる眼だ。あの部屋のあの瞬間にだけ見せる眼だ。35階の部屋の窓際まで歩いていった。そこにガラスはなかった。
誰かが背後に立っていた。人差し指を突き出していた。押さないでほしい。なんでもするからと思った。足元から冷え上がっていく。後ろを振り返ることもできない。横にも行けない。誰かに命の行方を預けたまま立ち続けていた。
「ケントくん、どう大丈夫?」
ケントは研究棟・南の仮眠室にいた。臨床試験のための部屋だ。病院での本試験の前の小規模なパイロット試験のための部屋で、使用することはほとんどなかった。知る人ぞ知る仮眠室だ。
「……すみません。気分が悪くて……」
「大丈夫よ。もう少し横になってればいいから」
ケントがベッドから起き上がろうとすると、由美が肩を押さえた。
「大丈夫よ、寝てて。上司の命令よ」
「……すみません……」と、ケントは頭を枕に沈めた。
「この部屋は快適なのよね。昼間どうしても眠くて眠くてっていうときがあるじゃない。女性の弱さを見せちゃいけないって頑張っちゃっても、体力は男性に劣るからね。だからたまにこっそり利用してたの。ダメよ誰かに言っちゃ。2人だけの秘密よ」と言って、由美は人差し指をケントの唇に押し付けた。
ケントは思った。また秘密が増えてしまったと。でも秘密ならいいけど嘘はいけない。誰かに言わないと取り返しがつかないことになってしまう。ケントは天井を睨みつけ意を決して言った。
「……由美さんに言っておきたいことがあります」
「あら、改まって何かしら。ベッドで看病されながら言う素敵な言葉かしら」と言って由美は足を組み直した。
「……原材料の白砂糖はやはりまずいです。ハラールな原材料とは言えないです」
「あら、そのことね」由美は腕を組んでしばらく考えてから言った。
「ケントくんが心配性なのは分かってるわ。そこがまた可愛いところだし。でもね。それって解釈の問題じゃないかしら。今ね、私達はここで2人きりで密室にいる。上司が部下の様子を見に来た。というのが普通の解釈よね。でもね、知っての通り、私とケントくんは肉体的につながっちゃってるの。表面的には見えない深い愛情という感情が今この瞬間もお互いに激しく行き来してる。ね。私達2人はそう解釈してるわけでしょ」
と言って由美は顔を近づけてきた。唇が重なりそうなほど。由美は続けた。
「恋愛って男女の心のすれ違いが大きな問題を生むし、逆に愛を深めることもある。二人の間に、ある事件が起きた。それが起きたことは事実でも、男女で解釈が異なる。よくあることでしょ。例えばね。私が街をぶらぶら歩いていた。するとカフェの窓側にケントくんが座ってた。なんとその向かい側には見たことのない女性が座ってたとするわよね」
と言って胸のあたりを布団の上から人差し指で2回つついた。
「女性の私は“ケントのやろう浮気しやがって”って思った。ところがよ。当の本人ケント様は“単なる英会話の勉強です”」
と言って、由美は肩をすぼめ、顔の横で両手を広げた。
「解釈しだいじゃない? いかがですかケント様」と、また指で布団をつついた。「解釈しだいで真実も変わってしまう。それにしてもよ。嘘はダメですよね。ケントくん」と言って胸のあたりを布団の上から両手で強く押してきた。