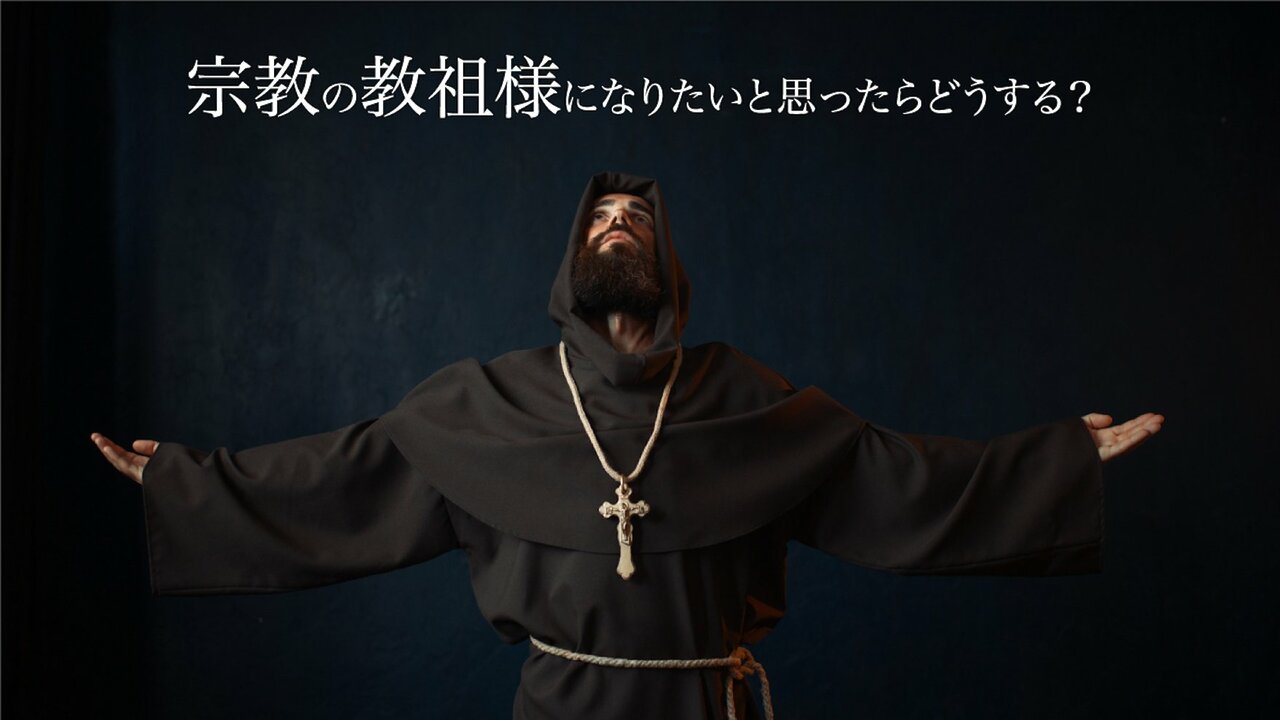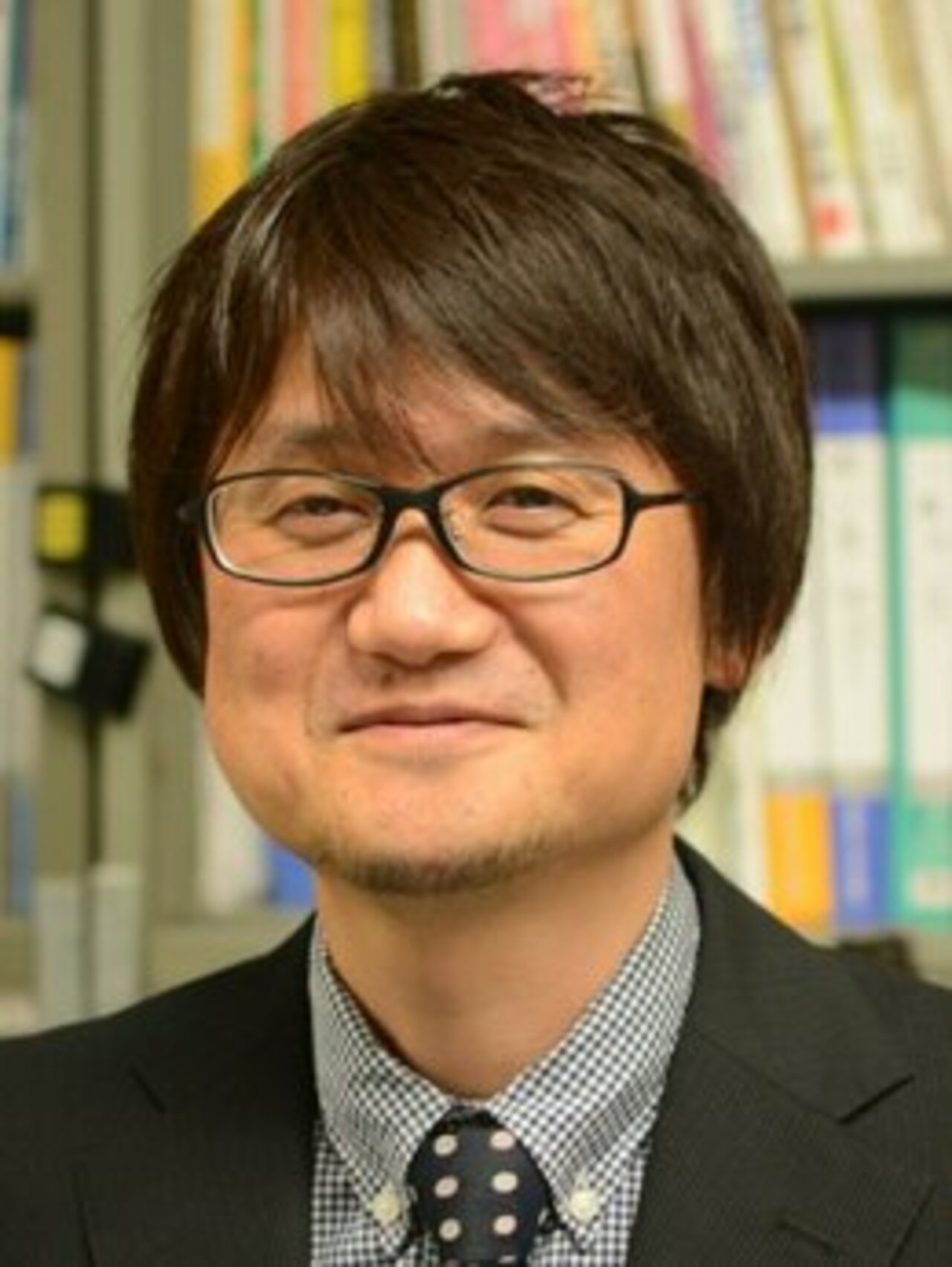第1章 ハラール
1
靖国神社のソメイヨシノが開花したと発表された。
平年よりも随分と早い3月初旬。
研究棟・西5階、トイレの個室にケントは腰を降ろしていた。
タバコを吸わない、コーヒーも飲まない、人付き合いの苦手なケントが、唯一落ち着ける場所だ。吸気口の吸い込む音がさざ波のようで心地よい。トイレットペーパーを下から軽く数回トントンと叩いた。休憩しているんじゃない、必要があって個室を使っているんだと、示すためだ。
食品系の大学院を卒業後、大手製薬会社エリザスに入社してから3回目の桜だ。ここまでは順調だった。特定保健用食品いわゆるトクホ商品化に向けた基礎研究で、論文を3つ書いた。あと2つ書けば博士の学位を取得できる。夢に見た大学教員の職につける。その可能性が大きく広がる。その夢が悪夢であったとしても、限られた人達の中でゆったりと過ごせる大学教員の職は自分に合っているとケントは思っていた。
そもそも大学卒業時に考えたのだ。就職先として一番楽しそうなところはどこかと。結論は大学教員だった。自分より能力が下の学生と、たわいない話をして、やる気にさせて実験させる。その結果を我が物のようにして論文を書く。教授になれば上司がいないに等しい。さぞ楽ちんだ。そう思えた。だからこそ、大学教員につながる大学院まで進み、その後、論文が書ける環境の研究職、エリザス製薬を選んだのだ。
しかし神はケントに試練を与えた。トクホを開発する健康食品開発部の閉鎖が囁かれていた。トクホ商品の売上は、製薬部門に比べればあまりにも小さいのだ。「所詮、食品でしょ」、「たいした効果もないのに健康食品です! なんて堂々とよく言えるよね」と、製薬系の社員には、健食部門はつつきの最下位、一番弱いチキンなのだ。
ケントは焦っていた。健食部門が消滅する前に必ずや論文を書き上げてやると。昼間は業務としての研究を進めながら、夜や週末は自分のために論文を書く生活を続けていた。
思ったようには進まないのが人生だ。ケントにとっては悲しむべき事態が起こった。
昨年の夏に「2020年東京オリンピック」の開催が決定したのだ。オリンピック委員会の投票結果をテレビの前で見ていた。
「頼む、落選してくれ」と神に祈った。
でも神はいつも僕を見放すのだと痛いほどわかった。海外から東京への観光客の増加が見込まれる。なかでも注目されたのは、経済発展の著しいインドネシアとマレーシア。いずれもイスラーム教徒の多い国だ。他社にさきがけ「宗教に配慮した健康食品を作る!」と、会社のトップが明言したのだ。
当然ながらケントの所属する健康食品開発部が担当部署となった。通常の業務に加えて、この新プロジェクトを行うことになった。ケントは神を恨んだ。そして「お・も・て・な・し」という5文字をも恨んだ。腕時計を見た。もう5分が過ぎていた。そろそろ戻らないと、と思った。
トイレから出たケントはエレベーターホール手前の非常扉を開き、階段で3階まで降りた。会社内でできるだけ人に会わずにすむ経路を熟知していた。エレベーターを待つ間、製薬部門の同期入社の人達に会うのでさえ嫌だった。製薬部門の人間は健食部門の人間を見下している。そう思えてしかたなかった。売上の低い部門の人間が、能力や人間性も低いわけじゃない。
3階の非常用扉から廊下に戻ると北に向かって廊下を歩いた。最も日当たりの悪い廊下の先にある最も利用者の少ない階段を使って1階まで降りた。2階の階段を使わないのは吹き抜けになっているからだ。事務系の間接部門がある研究棟北にくれば安心だ。製薬の中核となる創薬の研究棟東や、新薬の安全性評価の研究棟南には近づかない。
それにしても味気ない造りの研究棟。ルービックキューブのような立方体だ。何かの宗教行事で広場の真ん中に置かれた箱のようだ。研究棟北1階廊下の突き当たりに健康食品開発部がある。わずか数名が所属する会社内で最も小さな部署だ。
部屋には窓を向くように机が並んでいた。ケントは一番左端の自分の机に行き、椅子に腰掛けた。腕を上げ、背を伸ばした。伸ばしきった瞬間に、「ケントくん。お戻りね」と、後ろから由美が近づいてきた。うっすらとしたシトラスのいい香りがした。振り向く前に由美が言った。「また、トイレかな?」
由美はいつもそうだ。言われたくないことこそを簡単に口に出す。
返事をする間もなく「ところでケントくん。例の件、宜しくね」と、ドアの開け閉めを頼むみたいに軽い口調で由美は言い放った。そんな簡単なことではない。入社してたかだか3年目の僕が、なぜそこまで責任を負わないといけないのか納得できない。「そう言われても……」と言いかけたが、「何っ!? 何か言った?」と言って、由美はケントを凝視した。
何っ!?っていう言葉は意味を持たない。壁に向かって打ったボールが戻ってきたみたいだ。もう1回はっきり言えよ、と壁が言ったみたいだ。
間髪入れずに、「ケントくん。大丈夫よ。ノー・プロブレムよね」と顔を近づけてきた由美に、ケントはのけぞり、そして下を向いた。「まだ何か言いたいの?」と、由美が言う。こういう時、何か言わないといけないのだ。「自己主張できないのか」と罵られるのだ。精一杯考えて、「あの……ケントくんて呼ぶの、もう辞めてもらえませんか」と声を絞り出した。
「仕方ないじゃない。何度も言うけど。鈴木なんて名字、この会社にはゴマンといるのよ。電話がかかってきていちいち"男性の鈴木ですか?""失礼ですがどの部署の鈴木ですか?"。わかる? この面倒さ。名字は使わない。ファーストネームで呼ぶってルールを会社で決めればいいのよね」
鈴木由美は続けた。よどみなく抑揚を付けて言った。
「これはもの凄いチャンスなのよ。これだ!っていうインパクトのある商品ないでしょ。このままじゃ健食部門なくなるかもよ。ハラールをうまく利用した商品ができれば、この部署の価値も認められて。ね、そうしたらケントくんの目指す基礎研究もどんどんやれて、論文もガンガン書けちゃうんじゃない。お楽しみが待ってます、よね」と、由美は嬉しそうに言った。
いつも思う。由美の言うことは正しいのだと。内容は関係ない。民主主義では多数決が原則だ。会議をすれば由美の主張は認められる。押しの強い由美の意見は正義なのだ。他人への配慮をしないところが、さっぱりとした印象を与え、嫌味にならないのだ。基本的に楽観的だ。むしろ達観している。仕事も人生も。
見た目も大事だ。タイトなパンツに少し短めの着丈のジャケット。健康的な印象のショートカットがよく似合っている。細身だけれど筋肉で引き締まった体は35歳には見えなかった。そんな由美が課長だなんて、この会社で異例の出世だ。まあ、役職は付いたけど製薬部門から健食部門への異動だから格落ちでエリートコースからはずれた感はあるが。だからなのか、由美には少し影がある。仕事に熱意がないわけではないが、心の奥の奥で「まぁ、どうなってもいいや」みたいな。決断する最後でフワァっと気が抜けて魂が落ちていくような。
ケントは意を決して発言した。「……入社してまだ3年目の僕が、リーダーとして、どう進めたらいいんですか……」
腕を組んだ由美は微笑んだ。ケントの勇気ある発言を尊重したかのように。
「リーダーっていってもチームがある訳じゃないから、まずはいろいろと調べてもらって商品のコンセプトをつくってもらえれば、まずはそれでよしとしましょう」。そう言うと由美はヒールを鳴らし行ってしまった。
「ですよね」としか言えなかった。会社の上司が言うことに従えばよい。それだけのことだ、と自分に言い聞かせた。これまでの人生でノーと言ったことがあるだろうか。英会話学校では簡単に「NO!」と言えるのに日本語だと「イヤです。ダメです。できません」とは言えない。「Do you like apples?」には「No」と言えるけど、「リンゴは好きですか」と聞かれたら「まあそうですね」と答える。優柔不断とは違う。自分の考えがないのとも違う。日本語という言語が決断を曖昧にするのだ。日本語という言語は思考を鈍らせ、リンゴをシロップで覆ってしまうのだ。
由美のようになりたいと思った。心に浮かんだ言葉をそのまま口にしたいと思った。僕の心に浮かぶすべての言葉は、言ってはいけないことだと思ってしまう。
考えがまとまらずペットボトルの水を一口飲んだ。水道水で満たしたペットボトルを部屋の冷蔵庫でつねに数本、冷やしてある。一口飲んでから、しかたなく机のパソコンに向かった。「ハラール食品」と検索すると約1万件のヒットがあった。「イスラーム教徒が安心して利用できる食品らしい。豚とアルコールはダメらしい。マレーシアには多くのハラール食品があるらしい」。「らしい」、「らしい」が繰り返し使われている。
椅子にもたれかけ両手を頭の後ろで組んで伸びた。漠然とした情報ばかりで商品開発の糸口がつかめない。気を取り直し再度パソコンで「ハラール」と検索してみた。「食品」を抜いて検索すると随分異なる情報が出てきた。「ハラールとはイスラーム教徒の生活全般に関わる"良いおこない"を指し示す言葉だ」など宗教色の強い解説がヒットした。「結局、宗教なのか」とケントはつぶやいた。ケントの心が沈んでいった。
ケントは一応は神道信者だ。「一応」というのは何か特別なおこないをするとかは全くなく、ただ親が神道だから自分も神道なのだろうという程度だからだ。三重県伊勢市の伊勢神宮に近い場所に代々住んでいたからなのだろう。父親もその父親も神道だ。ただ祖父の信仰心は緩かったように思う。祖父に神道について尋ねてもはっきりとした答えは返ってこなかった。
だからなのかは分からないが、父親は厳格な神道信者だ。そんな父に対して、信仰心の違いというよりもよくある父親に対する息子の心情なのかもしれないが、なにかしらの嫌悪感を抱いていた。神道の教えが理由なのかはわからないが、無口な父親と会話した記憶がほとんどない。神道にはキリスト教の聖書のような書物が存在しない。そのため、解釈は多様だ。
僕にとって神道の教えは父親の躾とイコールだった。「他人に迷惑をかけるな」、「決めたことはやり抜け」、「社会のルールを破ってはいけない」、「嘘をついてはいけない」。父親の言葉は小学校の校長先生の言葉と同じだった。僕の役目は、ただ頭を下げて聞くだけだった。できるだけ主張せず聞くことに注力した。壁打ちの壁のように。心に浮かんだ言葉を胃のなかに流し込み分解することはできた。自己主張のできない性格になっていった。
小学校2年生の夏休みのある日、珍しく仕事が休みだった父親と街に出かけたことがあった。めったにないことなので鮮明に覚えている。映画を観た帰りだった。夏とは言え、夕方近く日が沈んで薄暗くなった駅前。繁華街の隅に浮浪者が地面にダンボールを敷いて座っていた。何も言わず通りすぎれば良いものを、通行人に押し出されるように、その彼の前で立ち止まった。目をそらそうにも相手の目が不思議と心地よく笑っているように見えた。父は軽く会釈した。相手もなぜか会釈をし、震えるような低い声で「恵んでください」とだけ言った。
「あいにくお金を持っていないもんで」と父はポケットに手を差し込んだ。ポケットには財布があり、そこには千円札が数枚入っていることを知っていた。映画の入場券を買うところを思い出した。
「働かないのですか?」と父は聞いた。
彼は何を言われたのか分からない様子で首を少しかたむけてから中腰になった。「恵んでください。持ってるんでしょ」と声を張り上げた。周りの通行人がこちらを見た。
「持ってる訳ないだろ。働きもしない奴にやる金などない」と父は声を荒げて言った。そんな父を初めてみた。父は金がない訳じゃない。嘘をつく必要があったのだろうか。わざわざ嘘をついてまで金を出さない。その行動に意味があったのだろうか。「嘘をつくな。正直に生きろ」と言う父自身がそれに反する行動をした。そう思った。浮浪者の彼の目の中の困惑したものを今でも鮮明に覚えている。「嘘をつくな。正直に生きろ」。この言葉に疑問や抵抗を示すようになった。
あれ以来、僕はなぜだか人前での発言を恐れるようになった。発言が嘘になってしまうのを恐れたのだ。人の目が異常に気になり内向的な性格になった。宗教は自分がしたいことを抑圧する方便に違いない。好んで宗教を信じる人間なんているのだろうか。そんな物を何万人もの人達が信じ行動するのが理解できなかった。理解したいとも思わなかった。目に見えない何かに従うのが嫌だった。
だから宗教と対極にあると思われた理系を専攻し、科学者の道を目指したのだ。それなのに今度はイスラーム教。遠くからは目に見える雲も、近くに行けば単なる水滴だ。頭の中にぼんやりと浮かんだ「ハラール」という言葉。目に見える成分にまで分解して、「これだよ」と提示できるものだろうか。自信がなかった。
ペットボトルの水を一口飲み、パソコンの検索結果をスクロールした。そこには「ハラール基準」という言葉があった。「ハラール基準」を満たせば認証マークが付与される、と書いてある。基準があればわかりやすい。ペットボトルの水を飲み干し机に置いた。
「はい。どうぞ。ケントくん。で、どう? 進んでる? 例の案件」
冷えたペットボトルを持った由美が机の横に立っていた。
そんなにすぐには進まないですよ、と言いたいのをこらえ、いつものように、頭を下げ賞状を受け取るようにペットボトルを受け取った。何かを言わないといけない。由美の要求がエスカレートする前に。「……ハラールってなんだか曖昧な感じで……」
「なに言っちゃってんの。曖昧であれどうであれ、すでにハラール食品は作られて販売されてるのよ。他社にできて我が社にできないはずがないでしょ」腕組みをして由美は言った。「ハラールには基準があるらしいじゃない。基準って言うくらいだからネットのどこかに一覧表でもあって、そこをよ〜く眺めて慎重に商品設計すれば簡単なんじゃないかしら。もっと丁寧に調べて今後の方針くらいはスパッと提示しちゃってね」
しちゃってねと言われても、と言いたいところだが、言ったところでどうなるものか。由美がジリジリと近づいてくる。早めに打ち返さないといけない。ケントは精一杯考えた。出てきた言葉は、「……基準にはむずかしいものもありますよね……例えば……」だった。
「例えばって、何っ!?」と由美が言う。もうこれ以上は打ち返せない……。
「じゃ、例えばよ、宗教の教祖様になりたいと思ったらどうする? ノー・プロブレムよ。まず宗教法人を作る。作るには見本となる前例を調べればいいのよ。すでにある宗教法人がどうやってできたかを調べて、それと同じようにやればいいだけじゃない。調べて行動。それだけよ。よろしくね」
由美は素早く振り返り、何事もなかったかのようにヒールを鳴らして行ってしまった。
由美の言うことは理解できる。科学の進歩も同じだ。論文で明らかになったことを他の研究者が、同じ手順で実験し再現性を確認する。その後、そこに新規性が加わっていく。まずは過去の有名な美しい論文を探せばよいのだ。それでいいんだ。そう思えばいいんだ。
ペットボトルの周りの水滴をティッシュで拭い取り机において、パソコンに向かった。基準があるなら、必ず誰かがその基準を作っている。その誰かに聞けば基準の詳細もわかるはずだ。宗教法人なら文化庁に聞けばいい。「ハラール基準」、「作成者」と検索すると、いくつもの「ハラール認証団体」がヒットした。どこが信頼できるのか検討がつかない。そのうちの一つにイスラームビシネス研究所があった。
怪しげだが、なぜか心に引っかかるものがあった。