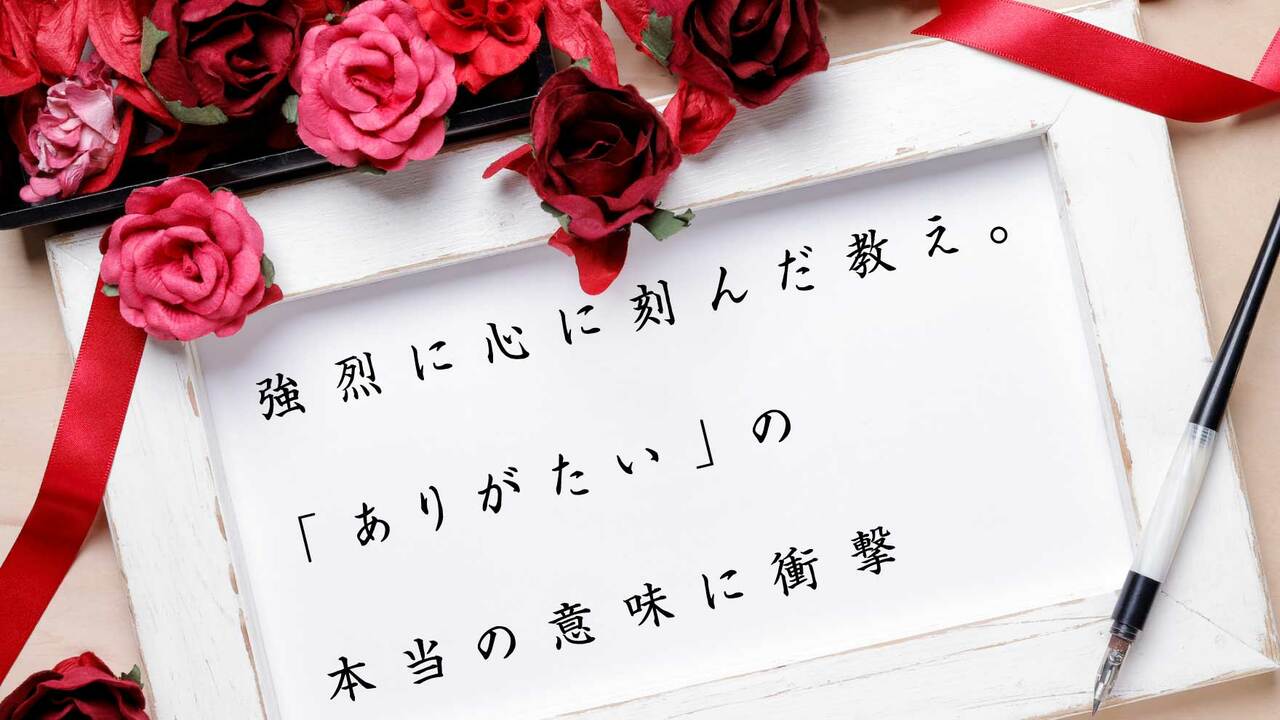エミリー・ディキンスンの世界
エミリー・ディキンスンは十九世紀、南北戦争時代のアメリカを生きた女流詩人である。生前に発表された作品はわずか七篇で、ほとんど無名だった。評価されるのは二十世紀になってからで、千七百篇以上も遺した作品は現在世界中で愛誦する人も少なくない。エミリーは結婚せず、生涯を生家の家族のもとで過ごした。また時代も女性の活動が極めて限られた範囲だった時代だけに、その詩が表現する世界は日常のささやかな世界であり、繊細な心象風景である。
先に掲げた詩にしても、日常の庭の風景、その季節の変化をとらえただけの作品というようにも見える。だが彼女の作品には決して単なる眼前の季節や風景を詠ったというだけではない深さというか、不思議な意味深さが感じられる。
エミリー・ディキンスンの作品には南北戦争という時代の影が色濃いと言われている。南北戦争は正しさを求める戦いという側面をもっているが、その戦争での死者に対する思いが彼女のなかではキリスト教的な殉教の死と結びつき崇高な憧れになっているという研究者の説を見るとき、自身の周辺に絶えずあった死と死者たちへの思いが彼女の作品に影響を与えないはずはないと思われる。それは何気ない日常を詠う詩のなかに漂う切なさや悲哀感となり、命を考える独特の視点にもなっているような気がする。
たしかに、過ぎて行こうとする晩夏、その暑さからやがて来る冷涼の秋へ移り行く季節の動きを感じているこの詩にも日常の庭の光景とその変化を見るという詩人の眼差しだけでない深さがある。日常の日々の光景を突き抜けて、そこには大自然やそれを動かしているものの存在、与えられている命の意味を考えようとしている視点があるように感じられる。生きている自分の人生の意味と自然の運行とを重ねあわせて畏怖している心を感じないわけにはいかない。
この詩はエミリー・ディキンスンの「自然16」(『エミリ・ディキンスン詩集』国文社、中島完訳二十五ページ)に収められている。