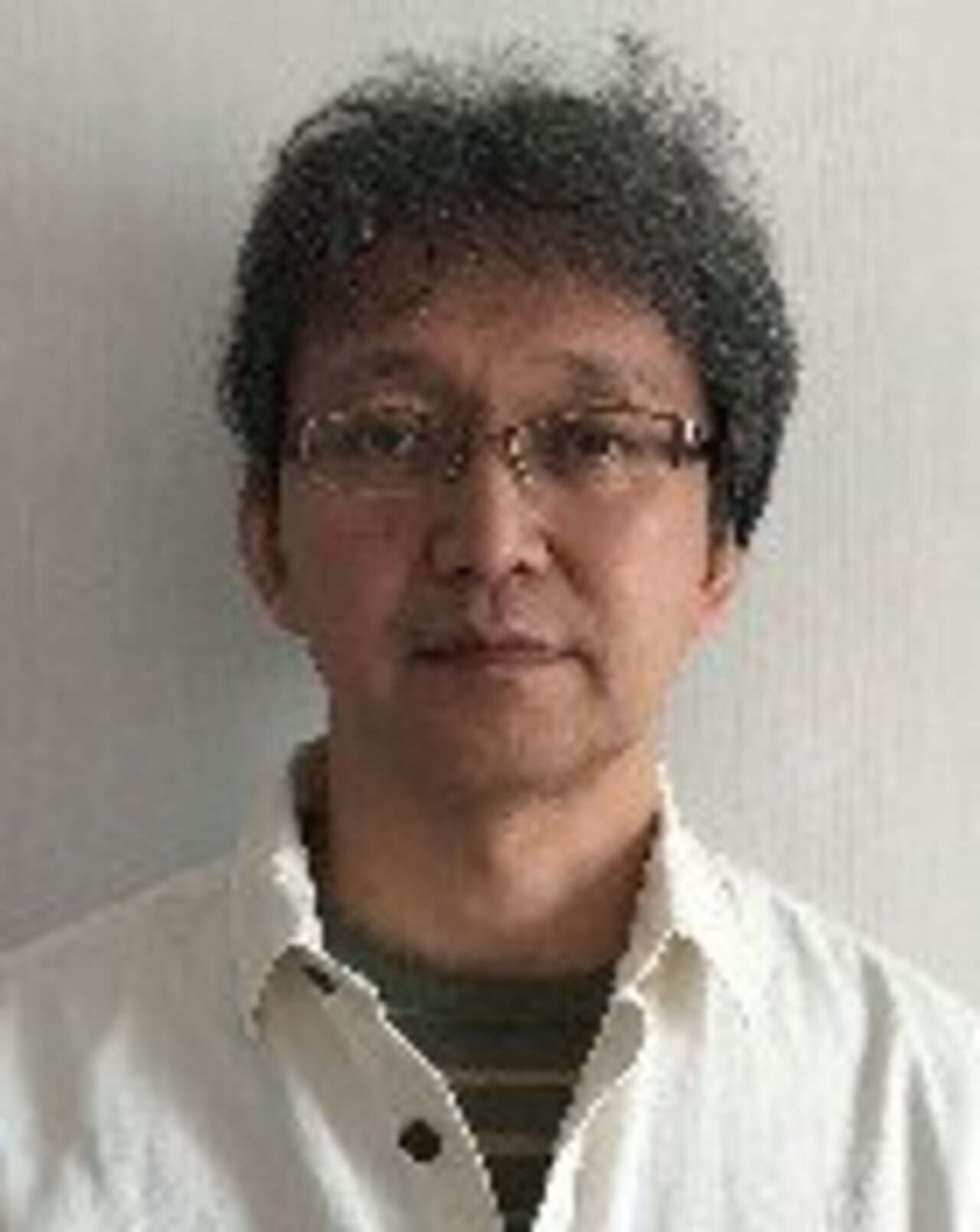「弾く」と「聴く」
そよ風に青葉の匂いが交じる季節を迎えていた。
近くの大庭城址公園の桜が三分咲きになったと知らされた日、和枝と廉は東京メトロ丸ノ内線で中野坂上に向かっていた。
「音の質感っていうのかな、たとえば乾いているとか湿り気があるとか、よく通るとか籠もった感じ、とかね。あと低音、中音、高音のバランスはどうなのか、弾いていて心地良いのか、違和感があるのか……。そういう楽器それぞれの持ち味はもちろん、試弾していると『ピアノ本人』に直接聞いてみたいことが山ほど出てくるわけよ。でも持ち時間の制約もあるからさ、ちょっと親しくなりかけてきたところで隣のピアノに移るでしょ。そうすると最初の数小節でさっきのピアノの感触はヒューってしぼんでいっちゃう。そんな感じなのよ」
「じゃあ、試弾を続けていく、今の探し方自体意味がないじゃん」
「そうとも言えるわね。でも、今まで八台弾いてきたけどしっくりくるものに出会わなかったというのは本当よ。あ、いや、スタインウェイを入れたら十台か。ウチに縁がない名器を数に入れても仕方ないもんね」
「スタインウェイは正直どうだったの?」
「タッチも音も『おおーっ!』って感じはあった。でも好きな音ではなかったんだな。中古品に染みついた癖なのか、単に調整の問題なのか分からないけどね」
ピアノ選びもなかなか楽じゃないなという思いが廉の頭をよぎったとき、背後からもふわっと蛍光色の明かりに包まれ、電車は中野坂上駅に滑り込んでいた。
地上は風が立って埃っぽく、青梅街道の二つ先の赤信号が朱色に霞んで見えた。
めざすのはベーゼンドルファーのショールーム。歩いてすぐだった。そしてガラス扉、防音扉と二つのエントランスをくぐると、そこは空気の重い異質の空間。ピアノ四台の息苦しいまでの存在感がそうさせていた。
「オーストリアの至宝」と言われウィーンっ子に愛され続ける楽器。調度品としても珍重されるという美しい外観。堅牢な漆黒の外枠に囲まれ、ブロンズ色の鉄骨が覗く。三本の脚のラインもたっぷりした美術品のような意匠。そして和枝にとっては、もう長い間ずっと気に掛かっていたピアノメーカーだったのだ。
和枝と廉は十七年前の一九九三年の元日、鎌倉の佐助に住む共通の友人である木南理子の紹介で知り合った。
木南宅に招待されていた二人。東京・中野の会社の独身寮から来た廉は約束の時間に着いていたが、高森和枝は優に三十分遅刻して玄関に飛び込んで来た。
「ごめんなさ~い! でもシフォンケーキ作ってきたので許してください」と屈託のない笑顔を振りまいてテーブルにケーキを置き、廉の斜め向かいの席に着いた。廉はその瞬間「これはいい!」と一も二もなく嬉しくなっていた。
余談になるが、和枝は三姉妹の末っ子で、廉はそこからさらに十年ほどさかのぼる大学時代、長女の高森真咲とはすでに知り合っていた。
東京から来た男子四人と鎌倉に住む女子四人が、同じく木南宅に集まる「合コン」の席だった。
廉には、きょう会う和枝が、その合コンで特に印象に残った「あの真咲さん」の妹と分かっていたので、内心かなり期待はしていた。
とはいえ、こんな場面でいつも心を曇らせる自分の脚の事情を素通りできるわけはなかった。期待が大きければ尚のことだった。
廉は、和枝が脚のことに気付く瞬間が怖くてたまらなかった。