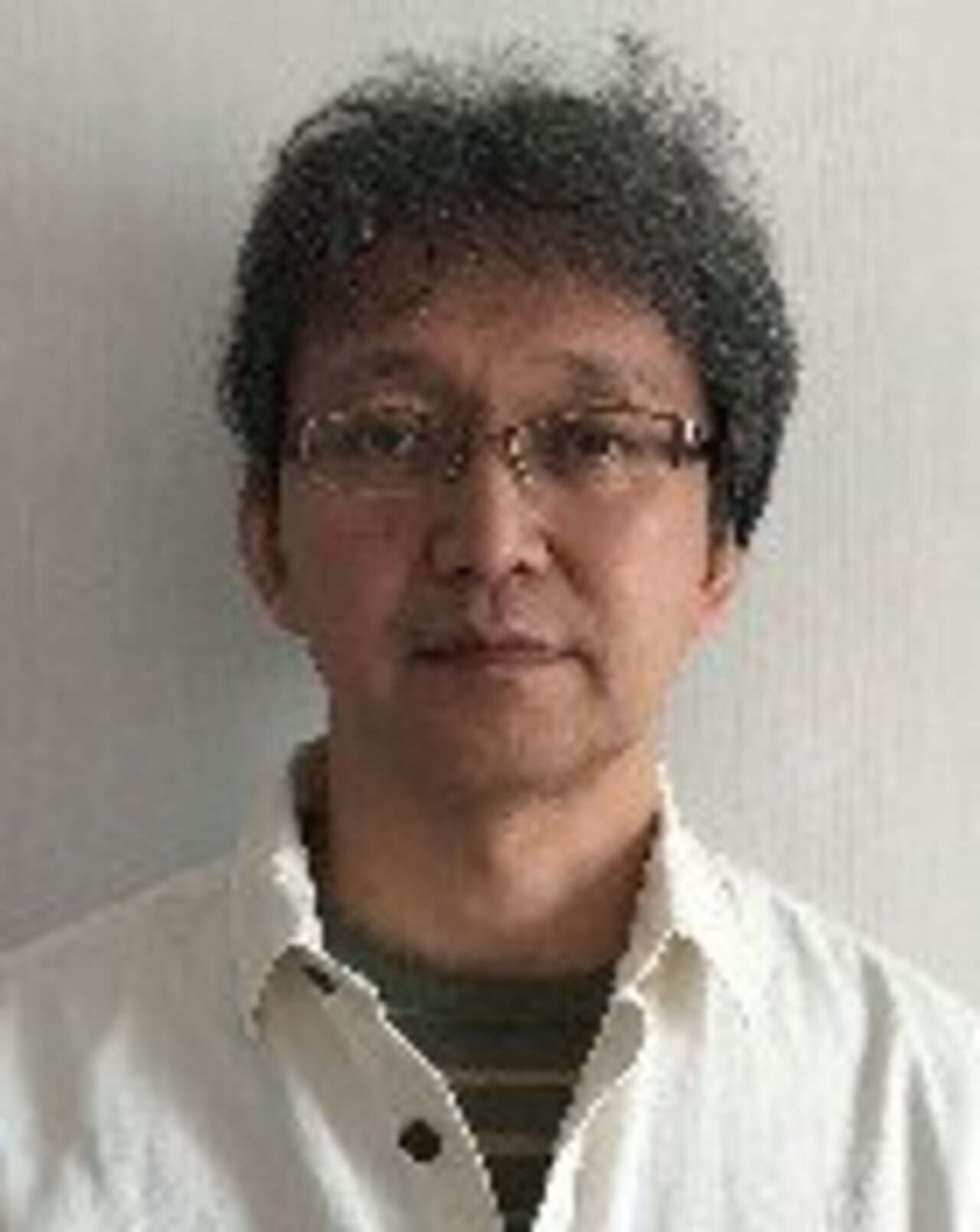主題 ハ長調
みなとみらい
次のゲートもその次も「満車」の赤ランプは続き、のろのろ運転のまま、ランドマークタワーを大きくぐるりと一周していた。やっとのことでクイーンズスクエア横浜の地下駐車場に潜り、車を停めると、その先はみなとみらい線に乗り新高島駅に向かう。
二〇〇九年十一月下旬の日曜日の昼下がり、平林廉と和枝にとっては、久しぶりの夫婦二人だけのお出かけだった。そう、「お出かけ」という表現がしっくりくる、わくわく愉しい、ちょっと記憶に残るひととき。今思えば、この時が「旅」の始まりだった。
新高島駅から地上に上がり、一歩ごとに硬いリズムを腰に送ってくる石畳の歩道を、左脚に麻痺がある廉は注意深く進む。廉は生後まもなくミルクを受け付けない症状が現れて、郷里新潟のN大学病院で幽門狭窄症と診断された。百日目には開腹手術を受け一命は取り留めたが、少し体が動かせるようになってくると、今度は別の懸案が見つかった。左半身、特に脚部に麻痺が見られたのだ。
小学一年生の夏、廉は小児療育センターに入院した。運動機能を改善するための一年がかりの治療が始まり、内翻足を矯正するギプスを装着したり、股関節の可動域を広げるための手術を受けたりした。検査と治療を繰り返す少年期から、青年期へと成長しても、廉の左脚の麻痺が消える日はついにやって来なかった。ただ日常生活で不自由を感じることはなく、スポーツも臆せずやってきた。
四十八歳になった今でも、とりわけスキー愛は人並み以上と言えた。