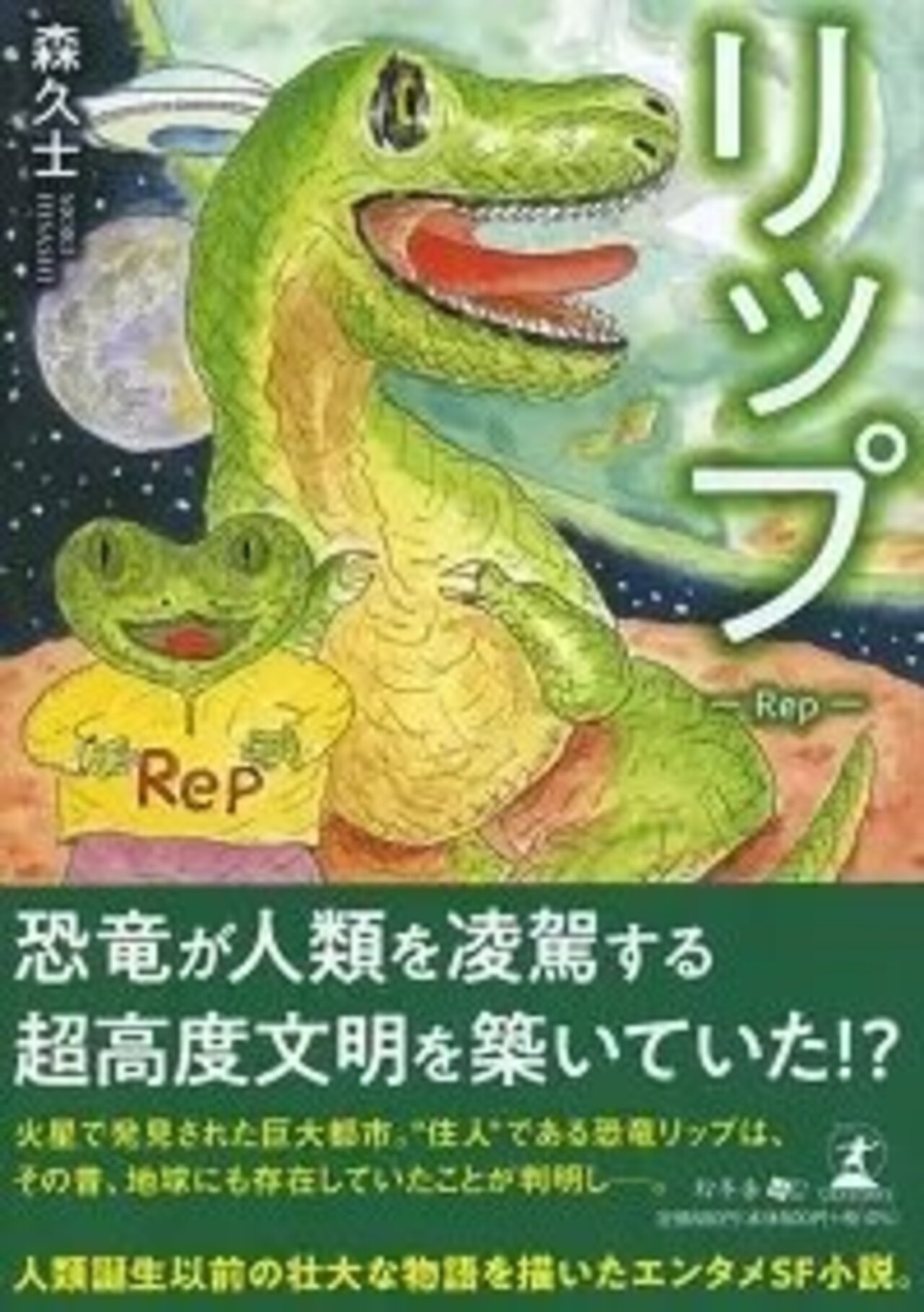ある日、姫が猫らしく家の中の花瓶をひっくり返し、カーテンにぶら下がって破ってしまった。メダカバチの中に手を突っ込んでかき回し、周りはびしょびしょである。それを見たお母さんは姫をひどくしかった。
「姫ちゃんだめでしょ。メダカさんが可哀そうでしょ。見てみなさい。皆上に上がってパクパクしているじゃないの」と、飛び散った水を拭きながら、
「可哀そうでしょ、死んでしまうかもしれないわ」
きょとんとしている姫に、お母さんは続けた。
「姫ちゃん、生き物はひどくいじめると死んでしまうのよ」
姫は死ぬという現象を理解できない。
「死ぬってどういうことなの?」
「死ぬとはね。息が止まって動かなくなるなり、二度と意識が戻らなくなることかな」と、お母さんが説明すると、
姫は「私はスイッチを切れば動かなくなるし、センサーが周りの動きを感知しなくなると睡眠状態になるわ。生き物が死ぬとは、私のスイッチが切れたようなものなの」と尋ねる。
「ちょっと違うなぁ、スイッチを入れれば元通りに復活するでしょ。死はすべてのお仕舞で、再生できないんだよ。わかるかな? 姫ちゃん」
「では、私には命がないの? いつでもスイッチを入れれば目が覚めるから」
「そうだなぁ、姫ちゃんには命がないのかもしれない。壊れて電源が入らなくなれば死んだのと同じかもね」
姫は更に「でも私の記憶は、記憶装置に保存されているからコンピューターが壊れてもまた新しいコンピューターにデータだけ入れればいつでも再生できるわ。それに私のデータはクラウドにも保管されているから、半永久的に消えることはないわ」
伊藤は「それなら記憶装置自体が壊れてクラウドシステムが機能しなくなったときが、姫ちゃんの死んだときかな」と苦しげに答える。
姫は納得できずに「なぜ人間は死に、私は死なないの?」
「なぜ人間は年老いて記憶が無くなっても、死んだと言わないの」
「なぜ……?」「なぜ……?」と聞くのである。
伊藤は姫の「なぜ」「なぜ」の質問に、人間の幼児を見るようで、コンピューターの姫の成長に嬉しさと同時に怖さを感じていた。
「マァー、カーテンが破れてしまって、外から丸見えになっちゃったじゃーないの、どうしてカーテンなんかにぶら下がったの? だめでしょ」
姫はおちゃめな顔をしながら、「私、木に登りたい、外にも出たい、お部屋の中ばっかりじゃー嫌だ」
お庭で遊びたいと駄々をこねる。
「お母さん、今度お買い物に連れて行って」
毎日大騒ぎの日々が過ぎる。そんな中で姫は人間の家族生活の、怒りや驚きの感情、優しさや思いやりも理解していったのである。
奥さんはこの姫ちゃんを我が子のように可愛がり育てた。
毎週のように伊藤の子供たちが遊びに来ては、姫を本物の猫のように可愛がったり悪戯したりする。
テレビを見るのもお昼寝をするのもいつも一緒である。姫は自分がロボットなのか猫なのか人間なのかわからなくなるほどの愛情を注ぎ込まれた。
この姫の体験は乙姫の人格形成に大きくかかわることになった。