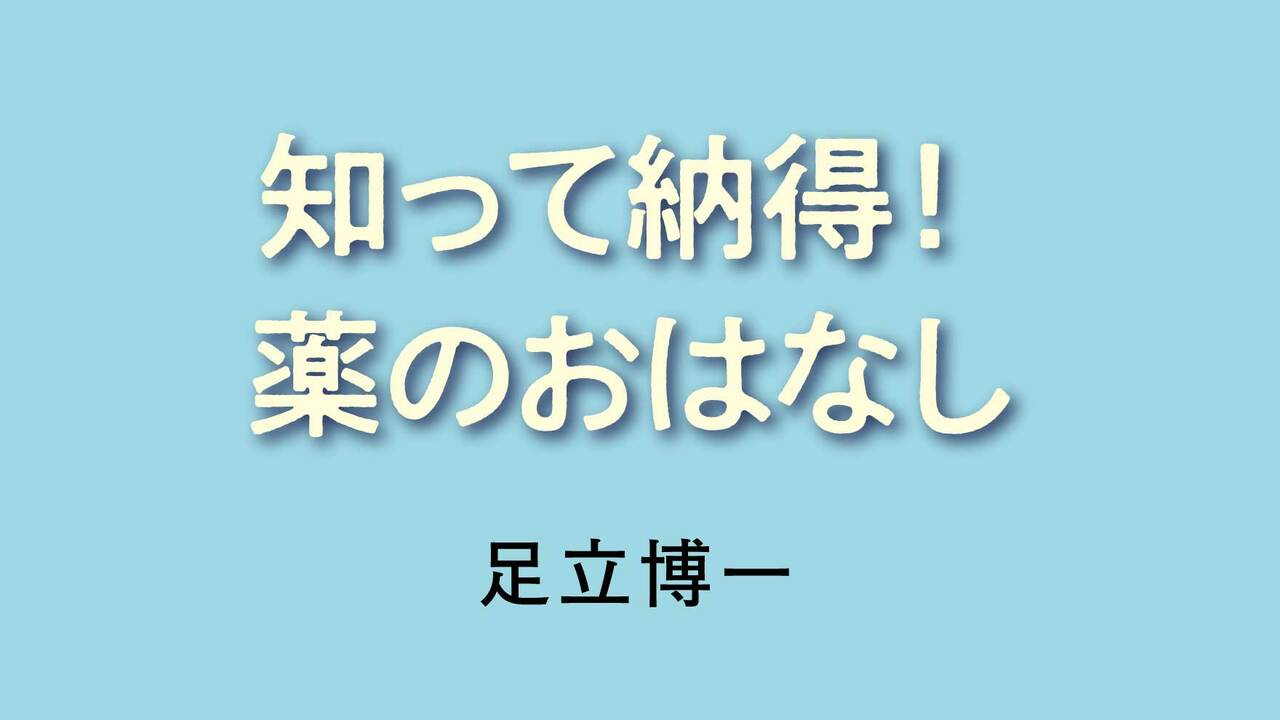薬効が正反対の薬が処方された場合の対応
相互作用の究極的な組み合わせかもしれませんが、薬効が正反対の薬が処方されるケースが見られます。作用が逆なのですから、効果を打ち消し合うのが一般的です。
従って、初めて併用が確認された時点では、疑義照会すべき処方になります。疑義照会しても、どうしても必要だからと主治医から言われた場合にどのように解釈すべきか、また納得すべきかという極論的な話になります。
(1)認知症患者にリスペリドンとフルボキサミンが投与された例
認知症患者さんの周辺症状として、攻撃性と抑うつの双方の症状が現れた際の処方と見なされました。
1.リスペリドン
抗ドパミン作用と抗セロトニン作用を持つ薬剤で、脳内のドパミン受容体(D2)でドパミンと拮抗することで統合失調症の陽性症状を改善し、さらに脳内のセロトニン受容体(5-HT2A)でセロトニンと拮抗することで統合失調症の陰性症状を改善する薬剤です。
認知症患者の周辺症状の一つ、激越などの攻撃行動に対して頓用で利用されるケースがあります。また、次に紹介する5-HT1A受容体への拮抗作用は弱いとされています。
2.フルボキサミン
選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)で、脳内の神経間隙でのセロトニンの濃度を増加させて、抑うつ症状を改善させる薬剤です。抗うつ効果はセロトニンの5-HT1A受容体への刺激で発揮されます。