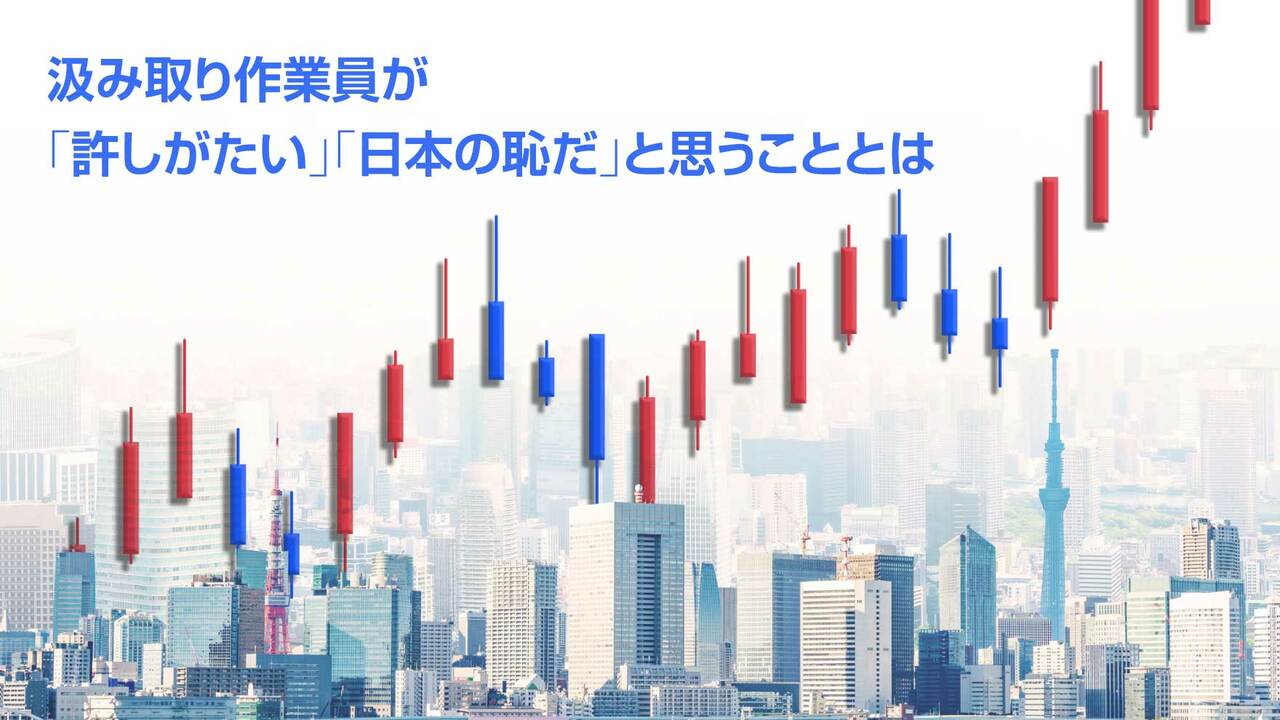健一の障害の症状
牛塚教授から友人として健一に寄り添うことを託された遠藤は、大学四年の頃から演劇にはまり、卒業後は特に唐十郎に憧れ、当時流行りのテント劇場として劇団「シルバー・テント」を自ら主催し、アングラ劇にのめり込んでいった。
アングラとは、アンダーグラウンドの略で、近代演劇が取り扱うことを拒絶してきた、土俗的なものを前面に押し出した演劇である。そこには、見世物小屋的な要素を含んだものが多く、公演は、サーカスのように日本各地を回って、公園の空き地や神社、寺の境内、河川敷などにテントを張って、そこを劇場にして行われた。
遠藤が主催する「シルバー・テント」は前衛的でシュールな内容のものが多く、頭をモヒカン刈りにしたり、前張りをしただけの全裸の身体にボディーペインティングを施してのパフォーマンスを織り交ぜたりしていた。
しかし、その内容には、貧しい田舎の農家の青年が都会の生活を夢に見ながらも、鍬をふるい、地べたを這うように草取りに励む、牧歌的な場面設定のなか、心の葛藤を描くものもあった。
遠藤は、テント劇だけでは生活ができないので、昼間は建築現場の土木作業員をしていた。一方、健一は就職活動に失敗したが、遠藤と同じく東京に住んで、ビルの清掃のバイトをして生活していた。
健一と遠藤の交流は卒業後も続いていた。遠藤は自分の演劇の夢を追いつつも、健一のことを気に掛けて就職先を一緒に探してくれていた。健一も演劇という夢を追い続ける遠藤をなんとか応援したくて、テント劇を観に行くだけではなく、前売りチケットを駅前で売ったり、テント設営の手伝いをしたりしていた。
健一が、前売りチケットを売るために、太いマジックで「シルバー・テント」と書かれた麻の袋に穴を開けて、頭と腕を通して、駅前や上野などの公園に「チケット発売中」の看板を持って立っているだけで、不思議とチケットが売れた。
いつもは無視されるか、横目でチラチラ見ながら避けて通り過ぎられる健一だったが、時々足を止めてチケットを買っていく人が現れはじめた。そして、その間隔が、どんどん狭まって、人盛だかりができることもあった。
手の不自由な健一が代金のお釣りをなかなか渡せないでいると、「公演費用の足しにしてください」と言って受け取らない人もいた。そういう人はほとんどが演劇かバンドなどの経験者だ。彼らはいかに一回の公演やコンサートを開くことが大変かを知っていて、なおかつアンダーグラウンドで行われている芸術をこよなく愛している人たちだった。
健一は、このような経験から芸術や文化を愛する心が、人間の間にできる差異という壁をこんなにも簡単に、しかも心地よく壊してしまうことを確信するようになっていた。そして、テント劇を主催している遠藤を改めて尊敬し直すのだった。
「芸術で空腹は満たされない」と言っていた学友がいたが、健一の心は心地良い満腹感で満たされていた。