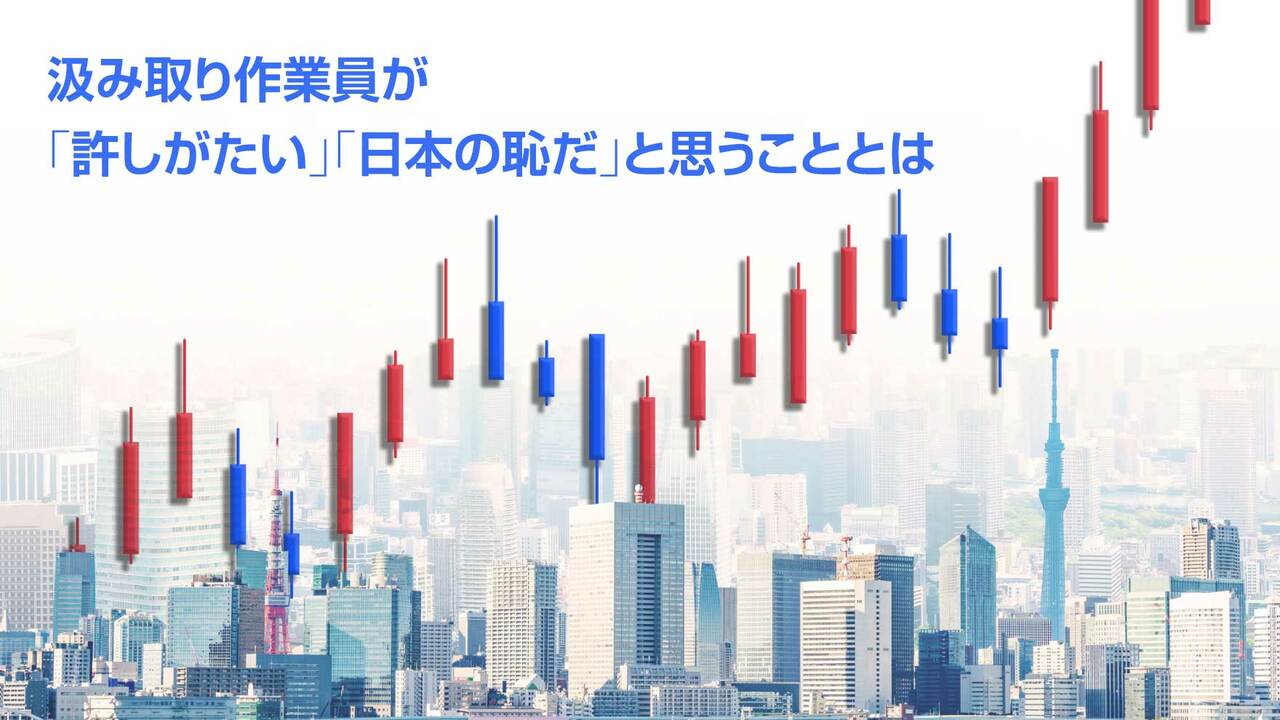その当時はロッキード事件などが明るみに出て、政財界の汚職腐敗が特に問い質されているときだった。遠藤は、このような社会の汚れた現実を自分の演劇で変え、浄化していくにはどうすればいいのかを思い悩んでいた。
健一は、「その日が楽しければよい」とする快楽的、刹那的に生きる同世代の若者が多いなかで、そんな崇高なことを考え悩んでいる遠藤を凄い奴だと改めて思った。
しかし、そのうち遠藤は、「桜は、散るから美しいんだな」とか、「日本のゼロ戦特攻隊の潔く美しい死が、戦争を終わらせてくれた」などと言うようになり、しばらくすると三島由紀夫の割腹自殺を賛美するようになった。遠藤は、俗に言う「滅びの美学」「死の美学」に傾倒していったのだった。
そして彼の書く脚本は、どんどん「散り際の美しさ」なるものを追求するようになり、集団自殺や組織の破壊による革命を描いたものが、多くを占めるようになっていった。健一は心配で仕方がなくなり、二日と空けずに遠藤のアパートを訪ねるようにしていた。
しかし、そんなことも虚しく、劇団が公演のために張った、銀色のテントのセンターポールの照明を固定するためのフックにロープをかけて首を吊っている遠藤が、劇団員によって発見された。
遠藤が最も神聖な場所としていたテント劇場。その地面に敷かれた、新調したばかりの濃い緑色のゴザの上に、彼が失禁して垂れ流した小便が、だらりと伸びた足の親指の先から滴り落ちていた。半開きの口からは舌が飛び出し、よだれが流れ、顔は鬱血して紫色に変色していた。遠藤が吊り下がっていたポールの後ろ側には、「私は自身の死を持って、腐敗しきった政財界の浄化を訴える」と書かれた短冊型の色紙が張り付けられていた。
このことで間もなく劇団「シルバー・テント」は解散した。健一はたった一人の親友を失ってしまった。それも健一を見守り、励まし、助けるはずの遠藤が、健一を救うどころか自分自身を見放してしまったのだ。