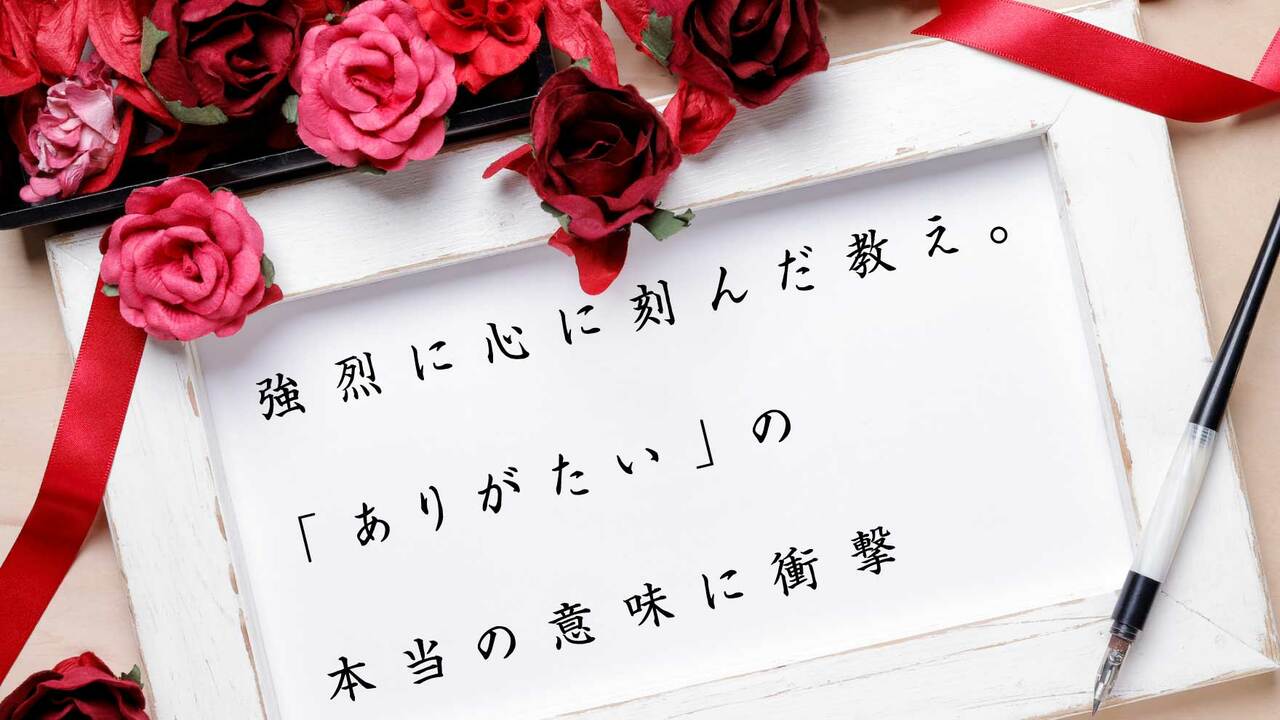関ケ原の戦い直後、正式な江戸幕府発足前から家康は矢継ぎ早にさまざまな施策を打ち出している。大久保長安による東海道、中仙道の一里塚設置、宿駅制を設けた伝馬の整備などはその代表的な例である。また各地の金銀山の開発を進め、幕府財政の安定を図るなど、それらの施策を見ると、家康がただ待っていただけでなく「自分の出番になった時になにをなしたいか」「なにをしなければいけないか」を常に考え、計画を立て、その実現をイメージしてきたにちがいないことがよくわかる。
江戸幕府初期の施策をみるとき、長い戦の世で自分の出番を待つ間、家康が思い描いていた国家像があったのだと感じられるのである。長い戦乱の世が続いて荒れ果てた国土の川や道路や街のインフラを整備し、往来の安泰を図り、鉱山を開発し国土を富ませよう、と強く願っていたにちがいない。また、そのためにこそ人材を集めていたのだ。
希望を持ち「長い時間を耐える」ということが、決して、「時間を我慢する」ことではないことを家康の人生は教えてくれる。そうして、長い時間に耐えることは、いつの間にかその人間の肚も作るにちがいない。時間に耐え、希望を持つというとき、それはただの夢物語を思うことではないのだといやというほど実感させられるのだ。
私自身の人生は考えていたものとはまるで違うことはもとより、想像したこともない世界が目の前に展開していき、当然想像を超えた役割に苦闘した。そうしたことのすべてが自分のしたいこととは、まるで正反対だったといってもよい。夢にも思わなかった挫折や展開に翻弄され、思ってもみなかった世界で働き、思いもしなかった人生が積み重なって現在にたどり着いている。
若かった私がたどり着くはず、たどり着きたいと切に思っていた地点とはずいぶん違っているのだが、いまになってみると、これはこれで良かったのだと思っている自分に気が付く。というより、これこそが私にとって必要な人生の道だったと確信できるようになっている。
「希望せよ」と教えられ、どんな状況でも失うことのなかった「希望」に導かれ、長い時間を超えて、いま、私はここにたどり着いている。
「巌窟王」の主人公エドモン・ダンテスは最後に自分を陥れた相手すべてに復讐を果たし、奪われたすべてのもの以上の財を得、しかも、若い美女を我がものにできるのだから、私だって希望を失うわけにはいかなかったのだ。
私が越えてきた長い時間が、私の希望をただの夢物語で終わらせないことをいまは願うしかない。