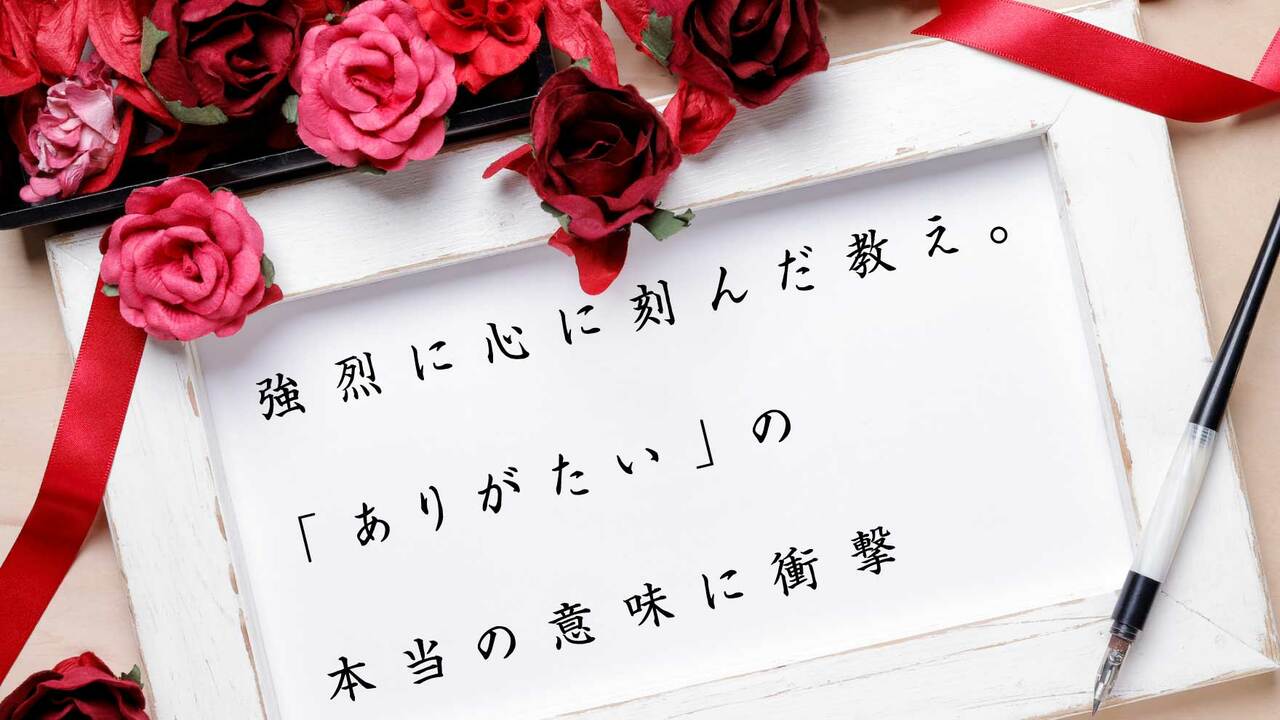なにもできないならせめて笑顔ね
なにもできないのだから、せめてにこやかな笑顔や柔和な顔、優しい言葉で相手を心地よくしてあげなくてはいけない、というのだった。相手を傷つける痛烈な言葉を私が使えることをとても心配していたのだ。
こんなやり取りは子供時代を脱したころになってもずっと続いていた。妹が嫁いで家を出、父が亡くなった後になっても母は時々「顔施」の話を持ち出した。二十代、三十代の私は多分まだ仏頂面で愛想が悪く、嫌いなものを激しく攻撃していたのではないだろうか。「顔施」も「愛語」もへったくれもない女だったのだろう。
「いいの、私はそのうち財施の人になるの。たくさんのお金を寄付する人になる。だからほかのはしないでいいの」
私は母の説教に、いつもそううそぶくのだった。
子供のころから、私はなぜかたくさんのお金を寄付する人になりたい、と言っていた。母は本当に私には手を焼いていたろうと思う。
だが、本当の「いざ」という、そのときがきたのに財施などとは程遠いところに自分がいることが嫌というほど身に染みた。財施どころか、本当になにもできない自分。家族のために家事をしたり、子供を育てたりしていないのだから、少しは多くの人の役に立つ、立派なことをしなくてはいけない、というような強迫観念はずっとあった。それなのに、立派なことどころか、ほかの人たちが易々とできていることが、自分にはなにひとつできないのだということが衝撃だった。
そんな思いに打ちひしがれていた日々に、ふっと「顔施」という言葉が脳裏に浮かんでくることが何度も続いた。