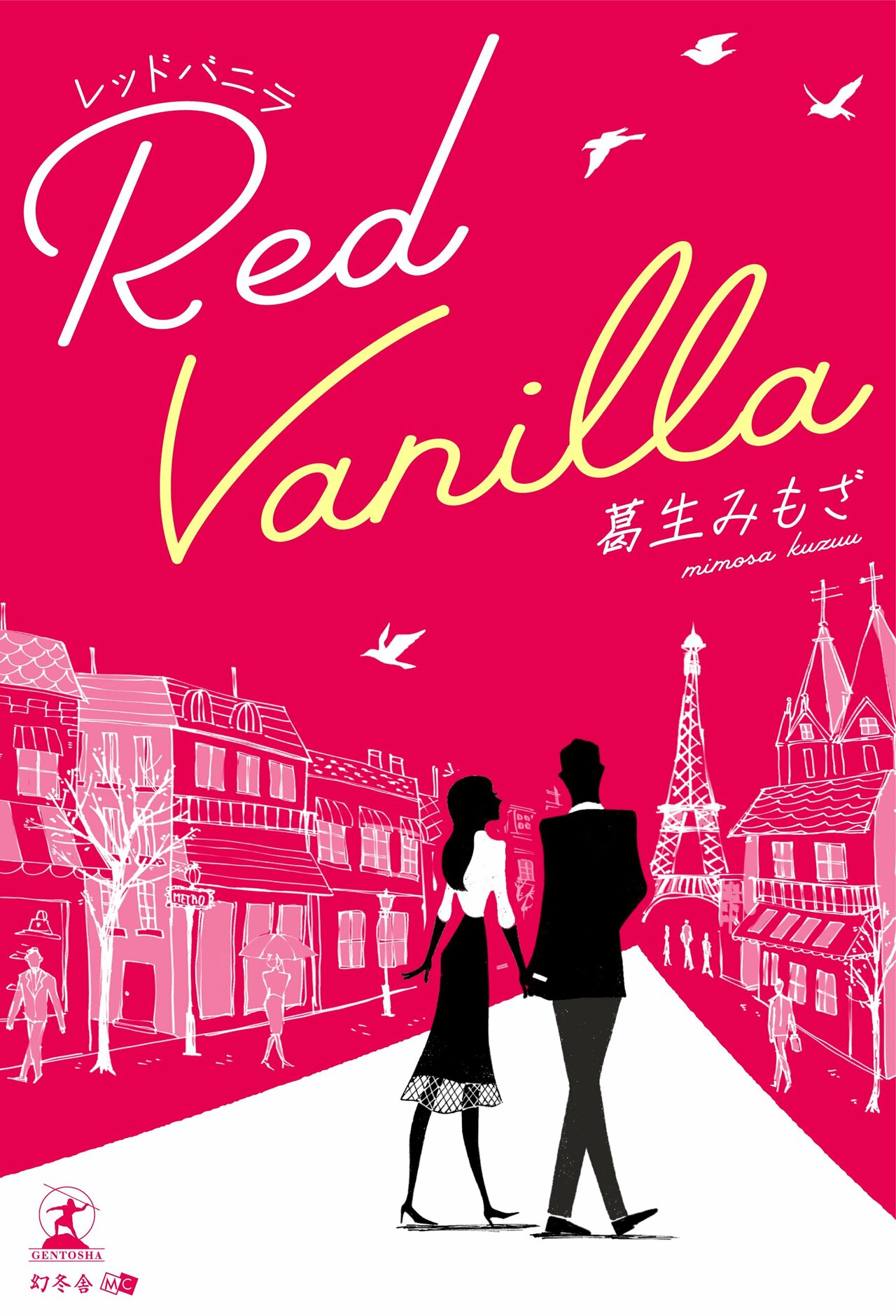さて、きっかり午後十一時半になった。最後の客は帰り、私のグラスもペーパーで折った鶴もぐにゃと片付けられて、私も持ち物をバッグにしまう。店のスタッフがカーテンを閉め始める。キッチンからコックが階下に着替えに行く。途中ちらと私を横目で見ながら、意味ありげな表情をする。
コックの白い帽子が下に消えていくのを見ながら私は「あ、地下」と密かにつぶやく。私は降りたことはないけれど、そうよ、この店には地下がある。
ということは、それはかつての穴倉酒場といわれた地下クラブの名残じゃないかしら。お酒や煙草や香水も入り混じった地下で、夜ごと繰り広げられるダンス。お酒と音楽で上気した実存主義者たちの会話。一九四〇年代の息苦しくなるような男女の情景が漂ってきそう。
遠いパリの歴史の中に包まれながら、私はコートを羽織った。彼が「行こう」と私を促す。
彼はカーテンを引いているスタッフに何か言っている。その若者は後ろ向きに返事をする。機嫌が悪いのかな。私は陽気に「オルボワール(さようなら)」と声をかけるとその若者はやはりカーテンを引いたまま「オルボワール(さようなら)」と返してくれた。これから連れだって出かける二人を見るのは野暮だと言わんばかりだった。
深秋や背中で送り出すデート