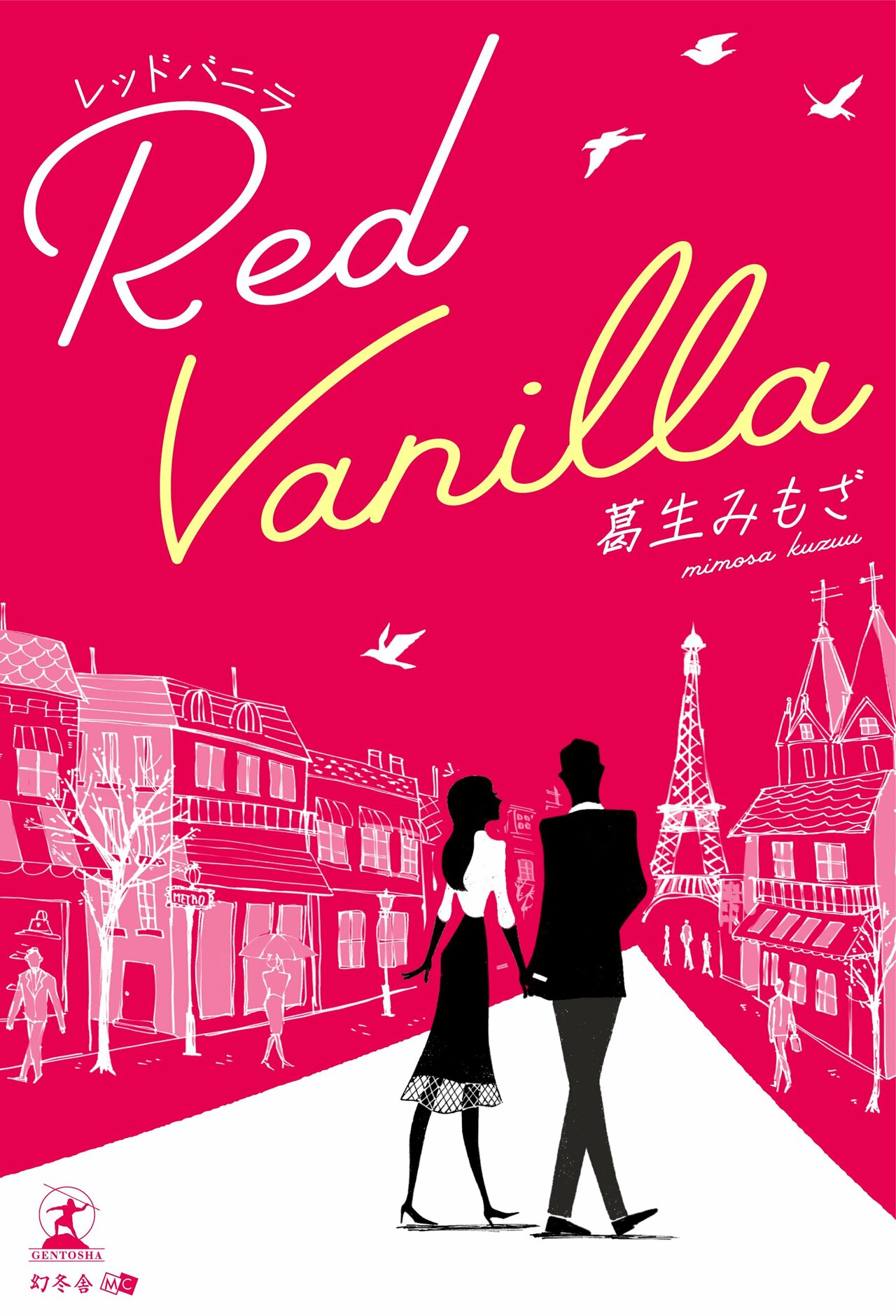サン・ジェルマン・デ・プレ秋灯
店を出ると彼は早足だった。追いついていくのに私は小走りに彼のあとを追う。彼が手を差し出してきたので私も彼の手を取る。自然なことだった。
パリの下町の夜は初めてだ。何も知らないのだから、手をつないでもらうと安心できた。私のヒールが石畳を蹴る。コツコツと深い音だった。店はどこも閉まり、暗い中にも街燈がちらちらと石畳を照らし、私たちの翳(かげ)をつくる。
彼はどこへ行こうとしているのか、何を探しているのかわからないまま彼のあとに従う。
路地を曲がりパッサージュ(屋根のある細い抜け道)に向かうも、彼は困ったようだった。
「これから歩いて君のホテルまで送るのはどう? ホテルはわかる?」
たしかそんなことを言ったのだと解釈した。私も今思えば、かなりバカだ。どこかの店で放られたら、どうやってホテルまで帰ろうかと心配していたものだから、ホテルまで連れて行ってくれるならよかったと思い笑顔で「うん!」と言ってしまったのだった。