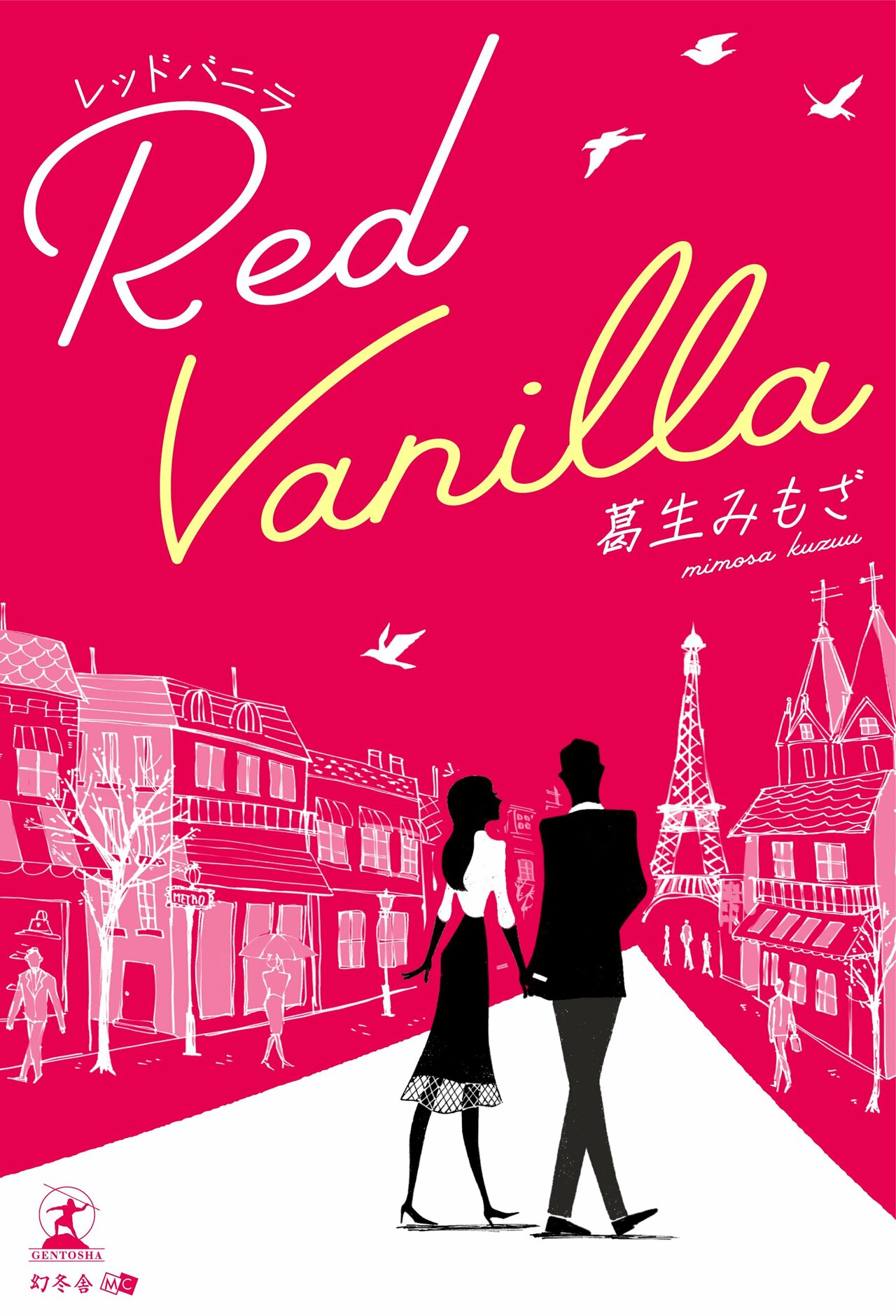サン・ジェルマン・デ・プレ秋灯
外国かつパリであるから、しかも子供でもあるまいしという心持ちもあり、私は別にキスを交わしたからといって、べたついた気持ちにはならない。もともとそういう性格なのだ。
しかし、かなりロマンチックな気分にはなっていた。彼と会話をしていたけれど、何を話していたのかよく覚えていない。ポンヌフを引き返すあたりで、「ねえ、夜のポンヌフだわ」と私が感激して言うと「そうだね、ポンヌフだよ」とだけ返ってくる。それが日常である彼にとっては当たり前だろう。あ、また。二度目のキスはさらに甘く、私の唇はもはや彼のものとなった。長いキスを受け止めきれずに私が首をひねって唇を離すと、彼もようやく身体を離してくれた。私たちの距離は確実に近くなった。
私のホテルは彼の店をはさんでポンヌフと反対方向にある。
「ホテルはどこかわかる?」と聞くので「わかるわ。ホテル・サンジェルマン・ドゥ・パリよ」とホテルの名前を告げた。ところが、そのホテルの名前を和訳すると「パリのサン・ジェルマンのホテル」となるので、私が「ホテルはサン・ジェルマン・デ・プレにあるのよ」の意味で言っていると彼が解釈していることが様子でわかった。でも、うまく伝えられず、ホテルまでの道もわかるので、そのままにしておいた。
私たちはうす灯りのドフィーヌ通りを抜け、間もなくサン・ジェルマン大通りに出た。
彼が立ち止まって言う。
「ここがサン・ジェルマンだよ。ホテルはどこ?」
「あっちよ」
「あのホテルじゃないの?」
「ちがうわ」
「きみはわかるんだね?」
「うん。たぶんね」
「…………。」
彼はどこか納得できないようだったが、私がわからなければ致し方ないわけで、この大通りからは私が彼をナビゲートするかたちになった。もうすぐサン・ジェルマン・デ・プレ教会だ。私がずんずんまっすぐ歩くだけなので、不安になった彼が私に尋ねる。
「わかる?」
「たぶんね」
「たぶん……」
と彼がつぶやく。大丈夫だって。わかっているから。私は「ふんふん♪」と夢見心地で大通りを歩く。向こうに大きなホテルの明かりが見える。とても泊まることはできないであろう素敵なホテル。通りは明るくはないけれど大きな建物の明かりのおかげで真っ暗じゃない。深夜のせいか、人通りもない。もうパリ市民は眠っているのか。