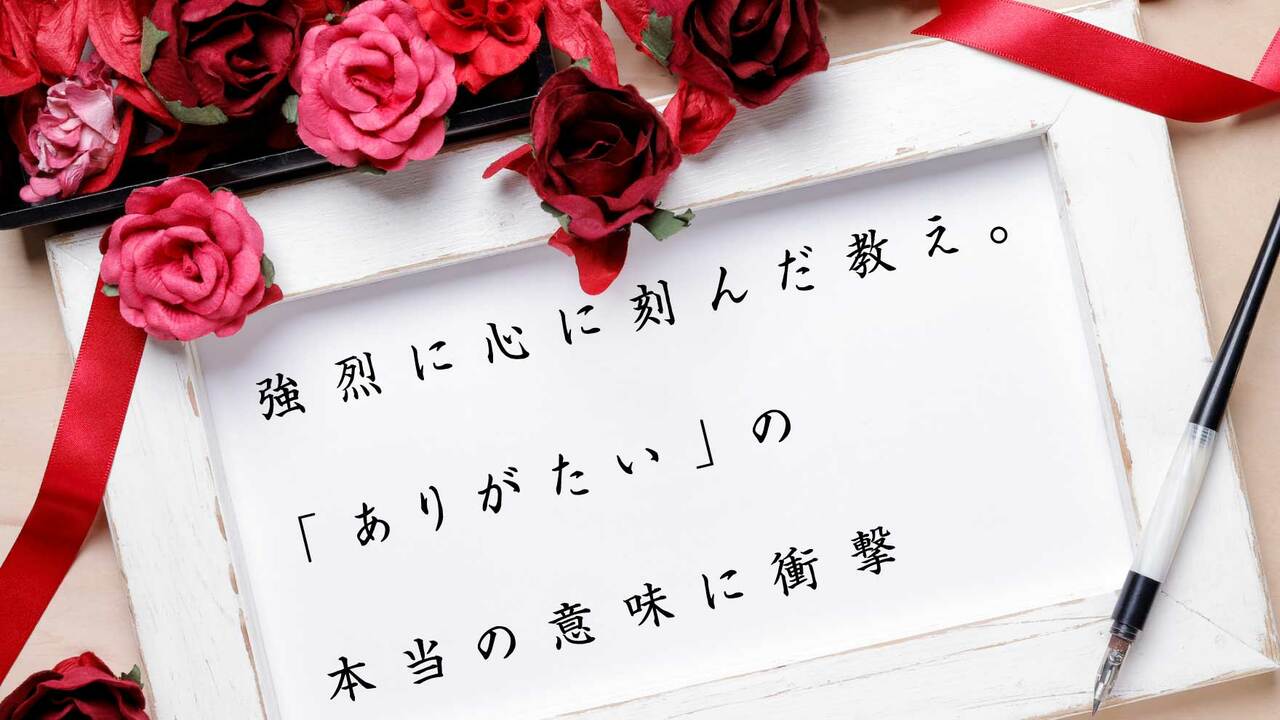元日の父
父は元日の朝、昨夜のうちに母が整えておいた上等の着物を着て、新しい水を汲んで神棚や仏壇に供える。神棚や仏壇の三方には大きな盆や皿に盛られた山海の供物が供えられる。里芋、蓮根、人参、といった縁起物の野菜や果物、羊羹のようなお菓子が盛られ、尾頭付きの大きな鯛が別皿で真ん中に供えられる。神棚のお神酒や塩、お米、お供え餅、お雑煮など、様々な供え物を父が丁寧にお供えして準備が整う。由緒正しい室礼の作法には則っていないのかもしれないが、それが精いっぱい、両親の感謝の気持ちだったのだろう。
家庭の祭壇にしては少々大げさなくらいの供え物なのだが、母は「家族そろって健康で、無事な生活をお与え下さっている神仏に一年分の感謝を捧げるのにはこのくらいの供え物ではとてもとても足りないくらい。感謝の気持ちいっぱいにお供えをし、そして新しい一年の無事をお祈りするのよ」といつも教えられた。
でも、何事もやや大げさで、やや派手好きだった父に比べて、きわめて合理的な母は父亡き後は大きな尾頭付きの鯛は止めた。「鰯だとて尾頭付きに変わりはない」という論理からだが、私はこの頃はさらに進化して、現在の暖房設備の整った家では七草までもたないので「尾頭付き」の干物にしてしまっているから、父はさぞ残念なことだろう。
そして新しい年の祈りが始まる。神棚と仏壇の前に父が座り、母、私たち子供がその後ろに座ると、その日父が決めたお祈りが始まる。私たちにも本が渡されて父のあとについて、たいがいはなにかのお経を読むのだった。
お祈りのあと両親に向かい「新年おめでとうございます」と挨拶して父からお年玉をもらう。そうして、やっと元旦の食卓に着く。
これが元旦の絶対の決まり事だった。だから子供たちも元旦に家にいないというようなことは許されなかった。冬休みにスキーに出かけても、友人たちは年をまたいでスキー場に滞在しても、私だけは絶対に年末には家に帰らなければならなかった。そのルールは私のなかでは今もって厳然と生きている。お正月に海外旅行などとても行けないのだ。
父は元旦のこの行事で、一年分の家長としての役割を果たしたつもりになったのだろうと思う。残りの三百六十四日の大半の日々は、妻や子供、つまりは家庭とうものに対してはまったくどうしようもない”不良おやじ”だった。
私は何故か、そんな元旦の父の姿が好きだった。
父が亡くなってもう何十年にもなるのに、いまも父を想うとき、まず浮かんでくる父の姿は夏休みに旅行や映画に連れて行ってくれる父や、銀座や新橋の上等な料理店へ連れて行ってくれる父でなく、粛々と元旦の行事をしている父の姿なのである。