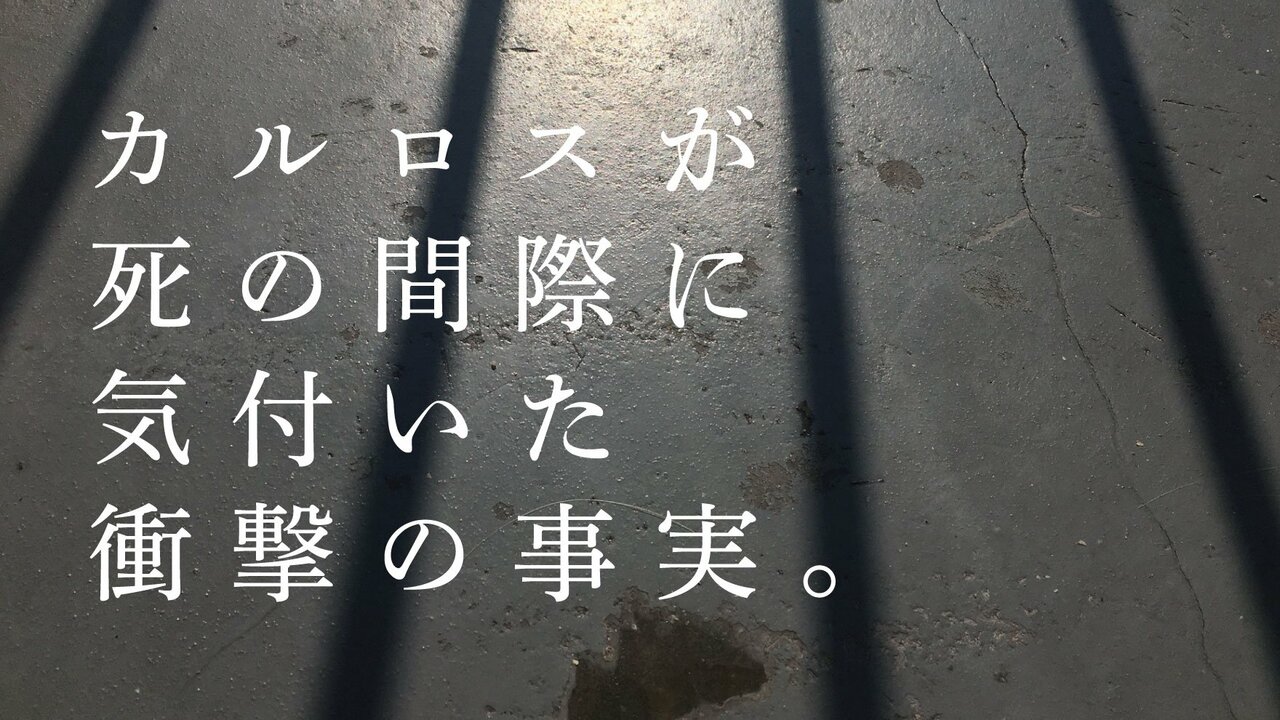第三章 ガルシア牧場
第二話 新しい命
コンスエラはガルシア牧場の生活に戻った。年が変わり、フィオリーナは四回目の出産で、六ぴきの子犬を産んだ。四ひきはオス、二ひきがメスだった。子犬たちはよく動く黒いボタンのような目をしていた。体はつやつやとした黒と茶色の毛でおおわれ、目の上に茶色の丸い模様があるので、目をつぶっていても、目が開いているように見えた。
フィオリーナはもう老犬で、今回の出産は難しいと思われていたので、コンスエラは六ぴきの子犬が無事に産まれたことが、うれしくてたまらなかった。仕事の合間(あいま)に、しょっちゅう子犬を見にやってくる。フィオリーナも満足そうな顔で子犬たちに乳を飲ませている。子犬たちはどれも元気だったが、最後に産まれたメスの子犬は、きょうだいよりもひとまわり小さく、育つのは無理ではないかと思われた。
翌朝、子犬の様子を見にきたコンスエラは、悲鳴をあげて持っていたミルクの皿を落とした。六ぴきの子犬が乳を吸っているフィオリーナの体は、まだぬくもりが残ってはいたが、息をしていなかったのだ。コンスエラは、大声で泣きながら、フィオリーナの体を抱き起こした。
「こんなことになることが分かっていたら、子犬を産ませるのではなかったのに。フィオリーナ。かわいそうなことをしてしまった。許しておくれ」
そう言っていつまでも、冷たくなっていくフィオリーナの体を抱きしめていた。コンスエラが母犬の代わりとなって子犬にミルクを飲ませ、毎日懸命に世話をしたが、子犬は次々に死んでしまった。最後に残ったのは、意外にも、育たないと思われた一番小さな子犬だった。コンスエラはこの子犬だけは何としても助けたいと、つきっきりで世話をした。
「神様、神様は私からカルロスを遠ざけておしまいになりました。どうかこの子だけは私からうばわないでください」
心からの祈りが通じたのか、やがて子犬はミルク以外のものも食べられるようになり、少しずつ大きくなった。そんなある日、コンスエラは机の引き出しから銀のメダルを取り出し、そっと子犬の首にかけた。それは、むすこのカルロスがフィオリーナのために心をこめて彫った「F」の花文字のメダルだった。フィオリーナが死んだときに、形見としてしまっておいたものだ。
「お前はお母さんそっくりだから、名前はお母さんと同じフィオリーナにしようね。ねえ、フィオリーナ。お前も私もひとりぼっち。いつまでも、私と一緒にいてね」
メダルはいやでも、少年のころのカルロスを思い出させる。カルロスのことは半ばあきらめてはいたが、やはり、むすこのことを思わない日は、一日もなかった。コンスエラはこれ以上カルロスのことを考えまいと、フィオリーナに急いでキスをして立ち上がった。