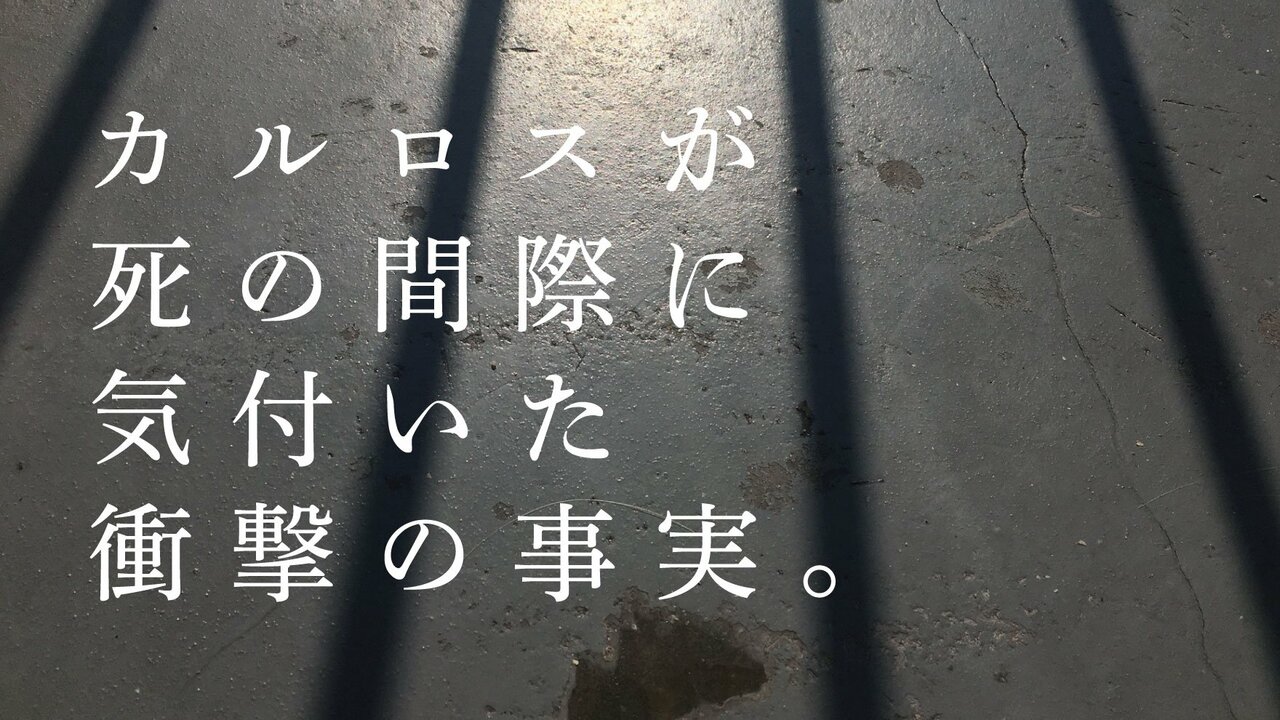第二章 コーヒー農園
第一話 ミランダ一家
ロレンソが主人であるミランダ農園は、祖父の代から、この土地でコーヒーを作ってきた。コーヒーの木はつやつやした濃い緑の葉の中に、赤く丸い実がなる。暖かく雨の多いここの気候がコーヒーに向いていたため、たくさんの実がとれた。
この気候が向いていたとは言っても、初めからコーヒー栽培がうまくいったわけではなかった。赤道に近いこの地域の日光はコーヒーの木には強すぎて、初めはなかなかよい実がならなかった。
祖父はいろいろ試した末に、農園のところどころに、葉が大きく繁る木を植えた。すると五、六年後にその木がちょうどよい日陰を作るようになり、つやつやしたコーヒーの実がたくさん実るようになったのだった。
コーヒーの実は、一つ一つ人が手で収穫する。それを集めて、手回しの機械で赤い皮と白い果肉を取り除き、ぬるぬるした種を何日か水につけてから洗う。それを太陽の下で乾かしてうすい皮をとると、コーヒー豆になる。
フランシスコも学校から帰ると毎日、農園を手伝った。フランシスコのそばには、いつもクレアがいた。カルロスにあげたロットワイラーの子犬のきょうだい犬である。七ひき産まれた中で残ったのはクレアだけだった。ロットワイラーは、村人が番犬としてほしがるので、ロレンソが気前よくあげてしまったからだ。クレアの母犬は二年前に死んでしまった。
フランシスコは手伝いが終わると、農園から少し離れた、見晴らしのよい所に登る。コーヒー農園は山の中腹にあるので、少し登るとふもとの村が見下ろせる草地があった。そこに座って箱庭のような村やコーヒーの林をながめたり、山の上を流れていく雲を見上げたりするのが大好きだった。
クレアは呼ばれなくてもフランシスコについてくる。フランシスコが家に帰るまで、そばにいるのが役目だと思っているのだ。そこで、母が持たせてくれたおやつを食べた。おやつはジャムをはさんだサンドイッチだったり、パウンドケーキだったり、ソーセージだったりした。
クレアと半分ずつ食べるはずだったが、食いしん坊のクレアの方がいつもたくさん食べた。
「クレア。ゆっくり食べるんだよ。ゆっくり」
フランシスコは何度も注意したが、クレアの食べ方は少しも変わらなかった。ここから見える山の形は、ちょうど山を二つに割った切り口のような半円形をしていた。日が沈みそうになると、フランシスコとクレアは家に帰った。
家ではマリアが夕食のしたくをしていて、父はまだ農園で仕事をしていた。もう少しすると、夕食ができたことを知らせるために、フランシスコとクレアが農園へ行くことになっていた。そんな毎日が、ずっと続くものだと皆が思っていた。