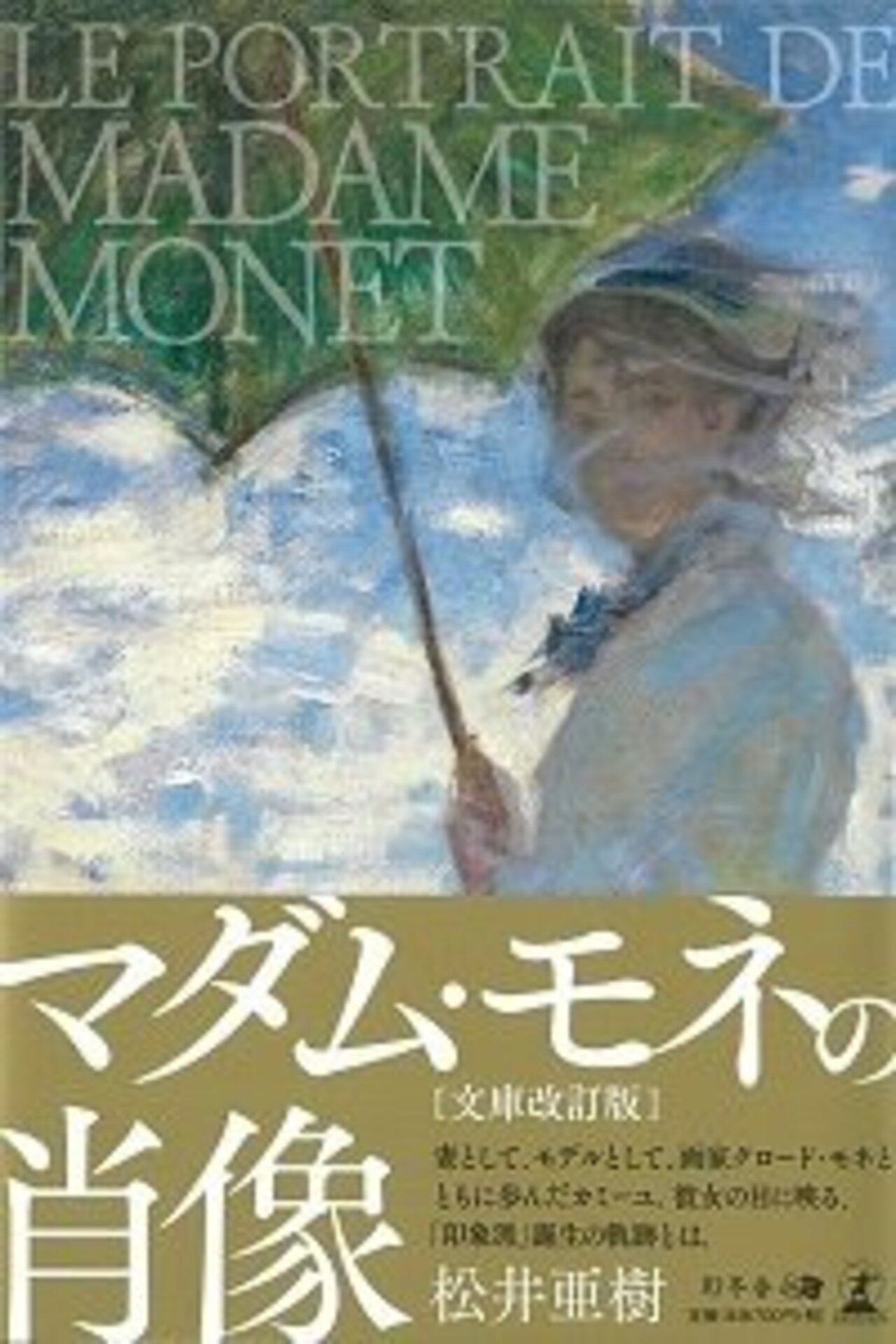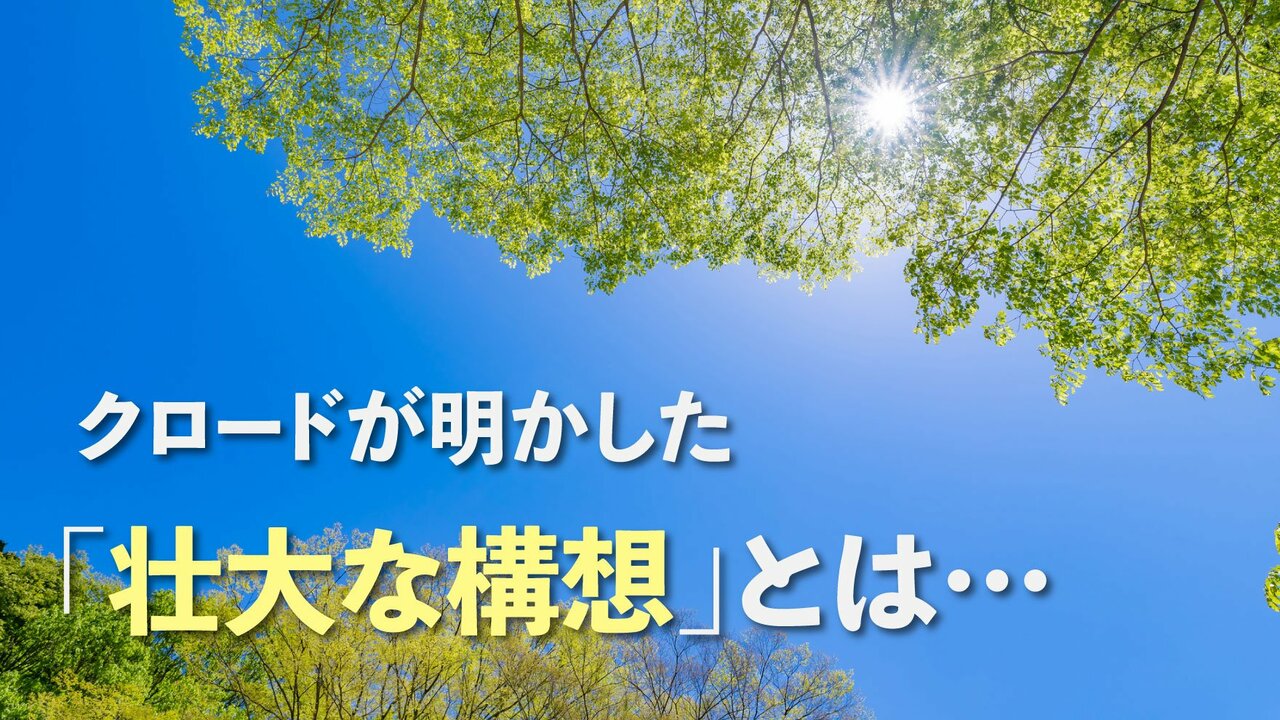画壇デビュー
日曜の朝早く、カミーユは昼食を用意していた。パンを切り、コールドチキンとレタス、玉ねぎ、パプリカなどを刻んで容器に詰めた。そうだ、塩と胡椒(こしょう)も持って行こう。今日は、アトリエでデッサンが終わったらチュイルリー公園へ行こうとクロードが言っていた。
このごろは、日曜の午後もたいてい一緒に過ごす。アトリエで三時間モデルを務めたあと、クロードと並んで公園まで歩く。街中のマロニエから一斉に新緑が萌え出している。カミーユの大好きな季節だ。生まれたばかりの緑は、なんてみずみずしく鮮やかなこと。しかも今、カミーユはクロードの隣を歩いている。こんなにも心躍る瞬間は、これまでなかったと思う。
木陰で一緒に昼食を摂りながら、二人は他愛もないおしゃべりをし、何でもないことに笑った。クロードがスケッチを始めると、カミーユは満たされた気持ちでその姿を見詰めていた。クロードの鋭い視線に晒されているのが自分ではないことも、この場合には幸せだった。
夕方になってクロードがスケッチを切り上げると、二人はカフェでコーヒーを飲んだ。新緑の中を渡ってくるそよ風が心地よかった。クロードが急に、ポケットから包みを取り出した。
「君に」
差し出された包みをカミーユが受け取ると、「似合うと思うんだ」クロードは言った。
「開けても?」
クロードはどうぞというジェスチャーをした。美しい紙袋から出てきたのはチョーカーだった。黒いレースで繊細に編み込まれ、中央には黒い石が嵌はまっていた。
「オニキス、なんだ」
クロードはいつも口下手な方だが、今日はとりわけたどたどしい。
「サロンが始まったら一緒に観に行ってくれるかい? できればその首飾りを付けて」
カミーユはチョーカーを両手で包み込むと、胸に抱き締めた。
「……うれしい」
いつも強気なクロードが、珍しく目を伏せてまだ何か言いたげにしていた。カミーユは、子どもの告白でも待つように優しい気持ちになった。
「君がアトリエに来てくれて、僕はサロンに初入選した」
クロードは、手元のコーヒーカップを見詰めたままそんなことを言った。
「君は僕のミューズだ」
クロードはやはり目を上げなかった。芸術こそ己の進む道と定めたクロードが“ミューズ”と言うとき、それは最高の賛辞だと思った。カミーユは、人目も憚はばからずクロードの首に両腕を回すとその唇にキスをした。そんな大胆なことができるなんて、今の今まで自分でも知らなかった。周囲にどれほど人がいようと、今のカミーユにとって、クロードと自分の二人だけが世界のすべてだった。