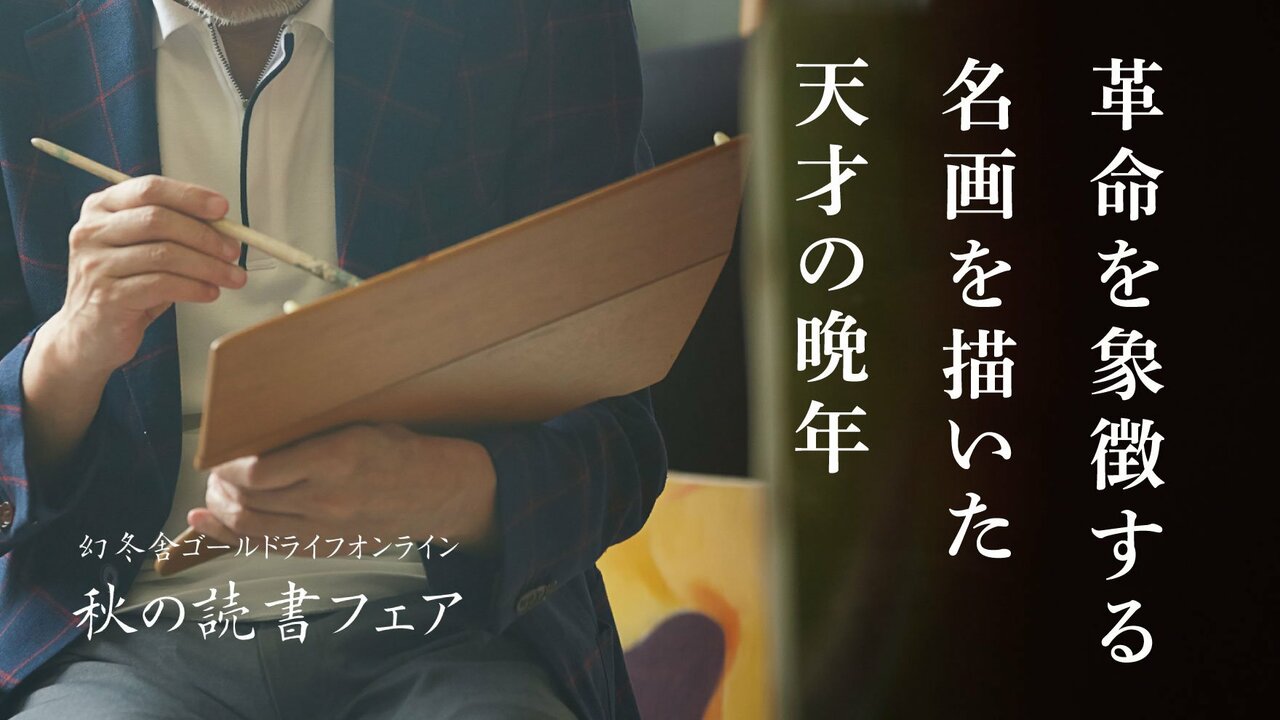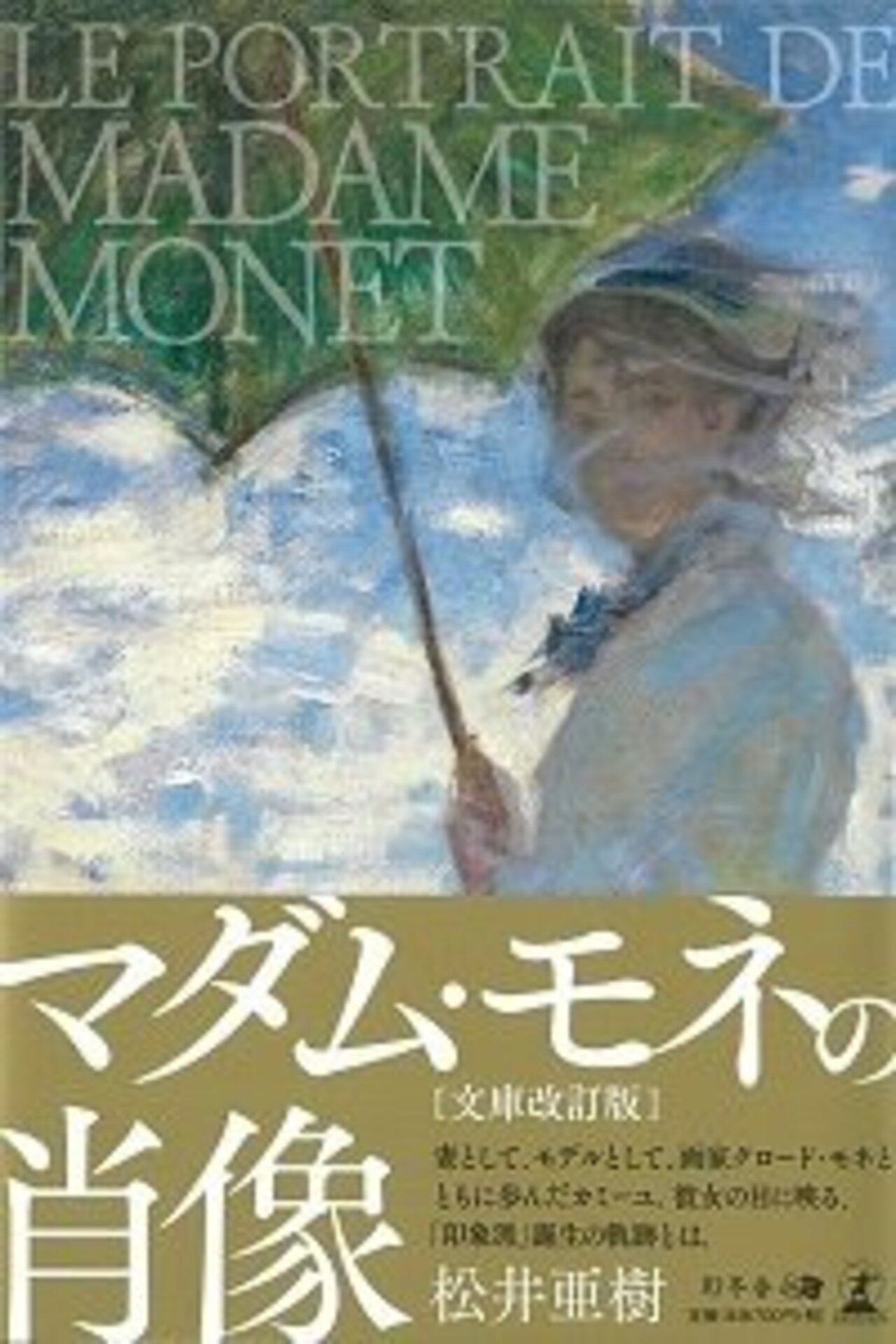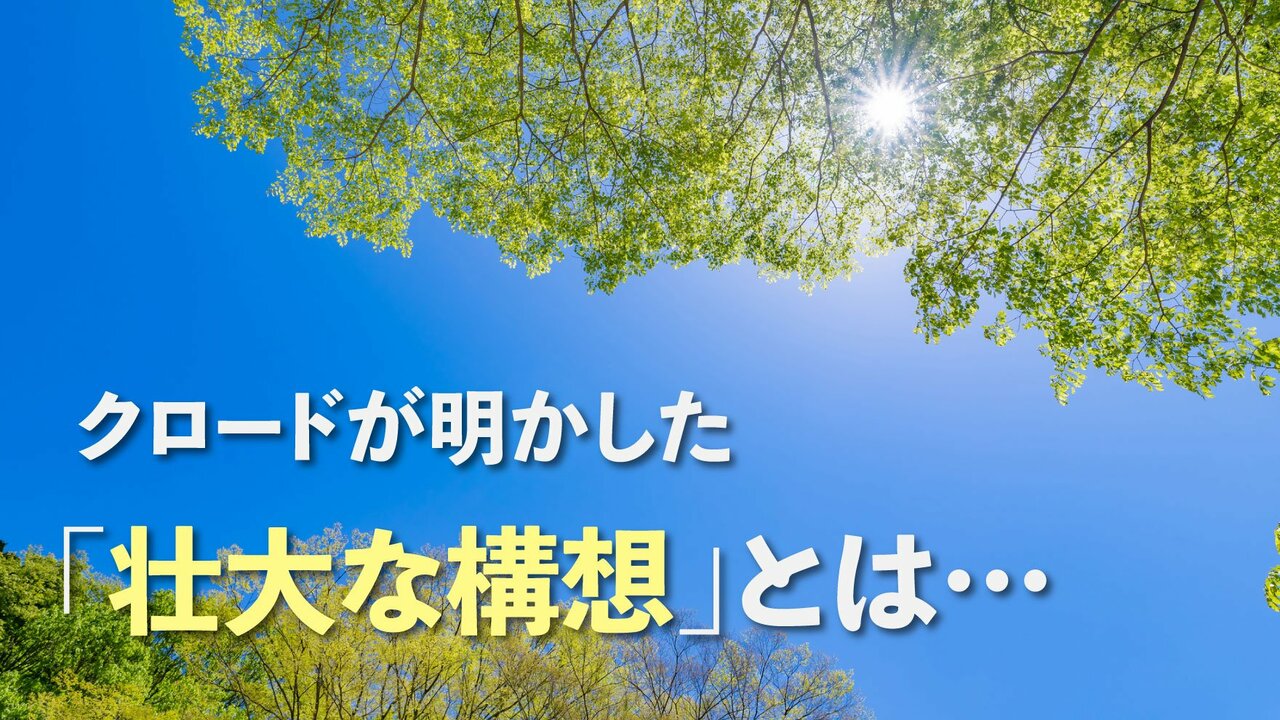ウジェーヌ・ドラクロワ
その日も三時間たっぷりモデルを務めた。
アトリエを出て、こわばった手足を伸ばすように歩き始めると、後ろからモネが小走りに追いかけてきた。これからチュイルリー公園までスケッチに行くという。
「天気がいいから、ちょっとセーヌ河畔を歩いてみよう」
初めて並んで歩く。急なことにどぎまぎして足がもつれそうだ。何か気の利いたことを話さなくちゃと焦るのに、言葉が見つからない。
セーヌを渡ったらチュイルリー公園とは反対方向に帰るのだが、それは敢えて口にしなかった。
そのとき、モネはふと立ち止まり、出てきたばかりのアトリエを振り返った。
「この建物の二階には、ウジェーヌ・ドラクロワが住んでたんだよ」
ドラクロワ。その名はカミーユでも知っている。
『民衆を導く自由の女神』は革命を象徴する名画として、フランス人なら誰もが知っているだろう。ここからほど近いサン・シュルピス教会のフレスコ画を仕上げるために、彼は最晩年をここで過ごした。
「つい一年半ほど前、亡くなるまでね」
モネはちょうど二階の辺りを見詰めたまま動かなくなった。少し間があって、また話し始めた。
「僕は二十歳のとき、くじ運悪く徴兵されたんだけど、それまでアカデミー・シュイスという美術学校に通ってたんだ。ドラクロワはそこの大先輩。ほかにも、サロンで審査員を務めるコローや、"レアリスム宣言"は知ってるかい? あのクールベもそこで学んでたんだよ」
クールベという名はどこかで聞いたような気がするが、コローは初めて聞く名前だった。かつて巨匠と呼ばれる人が最期まで芸術に魂を燃やし続けたアトリエ。
その前に立ってこの人は、今、何を考えているのだろう。
「フレッドが、……ああ、バジールのことね、ここに一緒に住もうと誘ってくれたときは震えたな」
珍しくはにかむように笑った。それは決して、生活費が浮くという現実的な喜びのためではないだろう。このパリに、画家やその卵の住むアトリエなら数え切れないほどあるけれど、巨匠と呼ばれる人のアトリエは数えるほどしかない。
「ドラクロワは色彩の世界の豊かさを僕らに教えてくれた。彼のオリエント絵画には、フランスで描かれる絵にはない光があった。不思議なほど強烈に覚えてるんだよ。とてつもなく偉大で、そこからは熱い光が放射されているんだ。そんな光をこの目で見たくて、徴兵されたときには迷わずアフリカ騎兵隊に志願した」
徴兵されれば、確か五年間は兵役に就かなければいけないはずだった。モネはいつ帰ってきたのだろう。
「でもチフスに罹かかってね、一年も経たないうちに家に帰された。伯母が三千フランもの免除金を払ってくれたおかげで、軍隊には戻らずに済んだ」
彼は少し遠い目をした。軍隊での生活については語ろうとしなかった。
「アルジェリアの光は本当に強烈だった。パリとは全然違ったよ。光一つで風景はガラリと表情を変えてしまう」
モネはまだ、アパルトマンの方をじっと見つめていた。カミーユは、そんな彼の横顔から目が離せなかった。
「僕はこのパリにいながら、生きている間にドラクロワと会うことはできなかった。アカデミー・シュイスに戻ることもない。通っていたアトリエも閉鎖になった。だけど、めざす道は見えている。少なくとも自分ではそう思ってる」