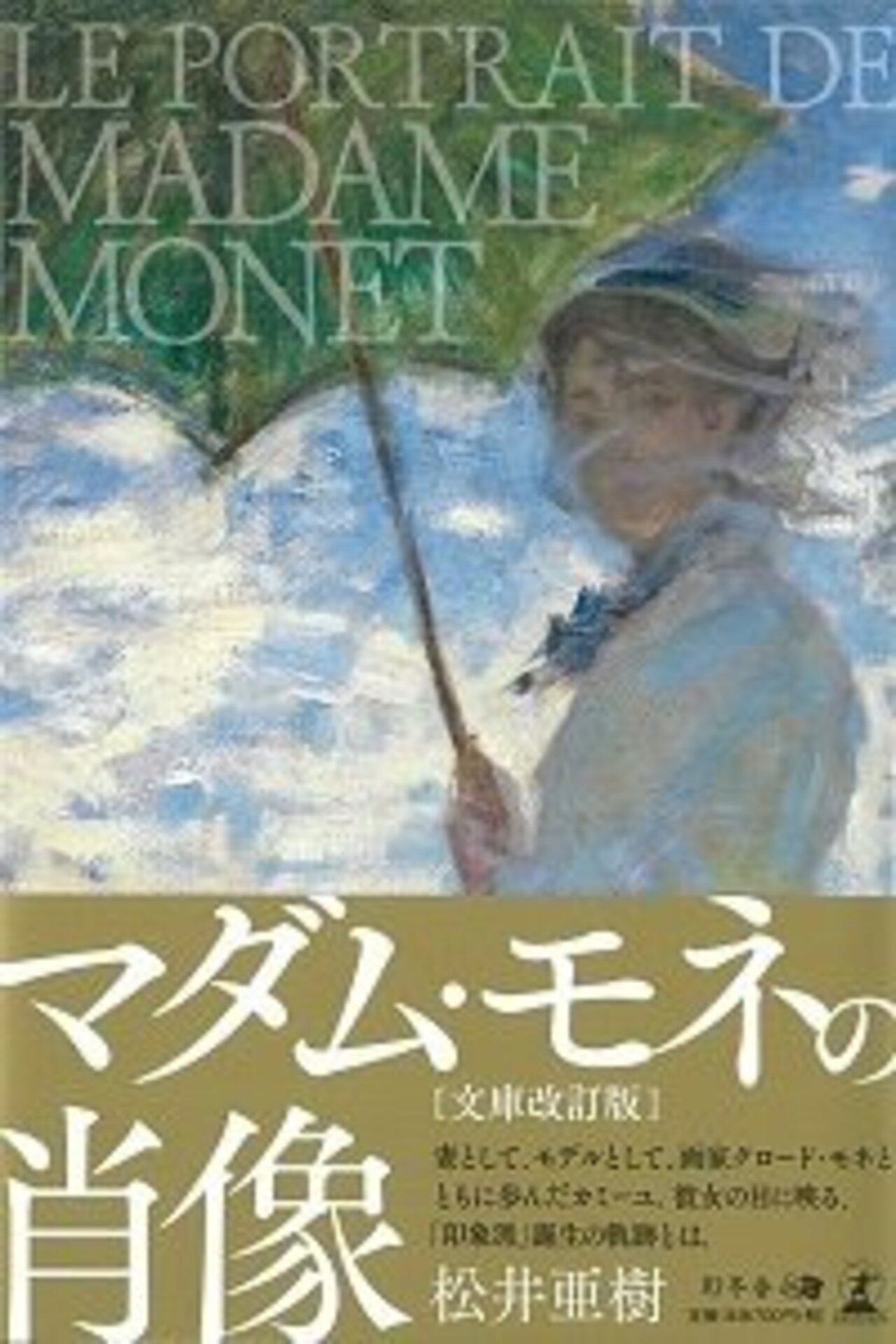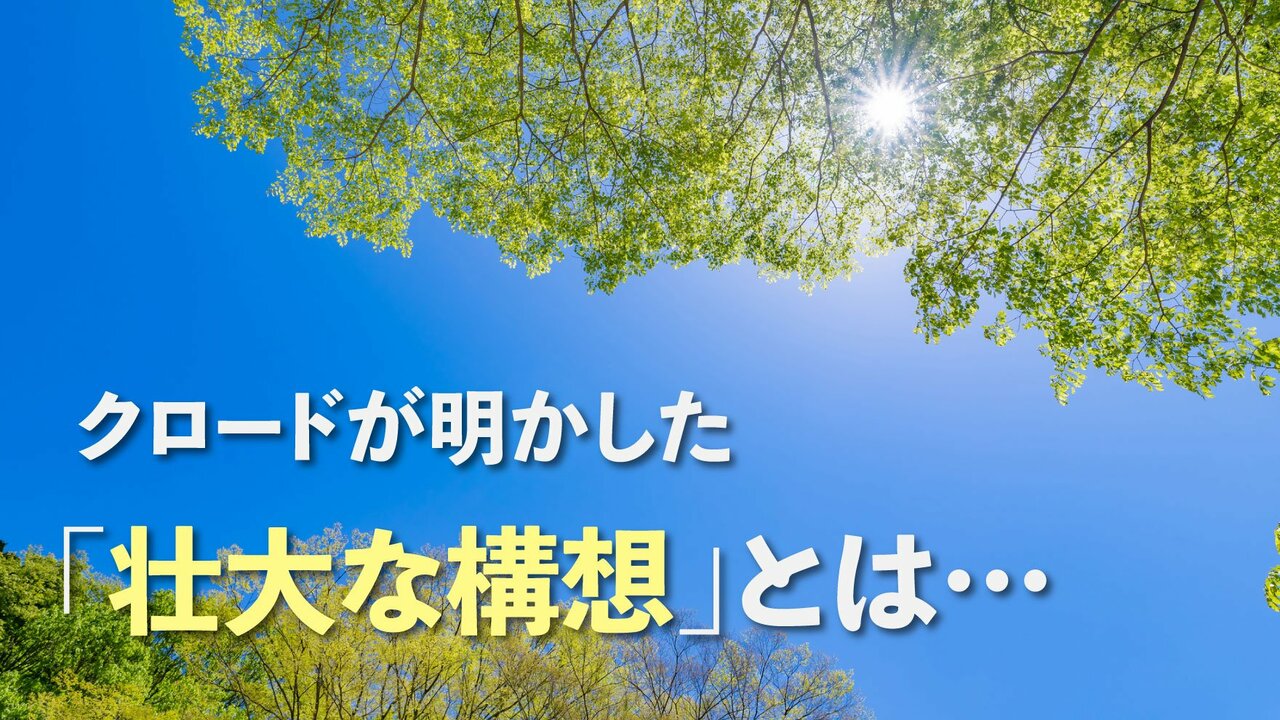出会い─パリの片隅で
カミーユがフェルスタンベール街に使いに出てから、もう一週間が経とうとしている。
ここ数日は、一日ごとに焦燥が膨れ上がった。ムッシュー・モネは「できるだけ早く」と言った。それは一週間以上掛かるのだろうか。もしかして、このままやって来ないなんてことが……。
店主の視線も日に日に厳しくなっている。
「すぐ取りに来ると言ったんだな」
何度も同じことを尋ねられ、そのたび
「はい、確かに」
と、答えるしかなかった。
カミーユはムッシュー・モネを待っている。この場合、客として当然支払いに来てくれなければ困る。
しかし、それだけでは説明し切れないほどに待ち焦がれている。自分でもそんな気持ちを持て余し、つい仕事も上うわの空になった。
カウンターに、先程まで来ていた客のために何枚か生地が拡げられていた。
「早く片付けなさい」
店主は不機嫌そうに言った。商談が不調に終わり、結局注文は取れなかったのだ。カミーユは余計な小言を言われないよう、手早く片付けようと思った。
二枚をたたみ終わり、最後の生地を持ち上げようとしたそのとき、カチャンと音がした。そばにあったインク壺を、脇に抱えた生地の端でひっくり返してしまったのだ。慌てて抱えていた生地を見ると、濃紺のインクがベッタリ掛かっている。壺は床まで落ちて割れ、一面にインクが飛び散っていた。いつのまにかすぐ後ろに店主が立っていた。
「何を突っ立ってる! すぐ片付けろ。汚した分の生地は弁償だ! カウンターも床も削って磨き直してもらわねばならん。お前にその代金が払えるのか?」
耳を塞ぎたくなるほど、恐ろしく大きな声だった。カミーユは申し訳ないのと、恐ろしいのと、請求される金額のこととで大混乱しながら、生地を安全な場所に置くと雑巾を手に取った。そのとき、店先の方から声がした。