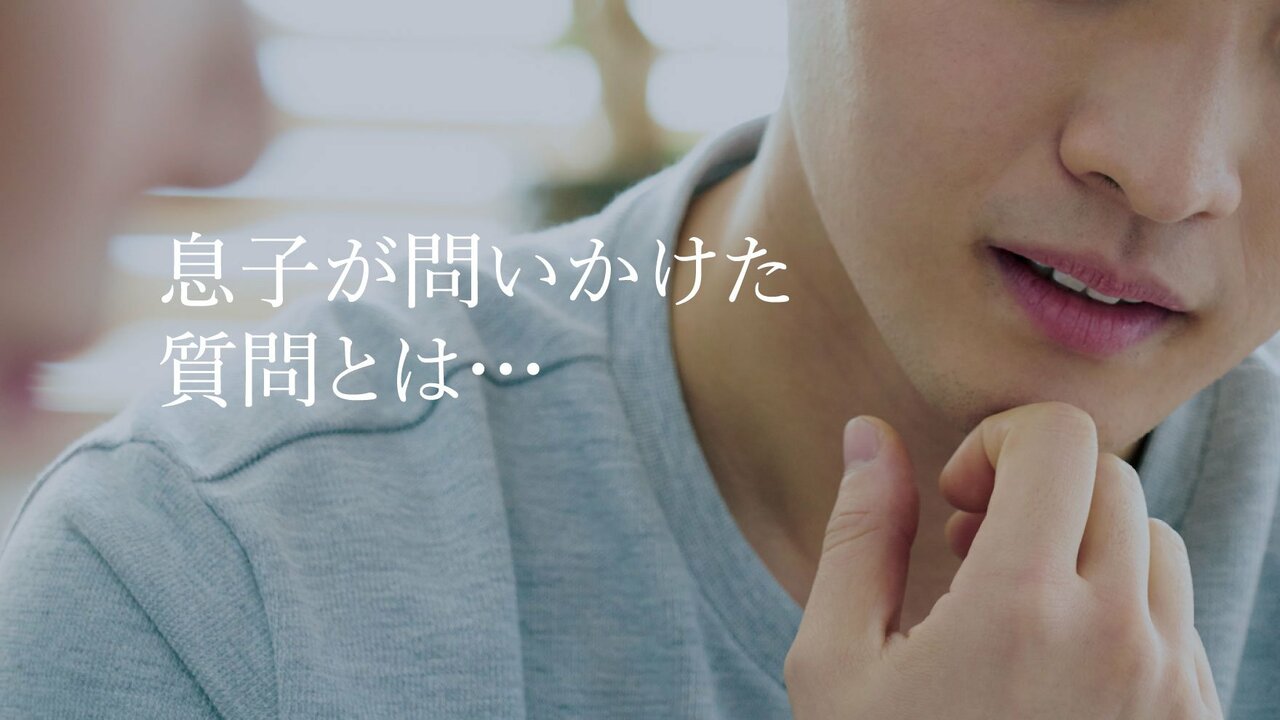自由奔放な息子からの質問
立花一家の治療計画を立てながら、つくづく考えさせられる。
ATLLは複雑な意味合いを含んだ病気だと。ウイルス感染により引き起こされる為、負の連鎖が患者個人に止まらず、家族に継承される可能性がある。これを不条理と呼ばずになんと呼ぼう。血の繋がりは絆という輝きだけでなく、まるで糾える縄のように、呪縛という側面も持ち合わせている。
だが立花一家は、そんな過酷な運命さえも受け入れて、前に進もうとしていた。不安や恐怖は簡単に消せはしない。けれども精一杯生き抜くことを彼女たちは選んだ。そうとなれば、わたしのこれまでの医師人生を賭して、治療に取り組むのみだ。
玄関からふと見上げた夜空。そこには満点の星々が輝いている。合間を縫うようにこぼれ落ちた流れ星に、わたしは願いを掛ける。願わくば、立花一家に、幸あらんことを。
「今帰ったぞ」
帰宅を知らせるいつもの挨拶にも、自然と力が漲る。わたしはこのところ不思議な充実感に包まれていた。裕子さんの移植に備えて文献を漁る日々は老体に堪えたが、良医を目指して診療に明け暮れた在りし日を思い出させた。
「おい多恵。いないのか」
妻の出迎えがないことに疑問を持ちながら居間へ戻ると、そこには珍客が待っていた。
「やあ、父さん。これはずいぶんと遅いご帰宅で」
「なんだ、智。帰っていたのか」
そこには東京の芸術大学に通っているはずの智がいて、ダイニングテーブルの中央を我が物顔で陣取り、缶ビールを呷っているではないか。
「まったく、連絡くらい寄越せばいいもの」
「きっとあなたを驚かせたかったんでしょう」
多恵は鼻歌を奏でながら台所で唐揚げを調理していた。成人式を過ぎても我が子は我が子、愛おしさは格別のようだ。
「たしかに今は再会を喜ぶべきだな。智、都会暮らしはどうだ」
わたしは背広をたたみながら倅の対面に腰かける。パーマを掛けた灰色の髪に極彩色のシャツという出で立ちは、『若さは馬鹿さ』だが、ここまで徹底していると清々しさすら感じる。
「人混みにやられて、地元が恋しくならないか」
「まったくならないね。毎日がお祭り騒ぎで退屈する暇すらないよ」
八重歯を覗かせながら語ってくれたところによると、勉強の合間に焼肉屋でバイトしながら、友人と旗揚げした劇団公演に明け暮れるという。若さとは、こんなにも溌剌として眩しいものか。
「ねえ、智。高校時代から付き合っていた彼女とはどうなったの」
達者な話運びに感心していると、多恵が大皿に唐揚げをてんこ盛りにして運んできた。
「ほら、家にも遊びに来てくれた子よ。とても感じが良い子だったじゃない」
「とっくに別れたよ」智は爪楊枝で唐揚げを貪りながらこともなげに言う。
「だれかに時間を裂かれるのがばかばかしくてさ。今は演劇が一番で、それどころじゃない」
「まあ、なんて言い草なの」
「いいんだよ。女なら履いて捨てるほどいる、って、母さん。そんな怖い表情するなよ」
豹変した多恵に気づいたのだろう、智は慌てて訂正した。こいつを見ているとわたしは不思議な心持ちになる。何者にも縛られずに自分の道を突き進もうとするこの性分は、わたしと多恵、どちらの血筋からきたものなのだろう。
「あ、ちょっと待ってね。智に食べさせようと上等なカニも用意していたの」
多恵は胸のまえでぱんと手を叩くと台所に戻った。智はその後ろ姿を見送りながら、やれやれとため息をこぼす。
「おお、怖。こりゃあ、下手な冗談も言えないな」
「智、おまえもおまえだ。多恵の前で女関係のことは気安く口にするんじゃない」
あれこれ口出しをしたくなる多恵の親心は分からないでもないが、こいつにはこいつの人生がある、好きなようにやらせればいい。それに父親としての読みでは、こいつには言い聞かせれば言い聞かせるほど逆に動こうとする天邪鬼さがあるから、黙っているほうがこちらの望む方向に進んでくれる。