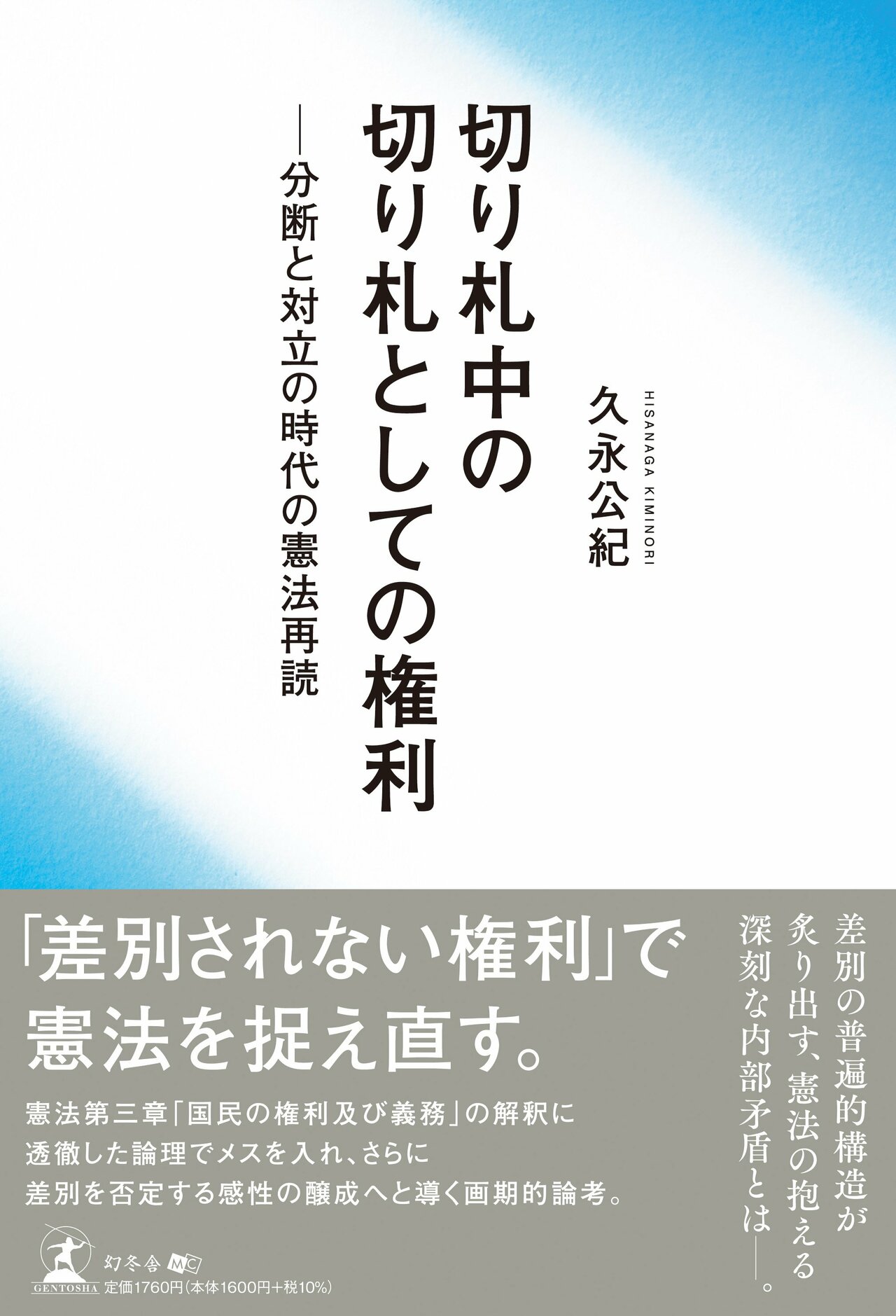裁判では、再犯の可能性についての明確な記述は無い。検事の論告での、本質的な掟(ルール)を無視し不感無覚で非人間的で恐怖を呼び起こす、という発言が、再犯可能性を示唆している程度。もちろん医者による診断も無い。社会に対して何のなすところもない危ない人間は、隔離・治療ではなく抹殺すべしという判決。
ムルソーが裁判について感じるのは、犯罪よりもムルソー自身(の魂)について語られたこと、自分の参加なしに自分をゼロと化しすべてが運んで行ったこと、よく考えて見ると、言うべきことは何もなかったということ。ここでは、課題1の整理に本質的な、犯人(ムルソー)の言葉は、無視され、検事はムルソーの内面を推測し故意による犯行だと断定している。療ではなく抹殺すべしという判決。
つまり、課題1と2の観点がほぼ存在しない裁判となっている。
ムルソーは、裁判の後、次のように思う。
判決が十七時ではなく二十時に言い渡された事実、判決が全く別のものであったかもしれない事実、判決が下着をとりかえる人間によって書かれたという事実、それがフランス人民の名においてというようなあいまいな観念にもとづいているという事実、こうしたすべては、このような決定から、多くの真面目さを、取り去る。
ムルソーは、責任・罰という概念や宿命についてどう捉えているか。死刑に関する新聞の記事は、しばしば、社会に対する責務ということを語り、それは償わねばならないとするが、想像力に語りかけない、と独房で思う。
訪れた司祭の言葉に、ムルソーの内部で何かが裂けどなり出し、「罪というものは何だか私にはわからない。他人の死、母の愛、そんなものが何だろう。いわゆる神、ひとびとの選びとる生活、ひとびとの選ぶ宿命─そんなものに何の意味があろう。ただひとつの宿命がこの私自身をそして他の無数のひとびとを選ぶのだ。」(筆者一部改変)と心の底をぶちまける。
ここには、ムルソーが、自分の意思決定・アクション選択は意識的にコントロールできないことを基点にした世界観を持つことが示唆されている。ただ、意識の仕組みを理解した反省レベルの考えを持っているかどうかはわからない。
自分の意思決定・アクション選択は意識的にコントロールできないという世界観を持っているからといって、危険な人というわけではもちろんない。しかし、ムルソーの場合、何をしでかすかわからない怖さがある。ムルソーの世界観形成過程については、殆ど語られていないが、一つだけヒントになる記述があるので最後に引用しておく。
職場の上司(主人)からパリでの勤務を打診された際に以下のように意識する。
「私だって、好んで主人を不機嫌にしたいわけではないが、しかし、生活を変えるべき理由が私には見つからなかった。よく考えて見ると、私は不幸ではなかった。学生だった頃は、そうした野心も大いに抱いたものだが、学業を放棄せねばならなくなったとき、そうしたものは、いっさい、実際無意味だということを、じきに悟ったのだ。」