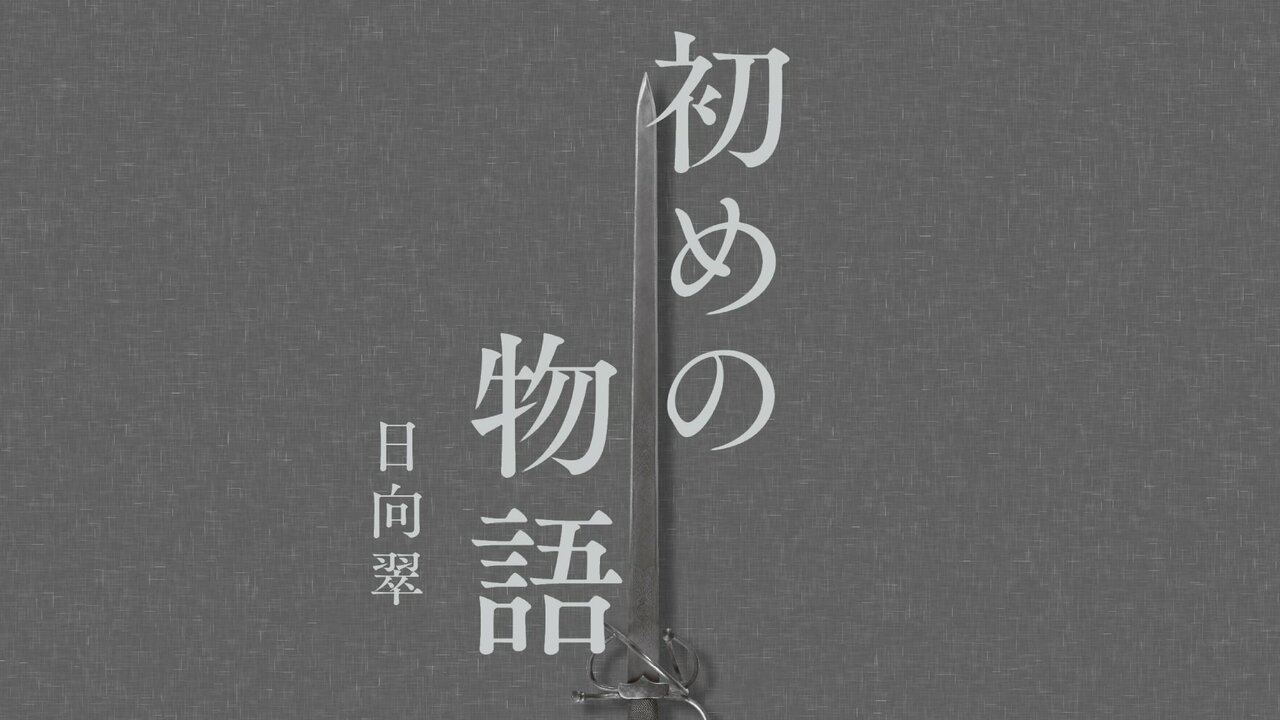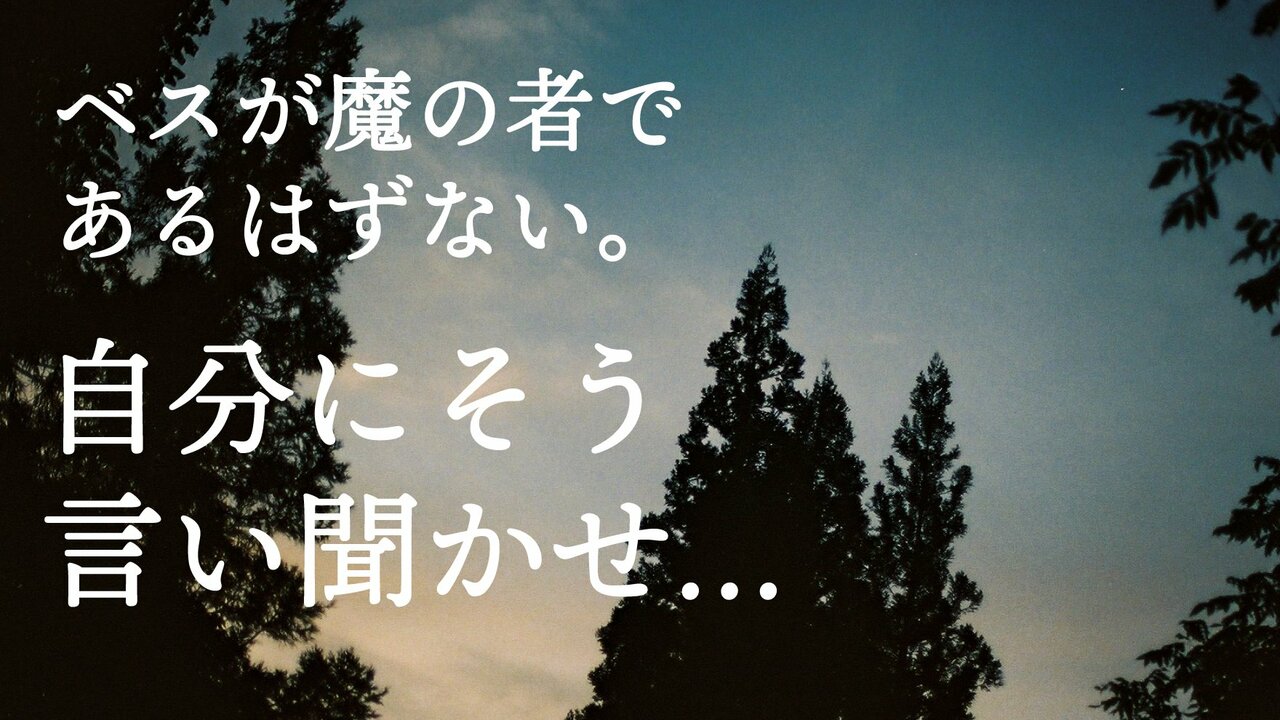脈拍
「ラウル!」
ベスはラウルが目を覚ましたのに気が付き、手を振った。屈託のない笑顔だ。彼らはラウルが麻袋に持っていたパンのかけらを少しずつ分けて飢えをしのぐことにした。二人はビクタスにまたがり、ラウルが前で手綱を取った。ベスはしっかりラウルの背につかまっている。
「今夜も森の中で過ごすことになるのかしら?」
ベスはのんびりした様子で言った。ラウルは、ベスが昨夜の狼の襲撃から、すっかり立ち直っているのを見て安心した。
「農家に宿を借りようと思ってる。ここは同盟国の国境なんだ。いずれマケドラーダ国のハワード卿の城にたどり着くはずだ。そうしたら君の国へ伝令を送るからすぐに迎えが来るだろう。あと二晩の辛抱だよ。」
もし休みなく一晩中馬を飛ばせば、今日中にハワード卿の城へ辿り着くことは、彼にはできただろう。しかし今は王女と一緒だ。彼女に無理をさせるわけにはいかなかった。
「道はわかるの? そのハワード卿の城への道は。」
「国境の森の近くに一年中紅葉したような赤い葉が付いた木に囲まれている湖があるらしい。城はそのそばに建ってる。」
「だから、最初から森の際を、行くことにしたのね。」
ベスが感心したように言った。
「私、港からずっとあなたを追ってきたって言ったでしょ。そのときは、どうして森の方へ行くのか不思議だった。」
ラウルは少し顔をベスの方に向けた。
「どうして僕の後を追ってきたの?」
ベスは真面目な顔でラウルを見つめた。
「賢くて冷静な人だと思ったからよ。」
「えっ?」
思いがけない返事にラウルは顔がかっと熱くなった。
「……どうしてそんなことわかるんだ? ……だって君は僕のこと知らないじゃないか?」
「よく観察していればわかるわ。」
ベスはこともなげに言った。
「いい加減なこと言うなよ。」
「いい加減じゃないわ。私だって供の者とはぐれて、助けが必要で必死だったんですもの。〈混乱して理性がきかないときは賢者を頼れ〉。姉のトレイシアに学んだことよ。」
彼女の口調から、ベスが姉を尊敬して、得意げに話している様子が感じられた。
「君の国の第一王女?」
「そうよ。私たち二人姉妹なの。やっぱり私の国ってあまり知られていないのね。」
「僕が勉強不足なだけだよ。」
ベスはにっこり笑って、ラウルの後姿を見た。
「あなたはとても良い騎士になると思うわ。いつか私の国へ遊びに来てくれる?」
ラウルは後ろからベスの視線を感じ、顔が赤くなった。
「いつかね。国王の許可が出たら。さあ、先を急がなきゃ。しっかりつかまって。少し飛ばすから。」
ベスの返事を待たず、ラウルはビクタスの鐙を蹴った。ベスが魔の者であるはずがない。ラウルは心の中で言った。太陽が頭上に昇った頃、彼らは川沿いで休息をとった。森の中は薄暗いが、それでも穏やかで平和な時間が訪れていた。
「ラウル、この木の実は食べられるわ。」
べスは、赤い実を差し出した。
「ああ、本当だ。僕も知ってる。」