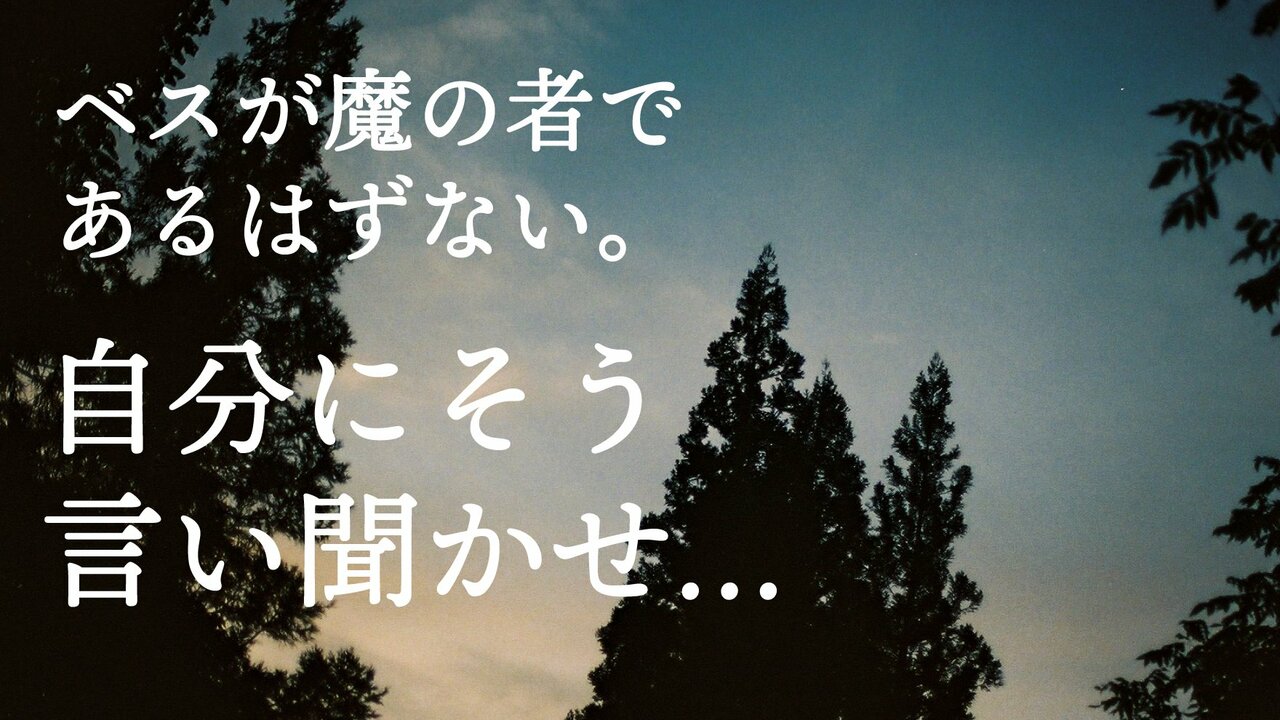しかし、震えているベスにそれを問いただすことはできないと思った。ベスが青白い手を伸ばし、さっきのようにラウルの手を取った。そして静かにラウルの手首に自分の指先を置いた。ラウルはベスを落ち着かせようと、その手の上に自分の手を重ねた。
「もう大丈夫だ。奴らはもう来ない。」
ベスは何も言わず、たき火の炎を見つめていた。そして静かに手を引いた。ラウルは心配そうにべスを覗き込んだ。いつの間にか彼女は落ち着いて笑顔を向けた。
「ありがとう。あなたはいつも冷静なのね。」
空が白み始めた。こうして一夜目が明けた。
脈拍
ラウルは剣に付いた狼の鮮血をユリカドの大きな葉でぬぐい、丹念に磨いてから鞘に収めた。
それから剣の鞘にもたれかかって座ったまま目を閉じた。騎士はこのように休息をとるのか。ベスは興味深そうに、ラウルの所作を眺めていた。
自分は前の晩ぐっすり眠ったので、今はほんのひとときでも、ラウルに休んで欲しかった。
小鳥のさえずりが聞こえ始め、森は次第に白みをおびて明るくなってきていた。馬のビクタスも静かに眠りについていた。たき火からは灰色の細い煙が一筋上っていく。太陽の光に照らされた森はまるで様相が異なり、夜に起きたことがすべて幻のように感じられた。
木漏れ日が、森の奥まで差し込むほど明るくなった頃、ラウルはゆっくりと瞼を開いて重苦しい眠りから覚めた。ぼんやりした頭の中に、ひとつの言葉が浮かんできた。
彼女は歌っていたんだ。
昨夜の馬上のべスの姿を思い出し、ラウルははっきりと目を覚ました。見間違えじゃない。その声を聞いて、狼は去った。まるで首領の意思がみえたかのようだった。そして自分の心も覗かれたように感じた。
ラウルは顔をあげ、ベスの姿を探した。ベスは馬のそばに腰を下ろして、優しくその背中を撫でていた。ラウルはじっとベスを見つめた。
穏やかな朝の光がラウルの姿を包んでいたが、その温かさも抗いがたい、そら寒い言葉が、頭に浮かんだ。
彼女は何者なんだ。魔の者なのか?