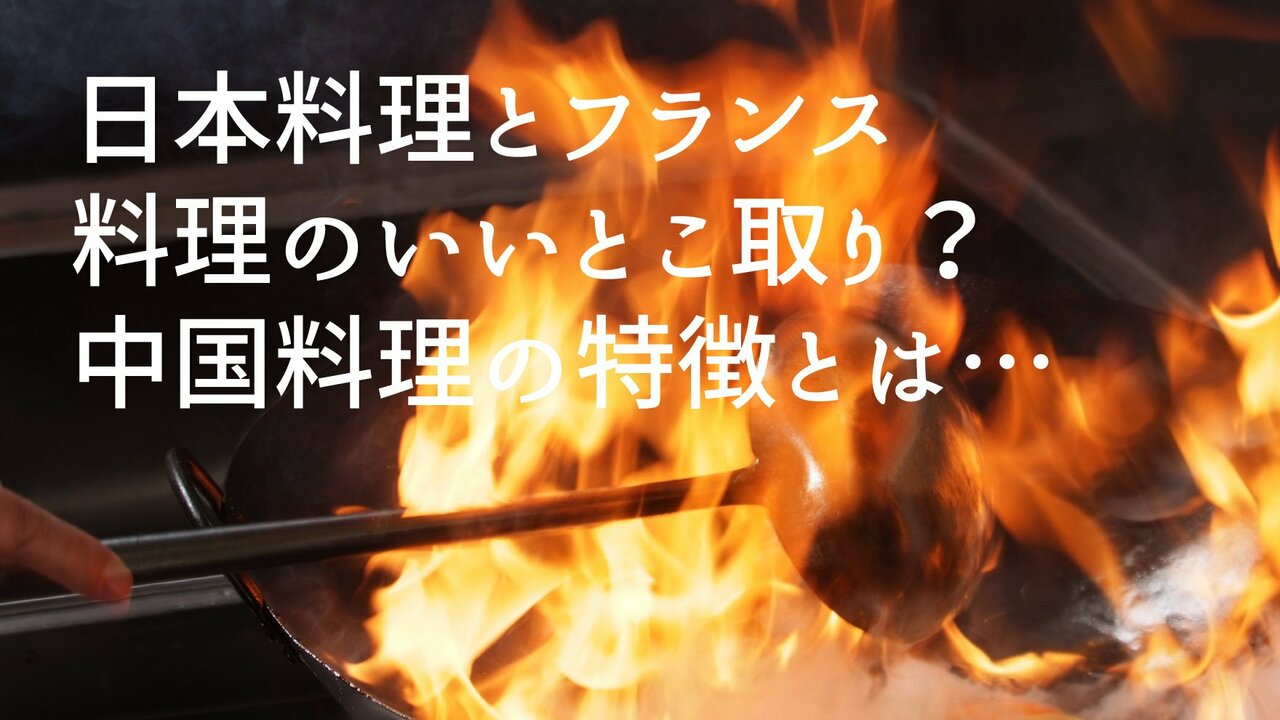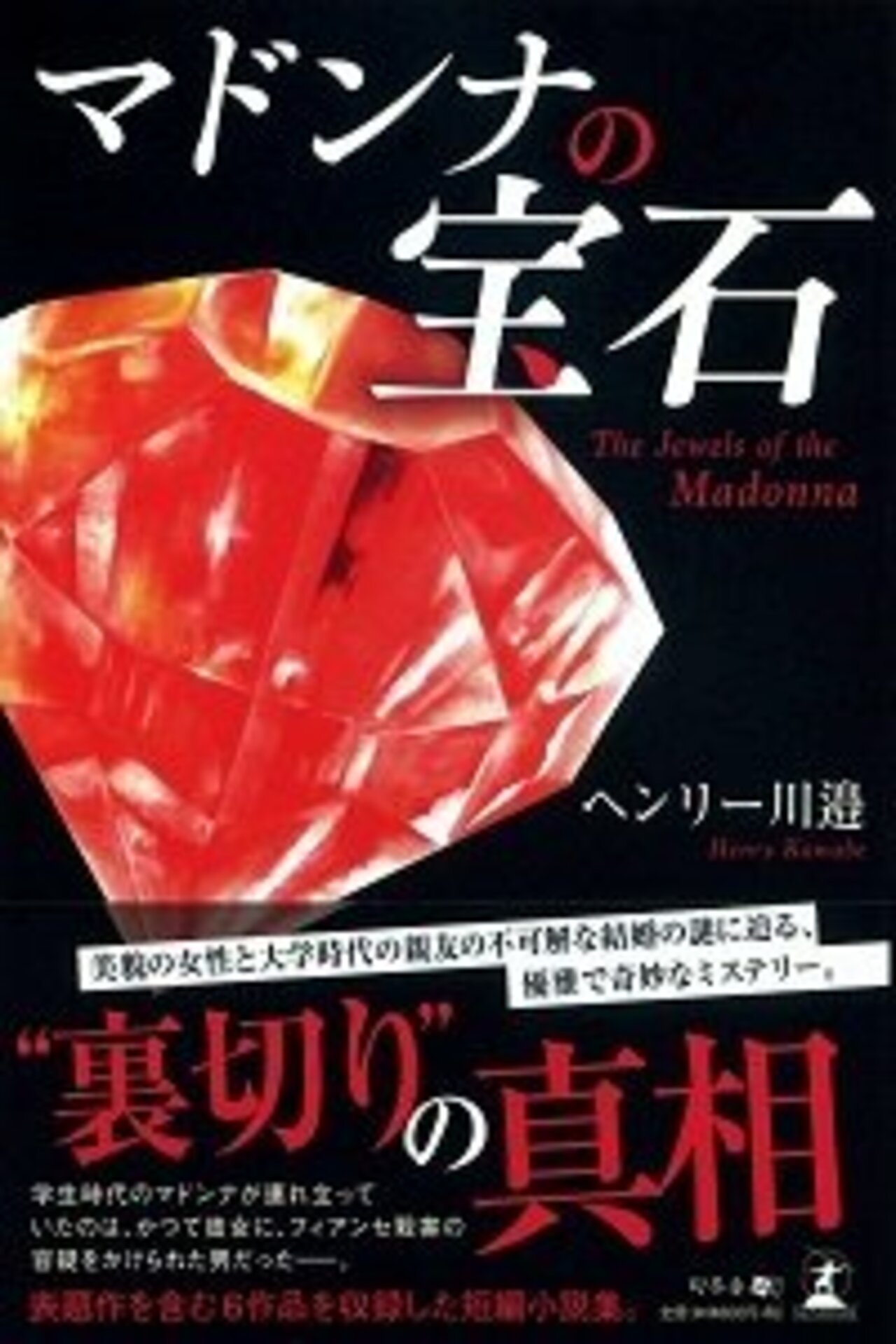奇跡の味
父はどんなに客が増えおいしい料理で評判をとりましても、自分で料理をするためにすべてを自分の目の届く範囲においておかなくては気が済まないたちでしたから、店の規模もそれほど大きくいたしませんでした。
支店を出したりする気も全くなく、ただひたすらお客様においしい料理を少しでも安く食べていただこうと、日夜工夫を重ねるのが常でございました。
そればかりか、料理を道具に使い、料理をおいしくするよりも商売の方に血道を上げている同業者を軽蔑して、調理人の風上にも置けないと憤っておりました。
また、そうなった責任は調理人にあるばかりでなく、権威に弱く味音痴が多い東京のお客様にもその責任の一端はあるのだと申しておりました。
外見や体裁や権威ではなく、純粋に料理のおいしいまずいを鋭く味わい分け、少しでも手を抜くとたちまち客足が遠のいてしまうフランスや中国のように、本当においしい料理を賞味しようと思ったら、食べる人の味覚やセンスを磨くことが大事だと、常々口にしておりました。
料理店の主人にあるまじく、お客様の態度にまで口をはさんでおりましたが、それもこれも父の料理にかける情熱のしからしめるところと、どうか大目に見てやっていただきたいと思います。
そんなわけですから、料理にかける情熱が愛好家に伝わらないはずがなく、湖南飯店は味にうるさい方や本物を志向する方の間でいつのまにか評判になり、東京一おいしい北京料理を、誰が見ても妥当なお値段で賞味いただける、知る人ぞ知る名店として、いつも繁盛しているのでございます』
朗読を終わると、内容を嚙み締めるように皆しばらく黙っていた。
「西太后の調理人の家系だったのか。すごいものだな。並みの人間じゃないとは思っていたけど、道理で料理が普通じゃないわけだよ。いや、知らなかったな」
料理評論家の成瀬が沈黙を破って感嘆した。
「これで陳さんの育ちも、店の由来も、店で出す料理も、料理に対する考え方もすべてわかったわけだ。なかなかのものじゃないか、この手記は」
遠山教授が感心した。
「しかし、事件はどうした。肝心の事件が出てこないじゃないか」
遠藤弁護士は不満気だ。
「まあ、あせるな。今は前菜のようなものだ。いずれ核心に触れてくるよ」
私がそう言ったちょうどそのとき、前菜がタイミングよく運ばれてきた。大きな皿の上に色とりどりの冷菜が、孔雀の模様を形作って鮮やかに盛り付けられている。
「拼盤でございます」
支配人が言った。
「なんだ、拼盤て」
遠藤が皿を覗きこみながら聞いた。
「前菜の一種で、冷たい前菜をいくつも組み合わせたものさ。陳さんのお得意の一つで俺が特別に注文しておいたやつだ」
成瀬が鼻をうごめかせた。
「先日中国大使がいらっしゃったときに召し上がったのと同じものを用意しました」
支配人が説明した。
「それにしても見事な盛り付けだな。食べるのが惜しいくらいだ」
遠山が感心した。
「おい、成瀬。お前少し解説しろ」
遠藤はまだ物珍しそうに料理を見ている。