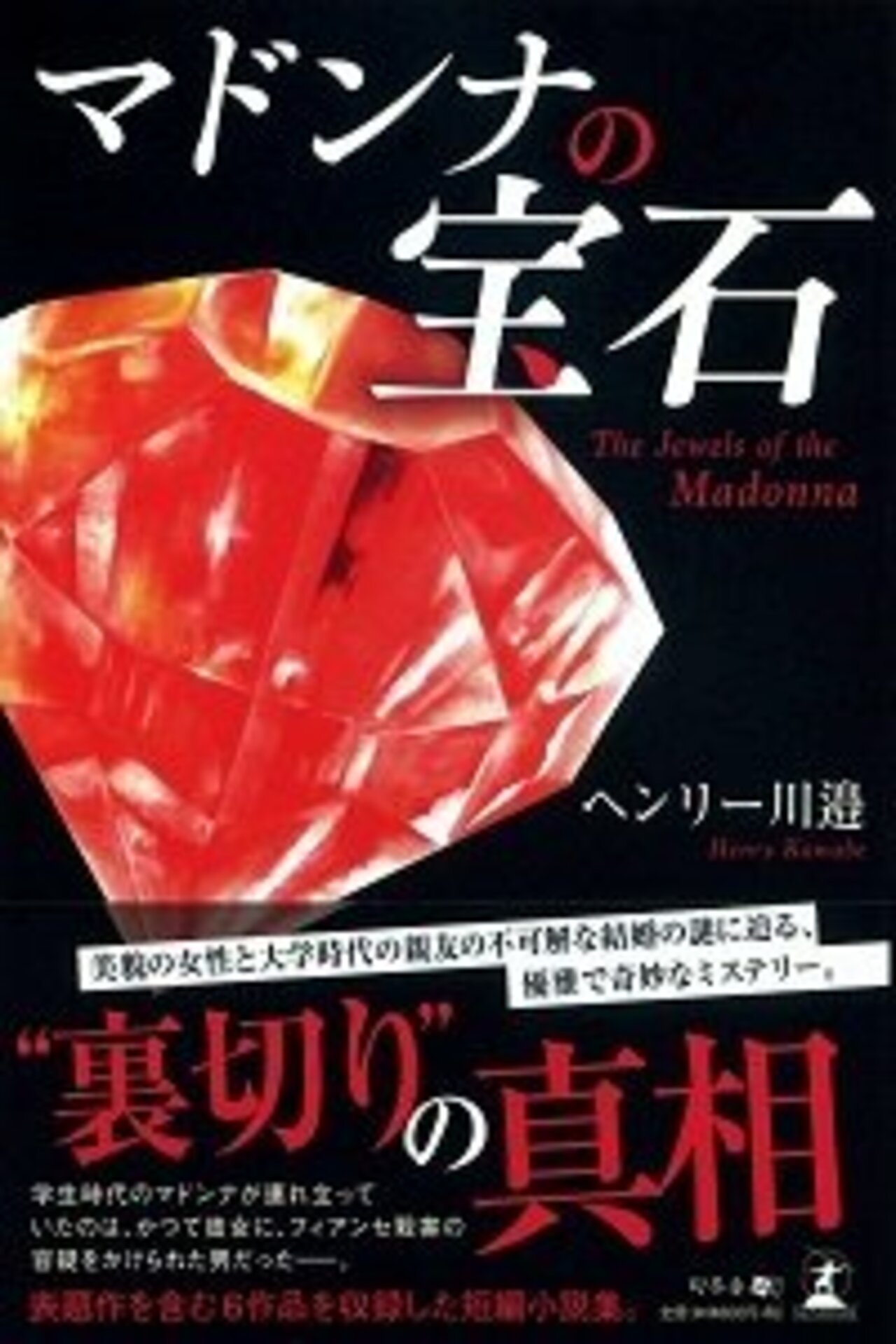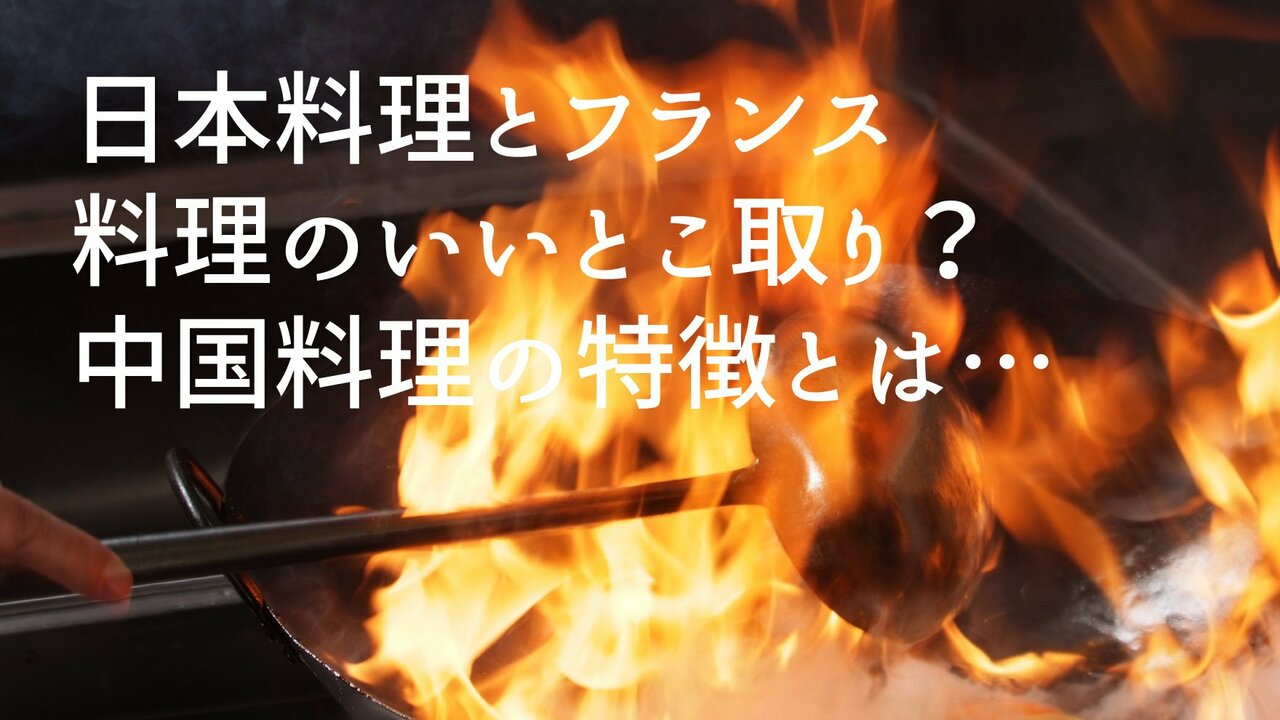奇跡の味
両親は日本に着いてから横浜の中華街の料理店でしばらく働いていましたが、やがてバラックが立ち並ぶ新宿のはずれに小さな中華料理店を開き、それが発展してこんにちの湖南飯店になったわけでございます。
言い忘れましたが、湖南飯店という名前は父が郷里の湖南省を偲んでつけたものですが、店で出す料理は湖南料理ではなく北京料理でしたから、中国人仲間からはよくけしからんと文句をつけられていました。
店の名前から湖南料理の専門店を連想させ、出す料理は北京料理ですから、看板に偽りがあり客を惑わすのがけしからぬというのです。
これについて北京からきた人が面白いことを言っていました。狗頭を掲げて羊肉を売るというのです。北京料理が最高の中国料理だと思っている人にとっては、湖南料理は狗頭になるのかもしれません。
父は北京料理店だからといって湖南飯店という名前をつけてはいけないという法はないといってとり合わず、結局いまも湖南飯店という名前になったままでございます。
父は清朝の生き残りのような祖父からきびしくしつけられて育った人ですから、私から見れば古い考え方に凝り固まった昔気質の人でした。
それだけに躾はきびしさを極めましたが、なかでも父が一番うるさく言っていましたのは中国人の心を忘れるなということでございました。
中国人の心を忘れないために父が私に課したことは二つございました。
一つは中国語を話すこと、もう一つは論語を読むことでした。家庭では日本語は一切御法度で、両親との会話はすべて中国語のみでした。
もっとも日本語が上手でない両親にとって中国語で会話するというのはごく自然のことでしたが、私は外で近所の子と遊ぶときは日本語で、家庭では中国語で話すという生活を送り、日本で育った二世にしては驚くほど流暢な中国語をしゃべることができるようになりました。
五、六才の頃、日本語の不自由な両親のために通訳をして時々ご褒美にもらったカルメラの味を今でもよく覚えております。論語を読むことと書き写すことは幼い頃から私の日課の一つでしたから、今でも主な文章はほとんど諳んじております。