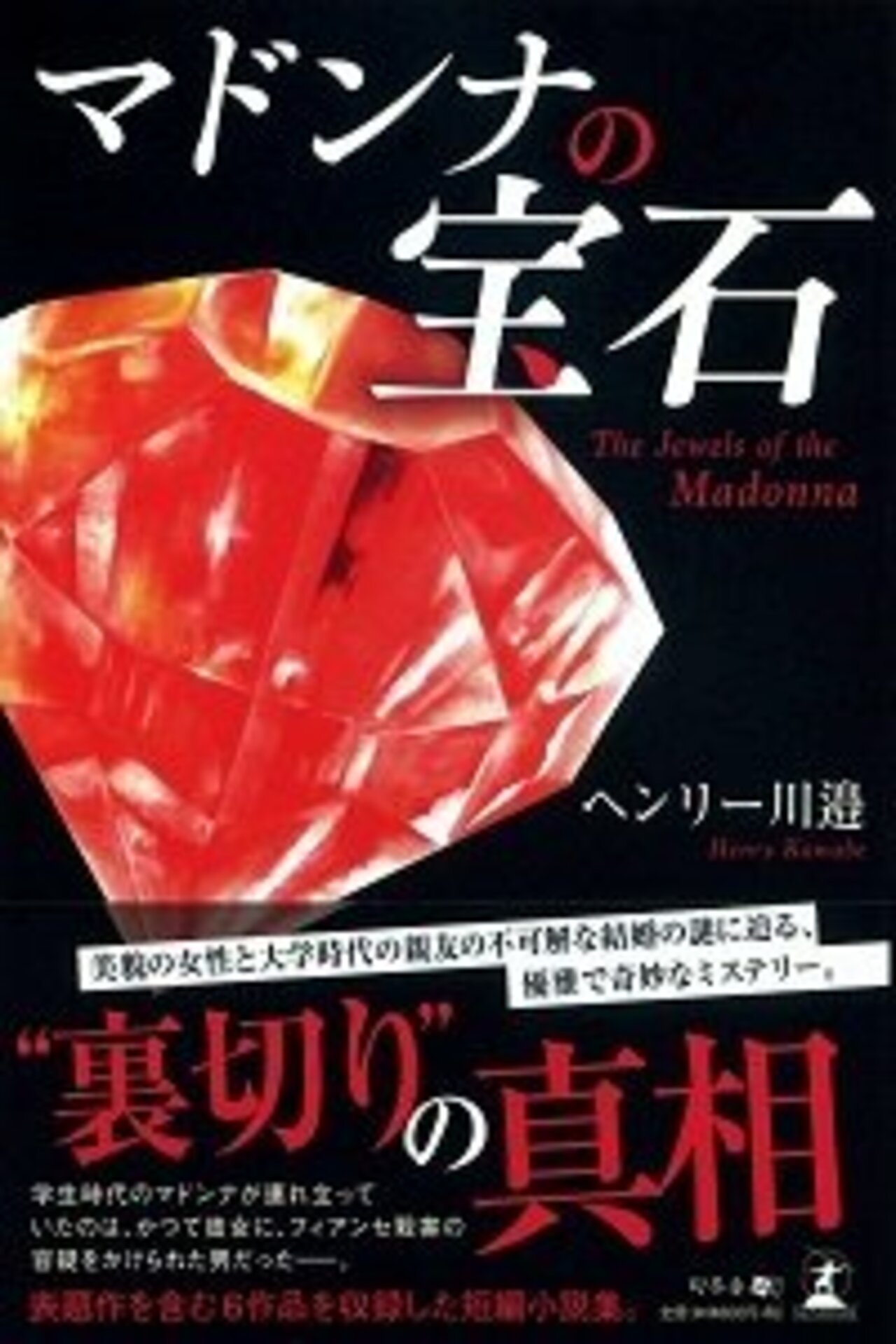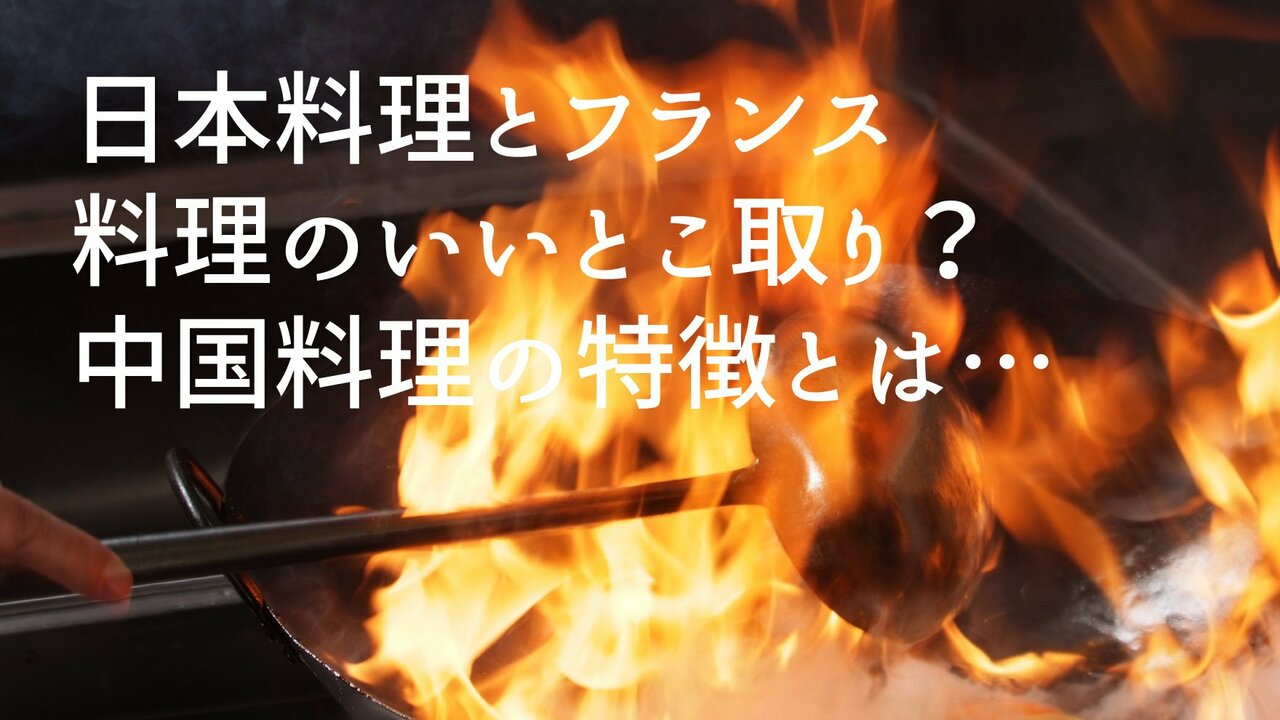奇跡の味
友人から退職祝いの席を設けたと誘われたとき、店の名前を聞いて十五年前の事件を思い出した。
あの事件は迷宮入りだったなとほろ苦い思いがこみあげてきて、来店前に当時の捜査関係の書類をもう一度ていねいに読み直してみた。
こうして店の前に立つと当時の捜査の様子がくっきりと脳裏に浮かんできた。「らっしゃいませ」若い中国人のウエイトレスの少し舌足らずな声に我に返った。
「予約をしておいたが席は用意できているかね」
幹事役の成瀬が鷹揚な態度で聞いた。
「どちら様ですか?」
「あ、先生、いらっしゃいませ。特別室を用意しております」
支配人らしい年配の男があわてて飛んできた。支配人に案内されて特別室に入った私は豪華な調度に驚かされた。精巧な細工が施された中国風屛風、色鮮やかな壺、見事な書体の掛け軸、象牙がはめ込まれた円卓、さすがに特別室というにふさわしい造りだった。
「ご無礼をしてすみません。まだ入ったばかりで先生を存じあげないものですから」
支配人が謝った。
「また新人を郷里から連れてきたようだね。気にしなくてもいいですよ。陳さんのいつもの道楽だ」
席についた成瀬が笑いながら言った。支配人が黙って頭を下げた。
「紹介しよう。こちらは支配人の張さん。張さん、今日はね、警視庁の名警部の引退を祝って同級生でささやかな宴の席を設けたんですよ。この人が名警部とうたわれた鬼塚、右手に座っているのが弁護士の遠藤、その隣が女子大で教鞭をとっている遠山です」
「錚々たる方々ですね」
「僕ひとりが途中で人生の歯車が狂ってしまって、しがない料理評論家稼業なんかをやっているんですよ」
成瀬はまた笑った。支配人が出ていくと
「ここはね、東京一の、いや日本一の安くてうまい中華料理店なんだよ。鬼塚の引退祝いというんで、掛け値なしに最高の中華料理を食わせてやろうと思って、それでここにしたんだ」
と成瀬が宣伝した。
「しかし、お前の本には書いてないじゃないか」
遠藤弁護士がクレームをつけた。
「自分がよく行く店は書かないんだよ。書けばHanako族がどっと押し寄せてきて、常連に迷惑をかけるからな」
「しかし、この部屋はすごいものだな。表は大衆風なのに、この部屋だけは別世界だ。壺は景徳鎮だし、書は王義之の臨書だ。名前は聞いたことがないが、この書体からみると臨書したのはいずれ名のある人に違いない。書だけでも大変な値打ちものだぜ」
遠山教授が感嘆した。
「さすが大学教授は目の付けどころが違うな。実はな、この部屋は陳さんが特別にしつらえた迎賓用の部屋で一般客用じゃないんだ。中国からの特別の客とか、大使館の接待とか、そういうのに使う部屋を無理に頼んで使わせてもらったんだ」
「十五年前にはこの部屋はなかったな」
私は記憶をたどりながら言った。
「なんだ、お前来たことがあるのか、この店に」
成瀬がびっくりしたような顔をした。
「仕事でね」
「ほう、面白そうじゃないか。どんな事件だったんだ」