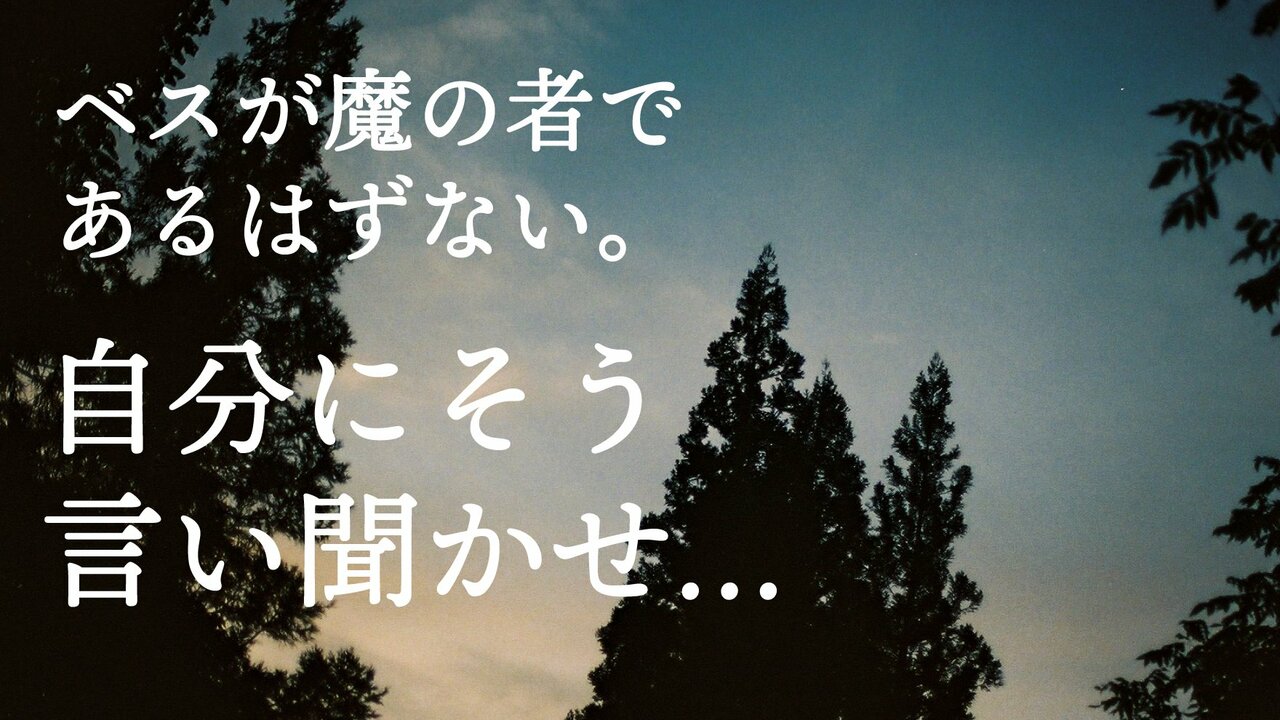ラウルはディアナベスの方を見ながらも、自分の経験を必死に思い出しながら、答えを探した。騎士は問われればすぐに返答しなければならない。それも騎士としての技能の一つだった。
「はい。たぶんあると思います。」
たぶんと言ってしまい、しまったと思った。
〈曖昧な表現は騎士の返答として避けるべし〉。
「つまり、僕は、いえ私は生まれてからずっと騎士としての教育を受け、城内で仲間たちと育ったのであまり機会がないんです。」
「でも、騎士仲間はたくさんいるのね。」
「はい。」
「よくわかったわ。でもそんなに難しいことではないのよ。私を王女だと思わなければいいのよ。まず、私のことは……そうね、ベスと呼んで下さい。あと、できるだけ敬語はなし。私はそうしてもいい?」
ディアナベスはラウルの眼を覗き込んだ。
「騎士同士も敬語で話すの?」
「いえ、階級によります。一緒に育った仲間たちとは、普通に。でもディアナベス、いえ、あのべス……。」
ラウルは言いよどんだ。
「貴女はその……王女ですから。」
「ラウル。想像するのよ。ここは城の中ではないわ。」
教育というのは大変な力を持っている。いかにラウルが厳しい訓練を受けて数々の難関を超え、選び抜かれて今の地位にいるか。
自分が小国の王女に生まれたために、どんなに奔放でいられるか。農民たちが複雑な外交問題に頭を悩ませないでいられるか。ブルクミランの陽気な町の人々が日々屈託なく笑えるか。
なかなか身についたものを一朝一夕には捨てられるものではない。
「さあ、ラウル。代わり番に夜を過ごすようにして、そろそろ休みましょう。どちらが先に番をする?」
「僕は一晩中起きているつもりです。慣れていますから。夜警も仕事のうちです。」
「私もよく徹夜します。一晩中ひとりで番をするのはお互いにとって良くないわ。集中力もなくなるし、狼が襲ってくるのはたいてい夕方か明け方よ。肝心なときにあなたが寝ずの番で疲れてしまっているかもしれないでしょう?」