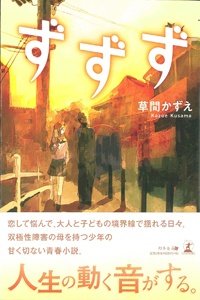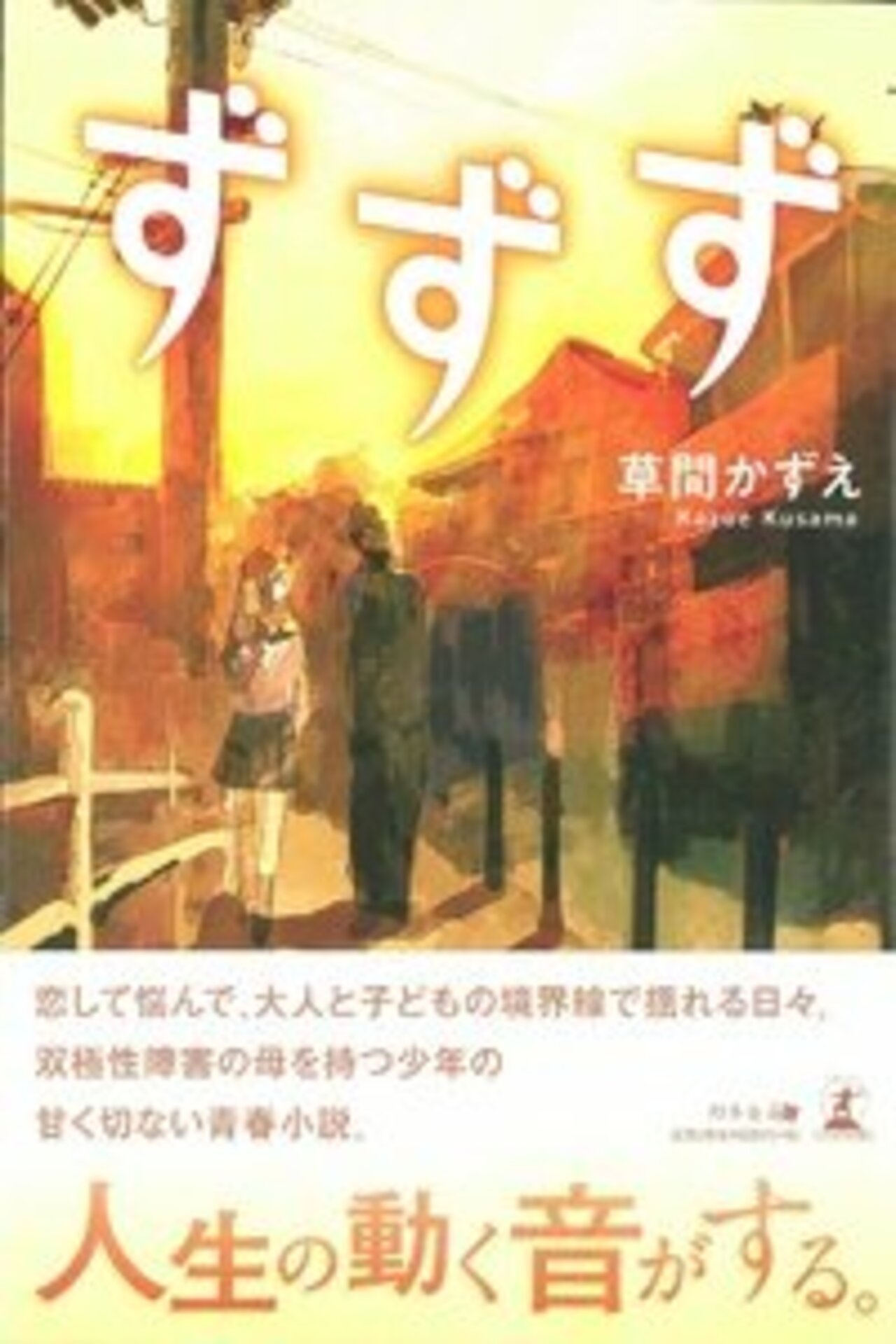そして、トレーの隅にあるもうひとつの紙コップには水が入っていることを教えてくれた。ガラスのコップでもない、陶器のカップでもない、プラスチックでもない、使い捨ての紙コップである。
「これは、ここで薬を飲む時のお水よ。今日はアッキーママが夕ご飯を食べてお薬を飲むのを見届けるわ」
「レストラン・菜の列に並ばなくていいのですか?」
「ここ常夏ハワイアンズの七〇七号室は特別室よ、食事もルームサービスよ」
「みんなと一緒に食べたいです。田畑さんと約束しました」
「まあまあ、しばらくはルームサービスを堪能してね。歯ブラシも付いているからここで磨いてね。外に出る必要はまったくないのよ」
「それは出られないって事ですよね?」
「ふふ、しばらくしたらきっとここから出られるわ。それはアッキーママ次第よ」
そんな事を言われても不安が不安を呼ぶだけではないか。それなのに大滝ナースは平然としていて、アッキーママの食後の薬を飲んだのを確認してから勤務が終わるのだと教えてくれた。
「帰るんですか? 私、夜は大滝ナースが居ないと不安です」
「大丈夫よ。一時間ごとに他のナースだけど見回りをしているから、安心して寝ていていいのよ」
確かに静かではあるが静かすぎて、かすかな物音さえしない特別室は闇の中へ放り出された猫のようだ。田畑さんはどうしているか、前歯一本はアッキーママを探しているだろうか、色んな事を考えてしまう。
それでも今日は大滝ナースは夕ご飯をアッキーママが食べ終わるまで付き合ってくれるようだ。