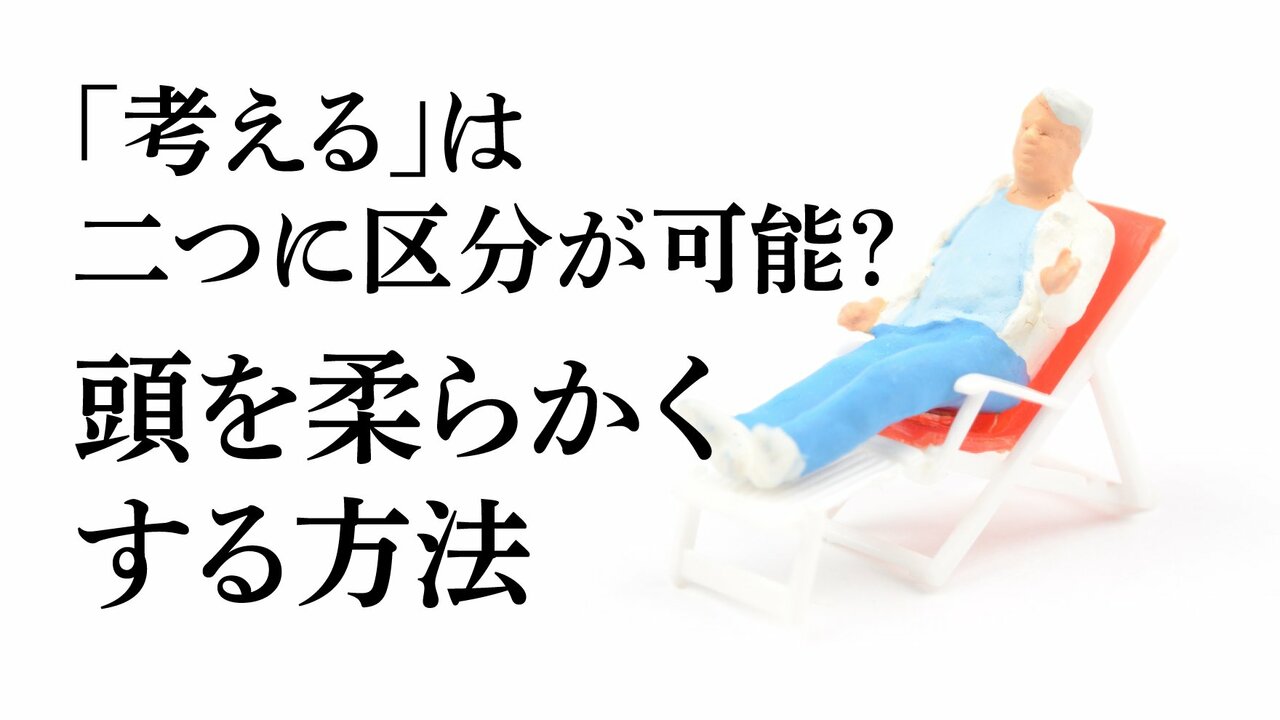「いい学校へ入れば、いい友達ができる。そのためには勉強せよ。名門高校へ入れば、それだけのことはある……」
これが良平の口癖だった。
ところが、高校へ入学した途端に、稔は、わがまま、贅沢の限りをするようになり、気が咎める風もなしに、あれを買ってくれ、うまい弁当を食わせろ、というようになった。
態度はいよいよ横暴となり、母親の横腹を蹴飛ばし、しばしば痣をつくるほどになった。そして、とうとう登校拒否までするようになってしまった。それを良平が注意すると、稔は父に向かって唾を吐き、
「手前は、俺がやりたいことに全部反対しやがったくせに、何を言いやがる!」
と言った。さすがにカッとした良平は、
「何だと? 稔。もう一度言ってみろ。親のありがたさもわからん奴はさっさと家を出て行け!」
と大声をあげた。すると稔は、獣みたいに目を見開いて、
「オウ、いつでも家なんか出てやる。出てやるから出て行く所と銭を用意しろ! この間抜け親父め」
良平の頭を殴り、部屋の中の物を手当たり次第放り投げた。稔は、その頃のことを今でも憎々しく思い出すのだ。家から電車で2時間もかかる享楽街のパチンコ屋で遊んでいる時も。
いや、遊びなんていう状態ではない。狂ったように、パチンコ玉を弾き飛ばしている時だって……。
このように遊んでいて、もう何時間経っただろうか。金も損した。とうに3万円は超えている。
握りしめていた最後の玉をとられて、
「こん畜生!」
パチンコ台を稔はぶっ叩いた。頭に血が昇っているのがわかる。その時、チラッと隣のパチンコ台を見た。隣の台は、雨のように玉が出ている。
床上の木箱には、パチンコ玉が重い鋼の塊となって光を放っている。
「糞、よく出る台だ」
小さな声で言い、玉を弾いている男の横顔を見た。
すると、男は気づいたのか、稔の顔を、サングラスの奥からじっと睨み返した。
稔は一瞬、戸惑った。