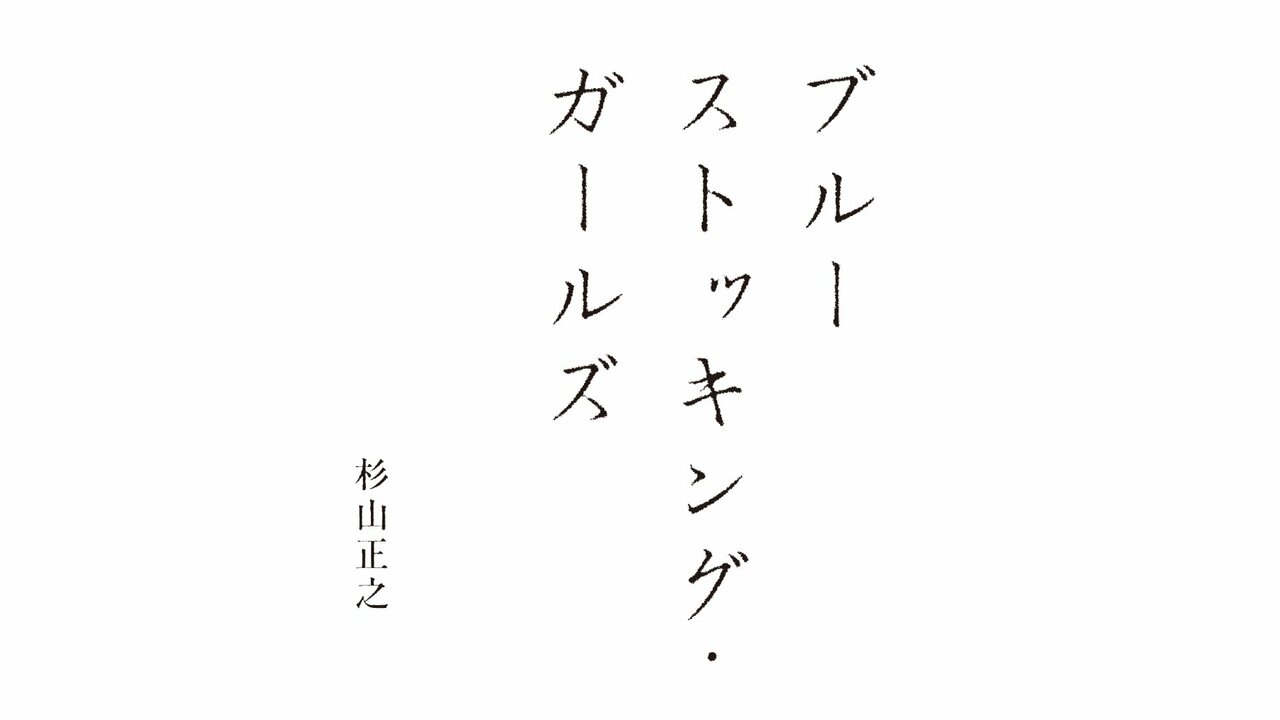第3作『山脈(やまなみ)の光』
三日間のぼくたちの展覧会が終わり、村瀬は「アパートを探す」と言って東京に一足先に旅立っていた。
搬出の日に園田は現れなかった。
「園田はどうしたんだ」
「知らない」
朱美は園田のことには無関心のように答えた。いつものように、美術部の後輩たちは大声ではしゃぎ回っている。ぼくは彼らと一緒にふざけるでもなく、ただ遠いことのように聞きながら、黙々と自分の作品を梱包した。
コウちゃんのトラックは、笛吹川沿いの桃畑の中をまた帰っていった。窓をいっぱい開いて、軽トラの窓からの花冷えの冷たい風を体に浴びた。
家の納屋の前で、カンバスを降ろしてもらった。
「じゃあね、先輩。寂しくなったら、いつでも部室に来ていいよ」
香子が無邪気に笑った。
「浪人生活は辛いよ」
朱美はクスリと笑い、
「先輩、頑張ってください」
とキリッとした目でぼくを見た。
「じゃあな。いつでも相談に来い」
とコウちゃんはそう言うと、エンジンをかけた。愛車の喘いだエンジン音が鳴り響いた。軽トラが桃畑の一本道の向こうに走り去るのを、ぼくはずっと見送った。
部屋の窓から、甲府市街に雷雨が降り注いでいるのが見えた。市街にある愛宕山の葡萄畑が白くかすんでいる。白い霧がそこに沸き立っている。
間もなく雨はこちらに上ってくるだろう。昼前まで部屋の扇風機が壊れていたので、脂汗を流しながら問題集に取り組んでいた。しかし頭には入らない。もうろうとしていた。
鉛筆を投げ出したい気持ちに耐えていた。夕立のおかげで、冷たい風が部屋に流れ込んできた。ノートを放り出し、サッシに肘をついていた。
ぼくは、急変していくこの盆地の夏の気象をしばらく眺めていた。ぼくの通っている山科美術研究所は、アパートを兼ねたビルの十二階にある。