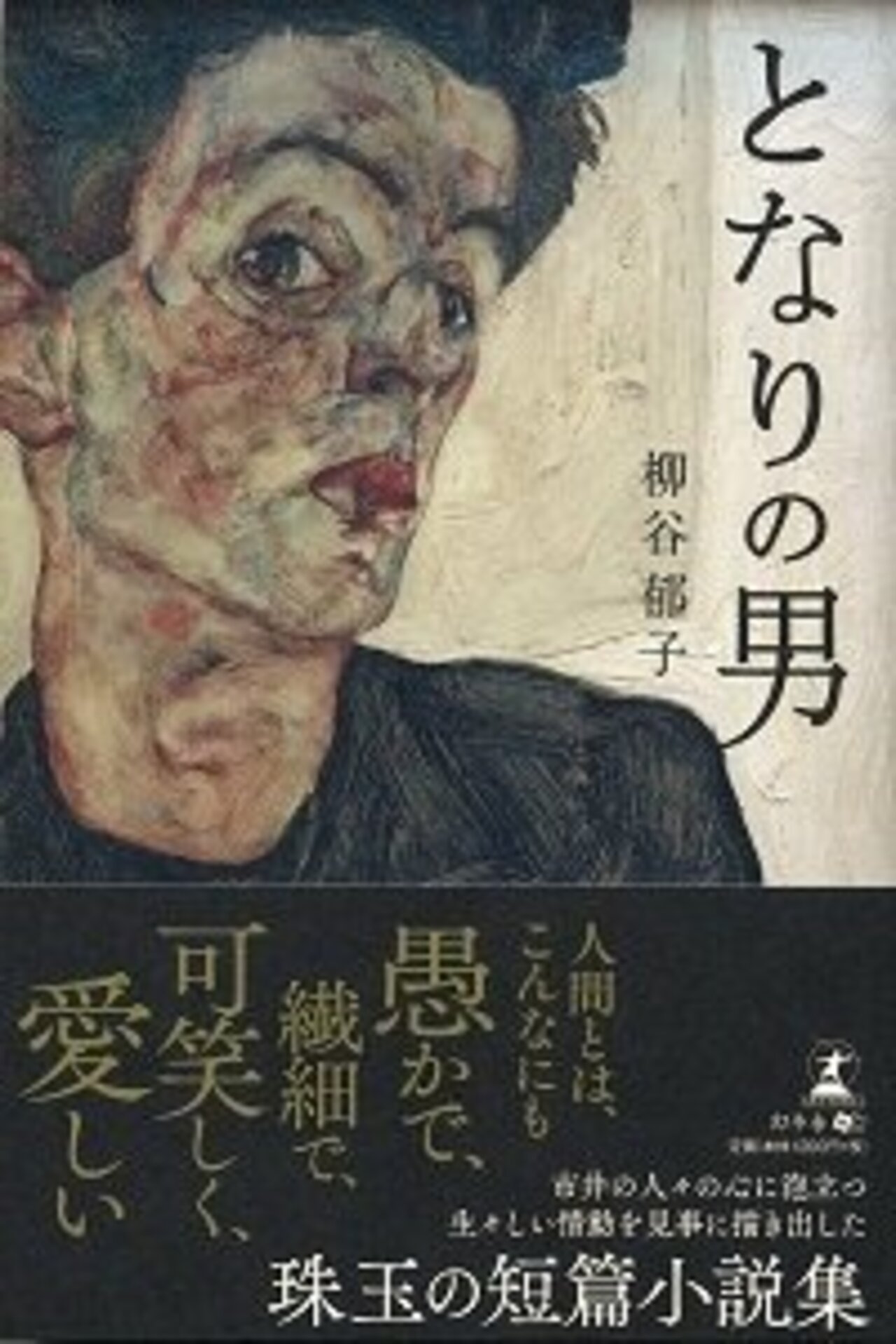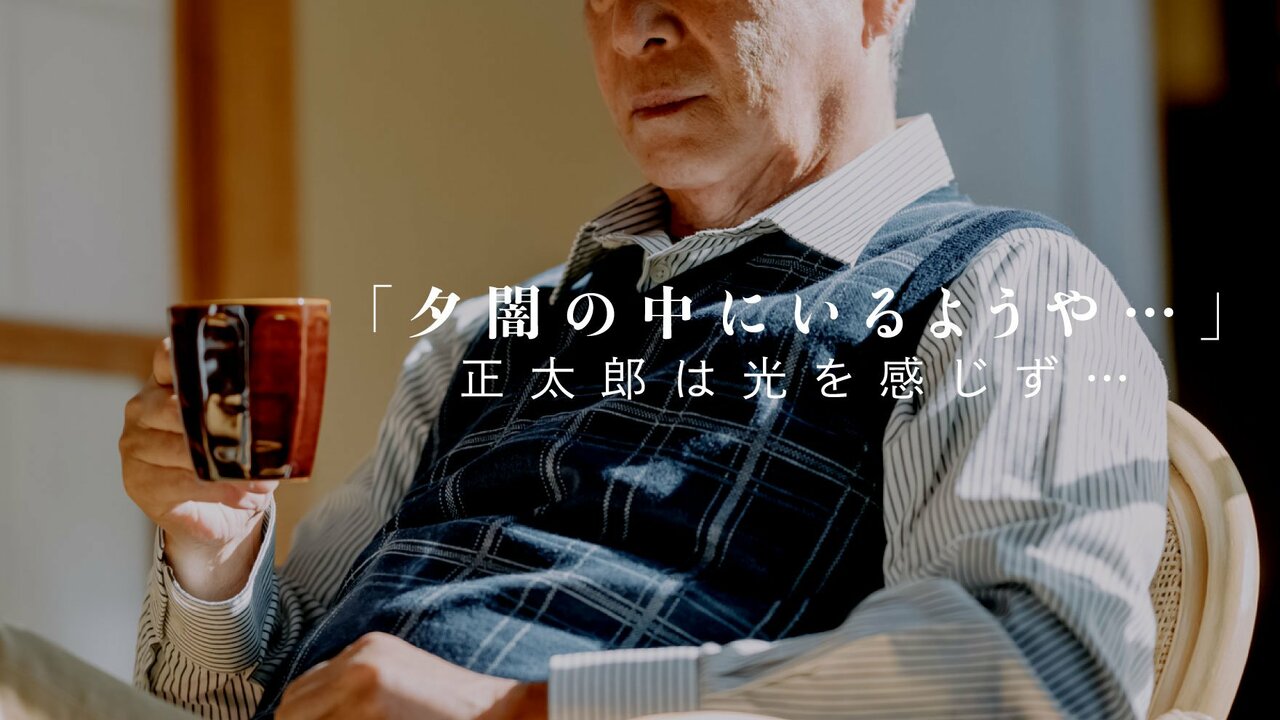言葉も表情も人間もちゃんとあなたたちに通じるのに、神秘と不思議の国からやって来た使者のように、或いは悪魔のように、静かだが饒舌で、平易だが奥深く、暗鬱かと思えば朗らかで、若いのか年とっているのか惑わせる彼らは眩しかった。
ユタから新宿へ、新宿から一仙のアトリエへ、何杯も重ねたオンザロックとカクテルの酔いにまかせて、あなたたちはその眩い一日を完結させるために最後の成果を期待した。すでに深夜も更けていたが、誰もそんなケチな思案など口にしなかった。
シュールレアリズムを謳う自分たちの作品世界とはどんなものか、アトリエを見せてあげようという画家たちの誘いに心弾ませて、あなたたちは勇躍、最終電車を乗り継ぎ、どこをどう歩いたのか彼らの案内に従ったのだった。
高い天井を戴いて鎭まる広いアトリエに、蛍光の白光を浴びて、何脚かの大きなカンバスと重々しい額縁や画がそれぞれの場所を占めて浮かび上がった。
足の踏み場もない絵具まみれの乱雑な仕事場を想像していたあなたは、その作品の確かさと清潔な空気に、わずかに残していたそこはかとない警戒心から解放された。
「この絵、ガンジス河に沈む夕陽ですか。燃える夕陽の光の中で戯れている生命たちですか。死者たちですか。生命の歓喜ですよね。死者の祈りですよね」
大作の前に立ったあなたは、ようやくインド研究会の学生らしく、早速、いつかは訪ねてみたいと思っているガンジス河を絵の中に見る。夜気に晒されてきた酔いはいつの間にか遠のいていた。
「同じなんだよ。生命の歓喜も死者の祈りも。しかしガンジス河とは恐れ入ったな」
一仙が後ろに立っていた。
「この絵、わたしが抱いているガンジス河のイメージと同じなんです。ガンジス河じゃないんですか?」
「夢から見た現実。現実から見た夢」
一仙は面白そうに言い、あなたの肩にその骨張った大きな手を置いた。
「さ、みんなで雑魚寝するとしよか」