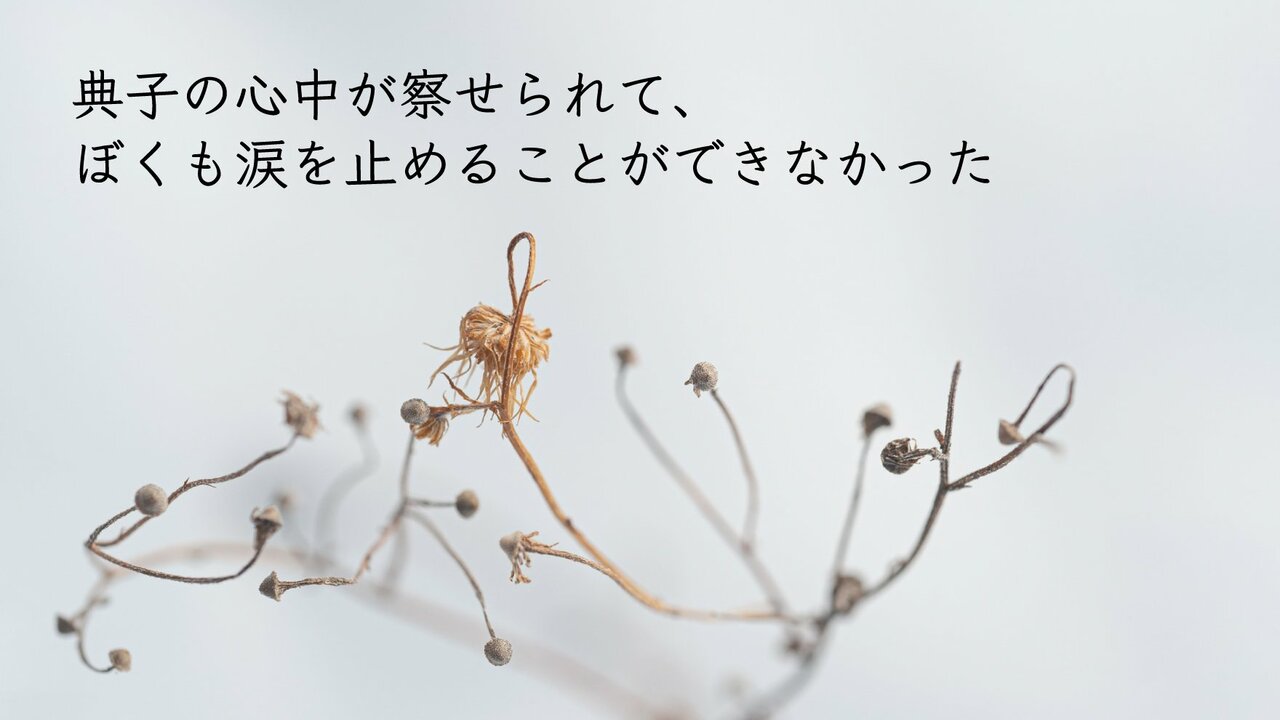別居
典子と結婚し、自分の思い通りにならない現実に突き当たったとき――。ぼくが選んだのは、話し合って解決をはかるという根気を要する作業ではなかった。また、胸に手を当ててみずからの非をかえりみ、それをあらためるという謙虚さでもなかった。
【関連記事】「出て行け=行かないで」では、数式が成立しない。
ぼくがしたことといえば、そうした姿勢をはなから放棄したうえで、望んだのはこのようなものではないと典子との結婚を否定することだった。自分の足を引っ張るもののごとく、それを呪うことだった。
自分にふさわしい相手はほかにいて、そのだれかとめぐり合うことで、つぎこそはきちんとした結婚を成就させるのだという独りよがりな思い込みにみずからを閉じ込めることだった。
そんなぼくが、結婚という不都合な現実を回避する手段として思いついたのが、離れて暮らすという方法、すなわち別居だったのだ。
だから、しばらく距離を置いてみないかとぼくが典子に持ち出したとき、でも、あるのは自分の都合だけで、典子の胸のうちにはみじんも思いをいたさなかった。
買い物帰りに不動産屋の前で足を止めたときも、窓ガラスに貼られた物件案内を思いつめた顔で見つめる典子とは対照的に、ぼくのほうは月々の家賃や引っ越し費用、それに当座そろえねばならない家具や電化製品などの出費のもろもろを頭のなかで計算していた。
ぼくにとって別居は、じつはぎりぎりの選択ではなく、自分の経済的な負担を天秤にかけてのものだった。もっと言ってしまえば、結婚という世間体に疵をつけることなく、気ままな生活と、他の女性のことを考える時間と自由を手に入れる方便でもあったのだ。
「離れて暮らしたら、また以前のように手紙を書くかもしれないわね」
典子がそう言ったとき、それが典子のどんな気持ちから出た言葉なのかがぼくにはわからなかったから、返したのは、
「そうだね、手紙だけでなく、またむかしのように『遠野物語』や『平家物語』を読んで感想を語り合おうよ」
と、そんな呑気な的をはずれたせりふだった。別居が既定のこととなったときには、
「ひとりで暮らせる自信がついたら出ていけばいいよ」
とことさら恩着せがましいことを言った。
「そんな自信があるならとっくに出て行ってるわよ。そんな自信なんかないから、この家から出られないでいるんじゃないの。……でも、離れて暮らすことであなたとの関係がいまよりも良くなるのなら、あなたの笑顔をまた見られるようになるのなら、そうするしかないから出ていくのよ」