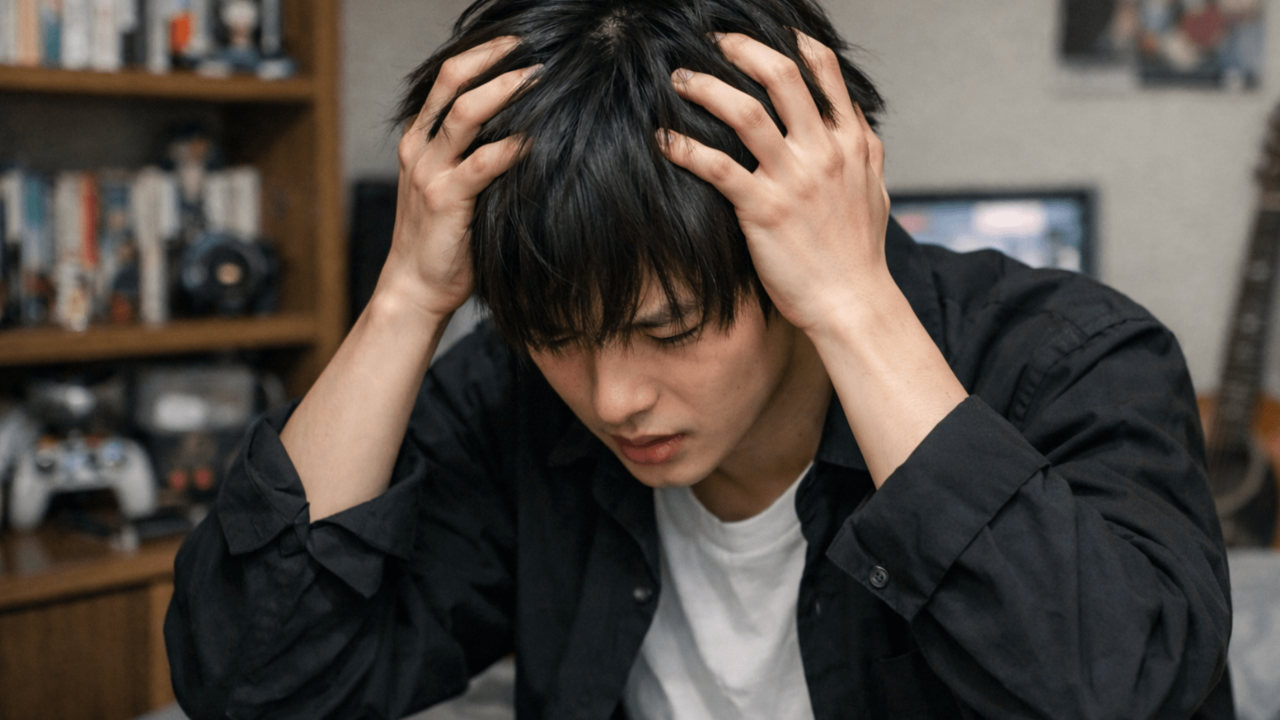そして、いよいよ典子の引っ越し先が決まった晩のことだ。
「あーあ、これで離ればなれね。籍は入れたままでいいのかしら」
すこし投げやりな典子に対し、自由をつかみかけたぼくは、
「離れて暮らすだけで、べつに別れてしまうわけじゃないよ」
と、別居がさも日常のつづきであるような言い方をした。
「だったら、週の半分は寄ってね。ひとりだとさびしいから」
典子は試すような目でぼくを見る。
「寄るよ」
とぼくは答えられなかった。たったそれだけの言葉をぼくは口にできなかった。
「そうよねえ。あなたは自由になるんですものね。あーあ、ほんとうは出て行きたくはないんだけどな。でも、あなたは私のことなんかぜんぜん見てくれないし。それでもあなたにすがっていこうと思っていたの。そんな自分がみじめだとわかっていても。でも、出て行くんだったらいましかないの。だって、いまだったら、あなたの笑っている顔だけを記憶のなかに残せそうだと思ったから」
そう言って典子はぼろぼろと涙をこぼした。
「まだ涸れていなかったのね。涙なんか、もうとっくに涸れていると思っていたのに」
子どものように典子は両袖で涙を拭き、それから思い出したように、
「明日、荷物の整理をするわ」
とぽつり言うと、壁にかけてあるドライフラワーをはずした。いまでこそ干からびているその花は、ふたりの結婚パーティーのときに典子の胸元を飾っていたもので、それを手に持ったまま典子はふたたび顔をくしゃくしゃにして泣いた。
典子の心中が察せられて、ぼくも涙を止めることができなかった。