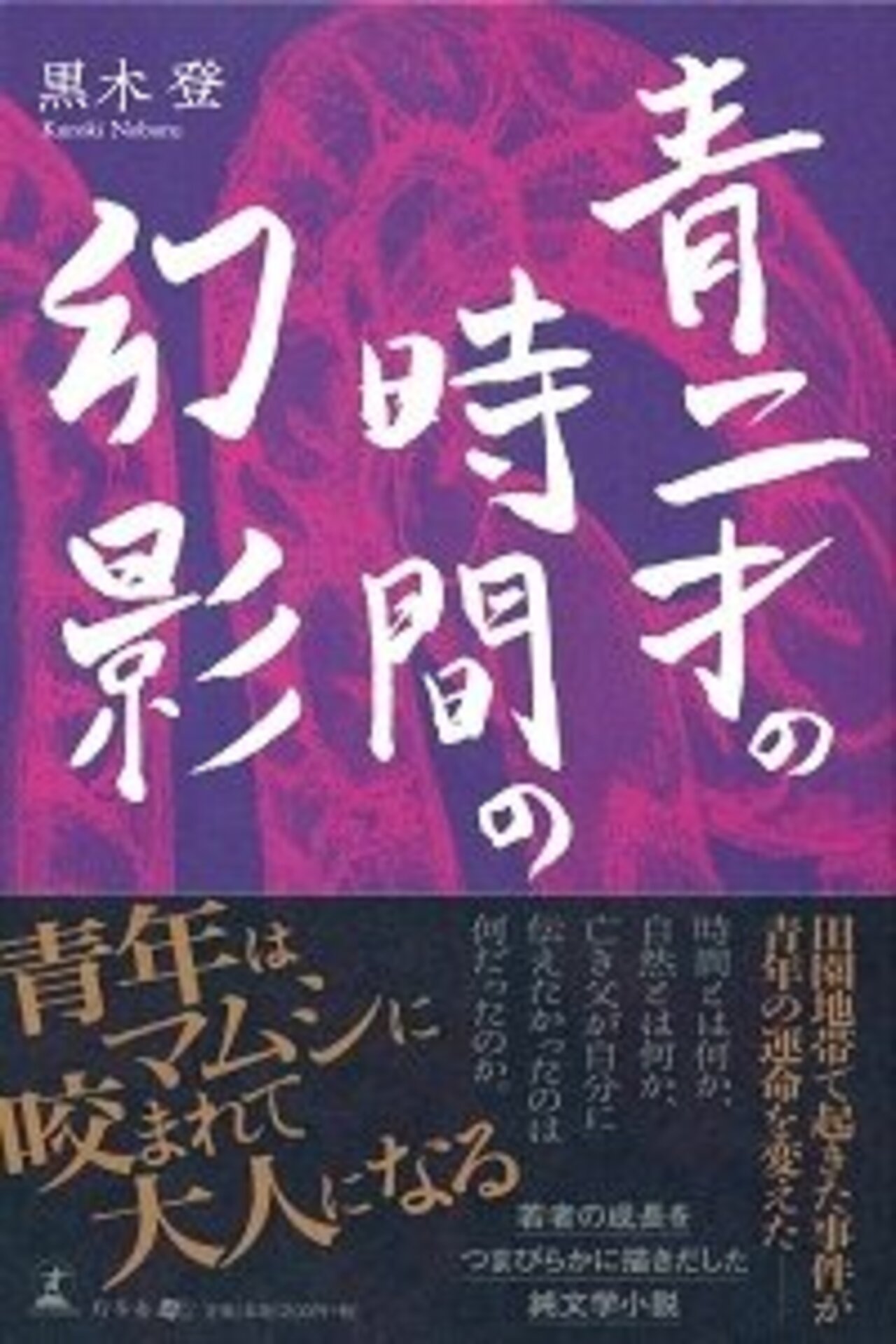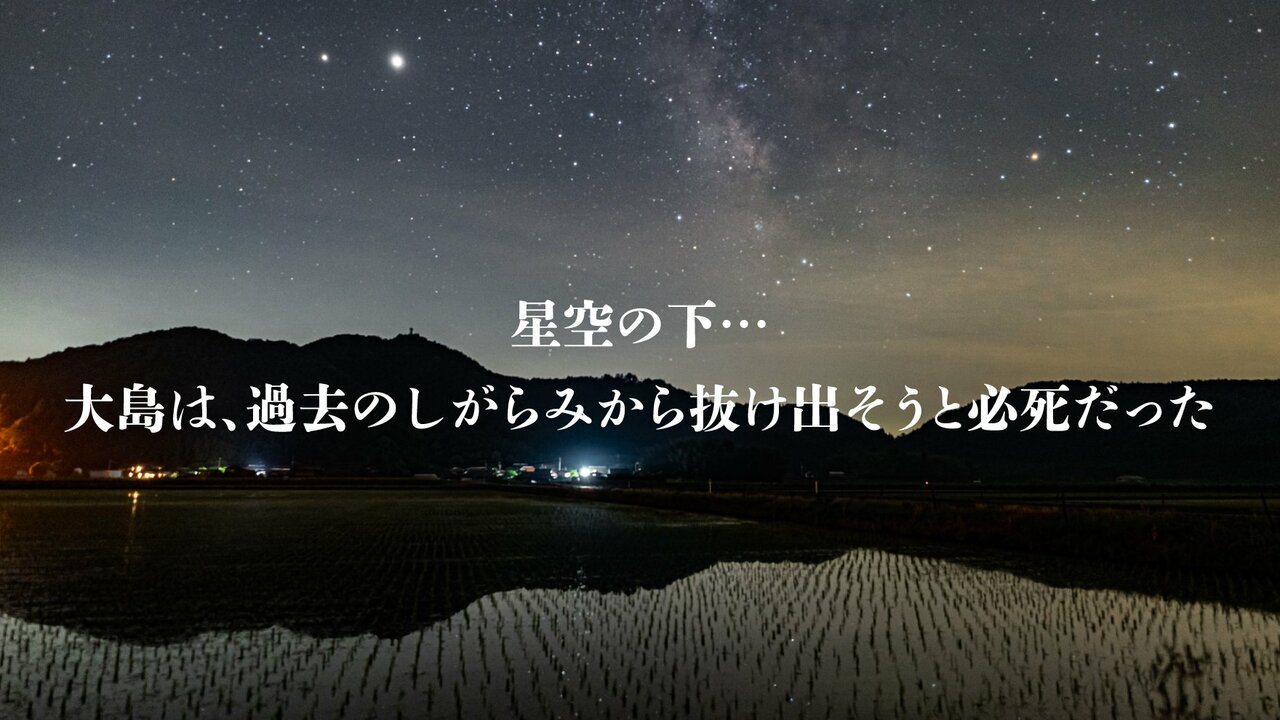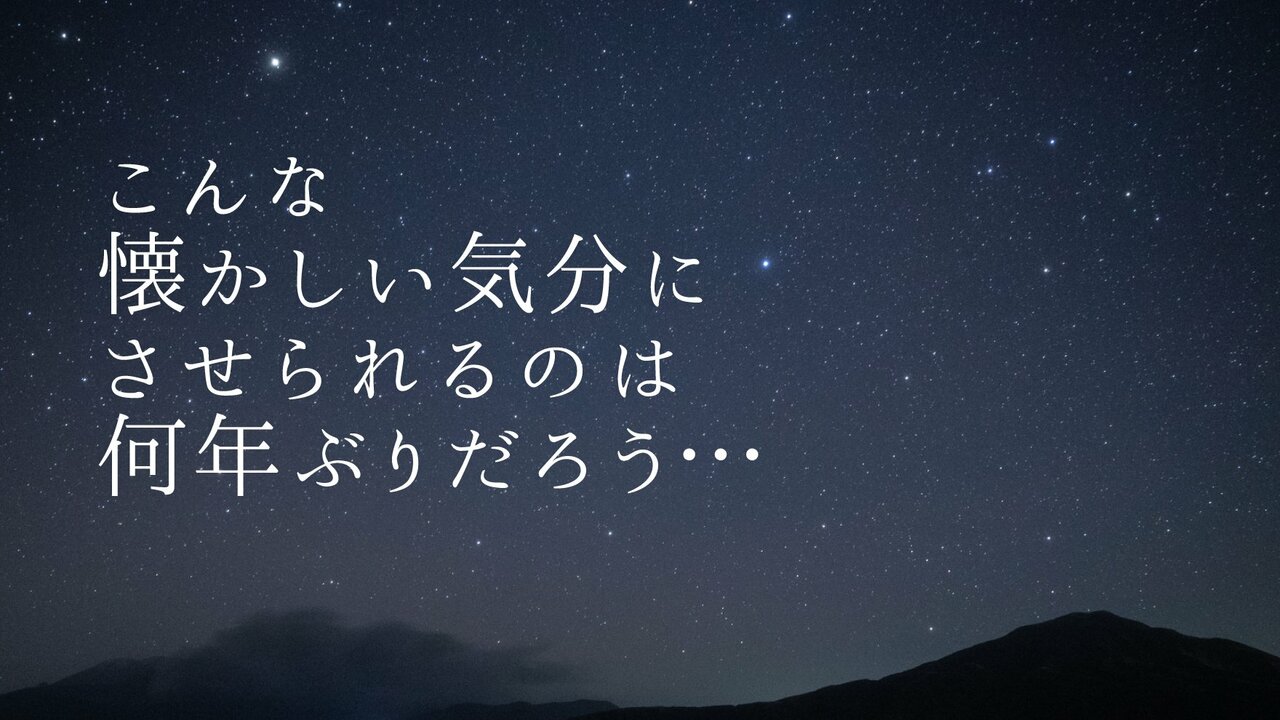「でも、あんたは本当に運が良かった」
腕組みしながら佐藤が訊く。
【人気記事】JALの機内で“ありがとう”という日本人はまずいない
「マムシを専門に捕っている人がいた頃だから、もう二十年も前のことになるかな」
「だろうな、最近じゃマムシのマの字さえ聞いたことがない。だいたい新聞に書かれるくらいだから、よっぽど珍しいんだよ、こいつは──」
「でも、あんたは本当に運が良かった」
「はあ……」
大島はベッドから首だけ浮かせ、少し恥ずかしそうな顔をした。
「全く面白いやつだよな、お前は……」
と言いかけて、佐藤はふと口をつぐんだ。ドアが開いて、看護婦が入って来たのである。看護婦は佐藤に気づいて何か言おうとしたが、佐藤のほうが先に何かを察知したらしく、急にベッドから腰を上げる。
午前中は、患者の安静時間になっていた。佐藤は振り向き様に、
「とにかく、ゆっくり養生することだな」
と勝手なことを言って、そそくさと病室を出て行った。看護婦と二言三言、言葉を交わしてから、大島はまたベッドに身体を沈めた。カーテンの隙間から紺碧の青空が見えた。
大島は、虚しい気持だった。何も考えたくなかったが、考えまいとすると、それはひとりでに浮かび上がってきて、不快な脈を打ち始めるのだった。
それは、あまりにも屈辱的な出来事だった。次第に瞼がつぶれ、睡魔が襲ってきたときも、大島はしきりに昨夜のことを思い浮かべようとしていた。救急車のサイレンの音がけたたましく鳴り響き、そうして夜の静けさが打ち破られたのがいけなかったのだ。
救急車が病院に横づけされるや否や、すばやく数人のやじ馬が群がった。そして担架で運ばれる男を食い入るように見つめ、口々に何やら囁き合った。
「どこでマムシに咬まれたんですか?」
そんな声がしたようだったが、はっきりと覚えていない。大島はショックで顔が蒼ざめ、意識は半ば朦朧としていた。
救急治療室に医師と看護婦が待機していて、直ちに手当てが始まった。その間、耳元では救急隊員が身元調査をする。名前、年令、職業、住所等……。
大島がか細い声で言ったとき、一人の老人が心配そうに大島の顔を覗き込んだ。この老人が急を知らせ、病院まで付き添って来てくれた人に違いなかったが、大島は声をかけるほどの心の余裕はなかった。
大島の端正な顔立ちは一見、律儀そうにも見えたが、今は正気を失い、恐怖心でひどく歪んでいる。マムシに咬まれたのは、左足の小指。わずかに刺し傷が入り、そこからうっすらと血が滲んでいる。