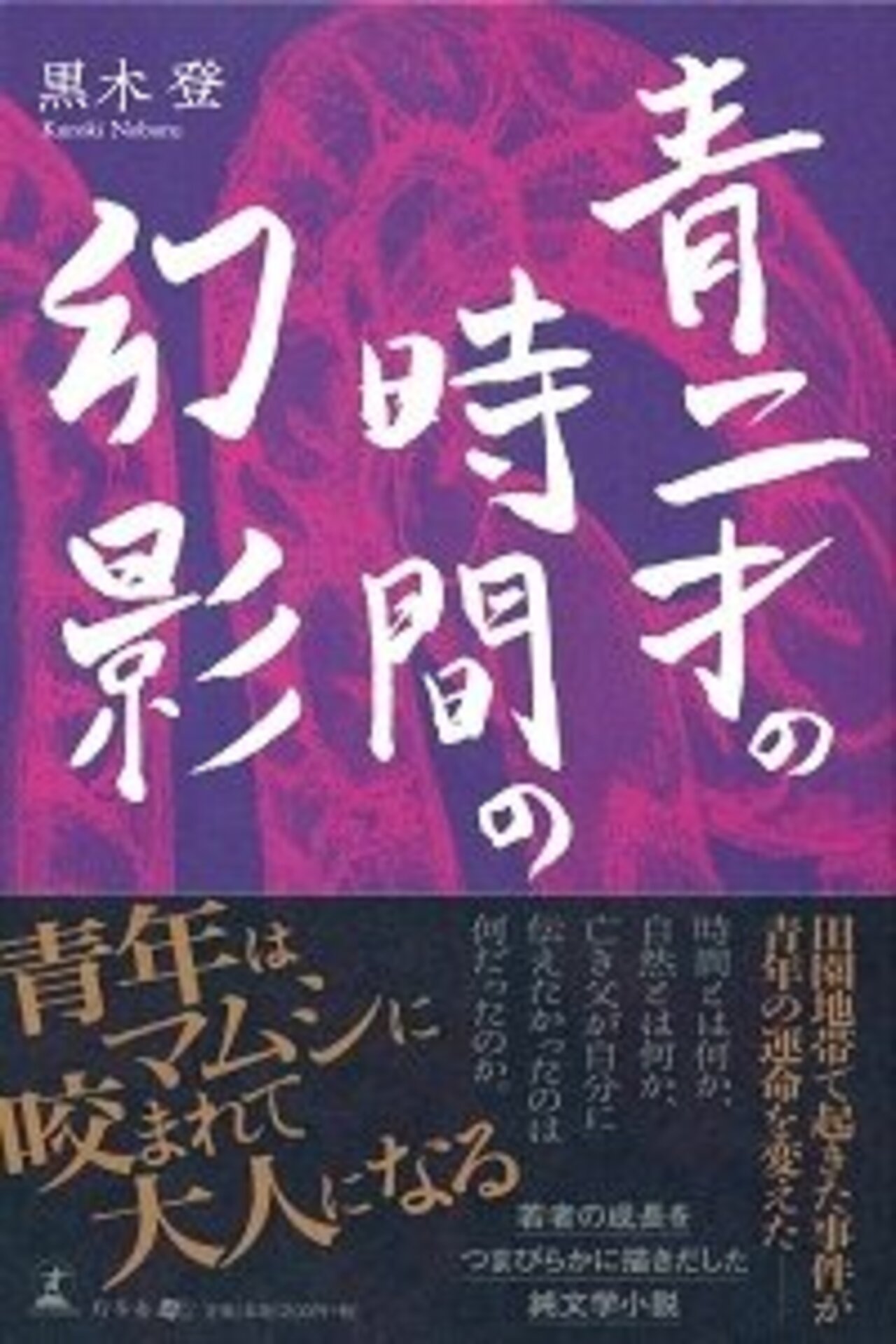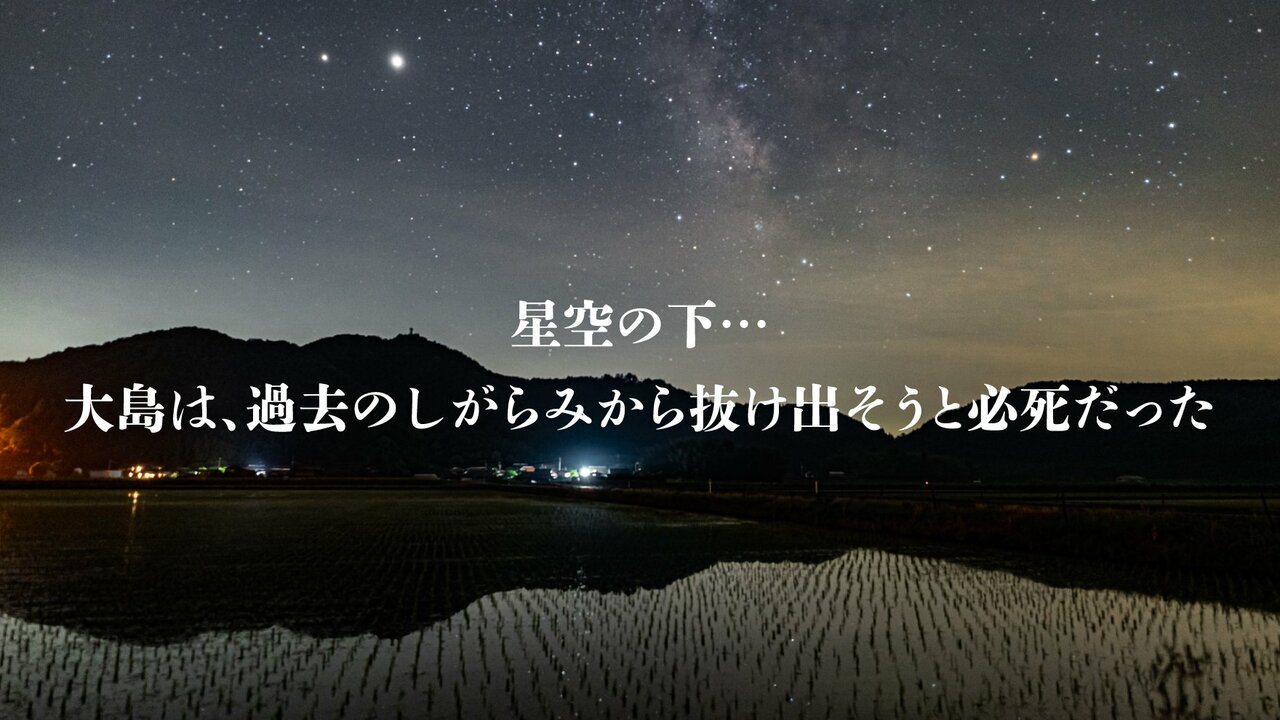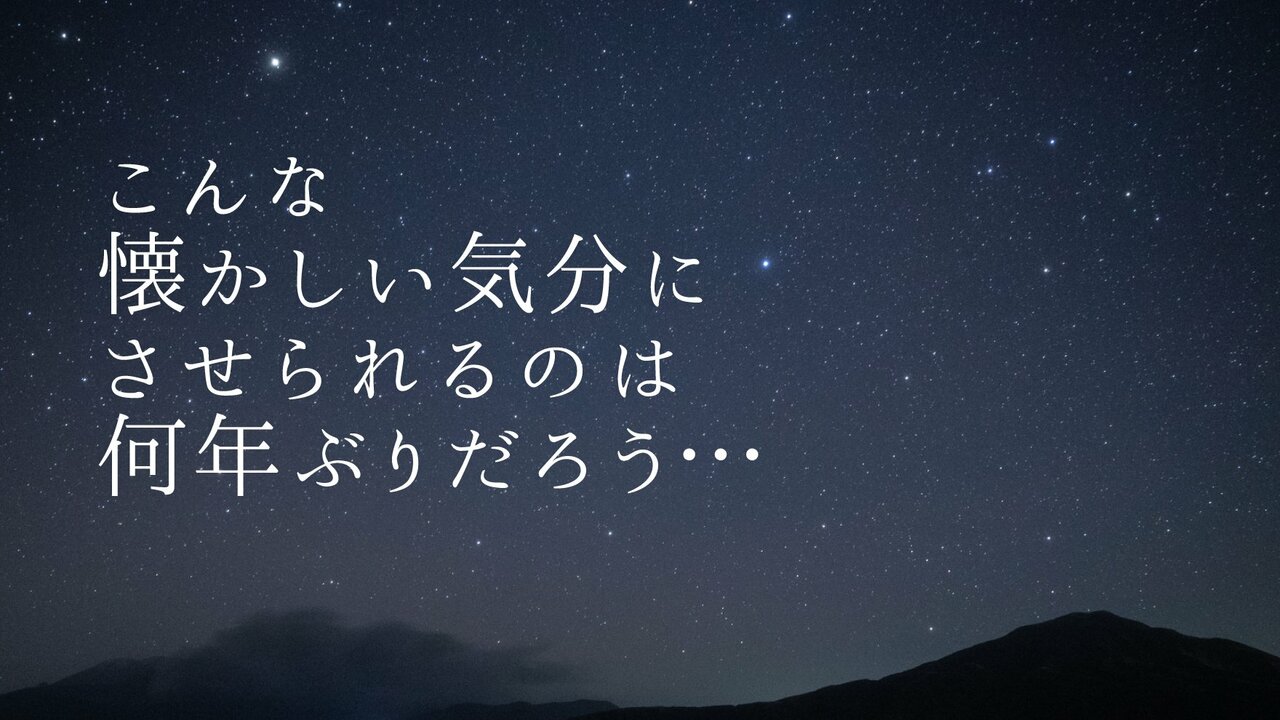珍しそうな目つきで大島を眺める佐藤
「やっと気がついたようだな。そう妙な顔をするなよ、これでもお前のことを心配して来たんだぜ」
呆気に取られている大島にそう言うと、佐藤は新聞に書いてあったことなどを、やや面白半分に語る。
「会社へ行けばお前の話でもちきりだし、朝からお笑い草さ。まさかお前がマムシに咬まれるとはな。
全く恐れ入ったよ、これは」
「そう言うなよ……」
大島はムッとして言ったが、その声は小さく力がなかった。
まだ頭がボーッとしている。体は鉛のように重い。眠ったという意識はなかった。
ずっと起きていたと思うが、はっきりしない。
看護婦に声をかけられ、勧められるままに朝食をとったものの、食欲はなかった。
ベッドに横になってからも、また果てしない靄の中を彷徨っていたような気がする。
瞼は腫れぼったく、何かにうなされたような不快感が残っている。
「今朝、社長が何と言ったと思う?」
佐藤は、そう前置きして、
「会社始まって以来の珍事だって。田中と谷口はクスクス笑うし、朝から白けっ放しさ」
「………」
「そこか?」
ベッドの端のほうにちょこんと腰を下ろすと、佐藤は包帯が巻かれている大島の左足を顎でしゃくった。その部分だけ掛け布団からはみ出し、少し高くしてある。
「マムシを踏みつけたのか?」
「………」
「だろうな、踏んづけりゃマムシだって黙っていないさ。一体、あんなところで何をしていたんだ?」