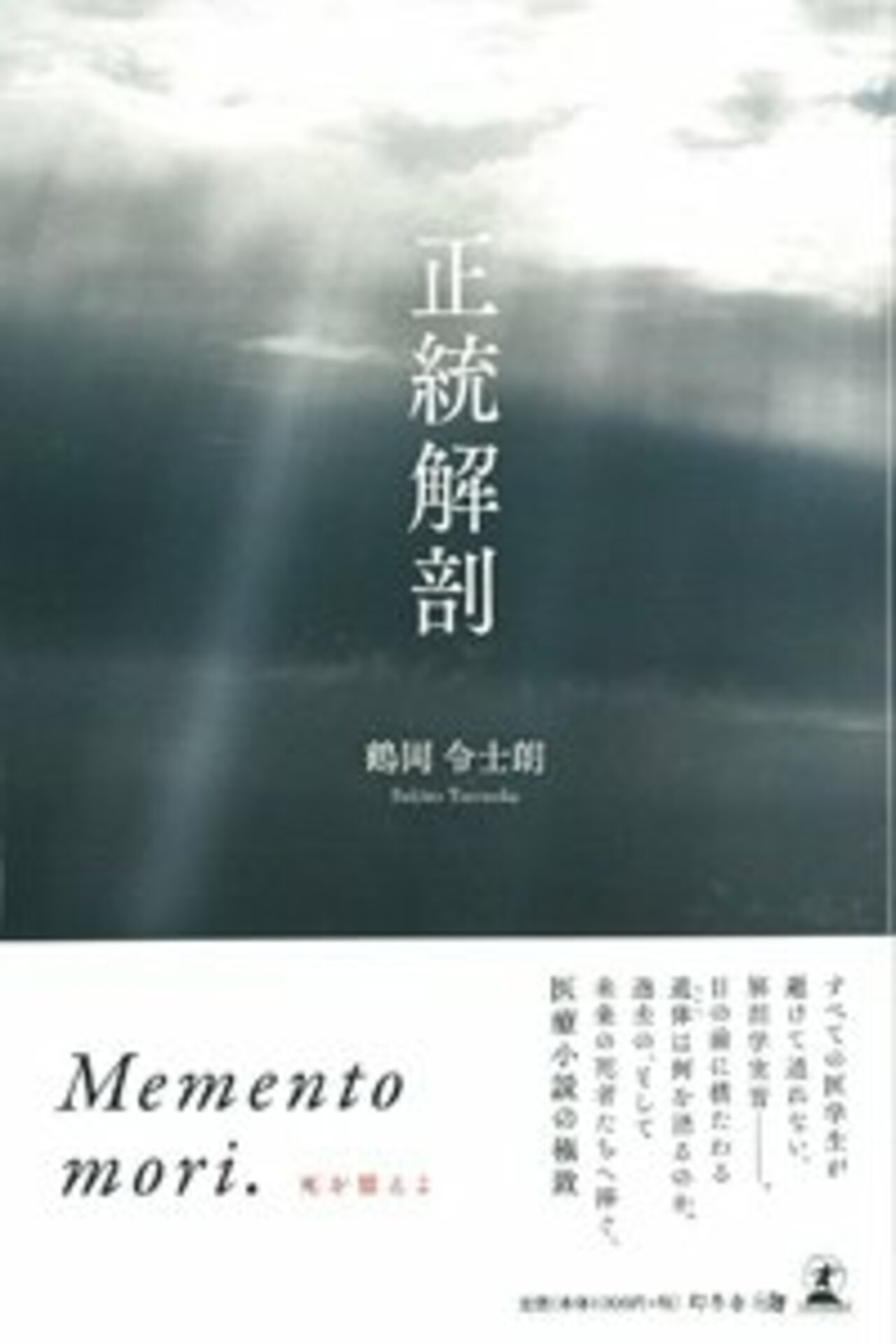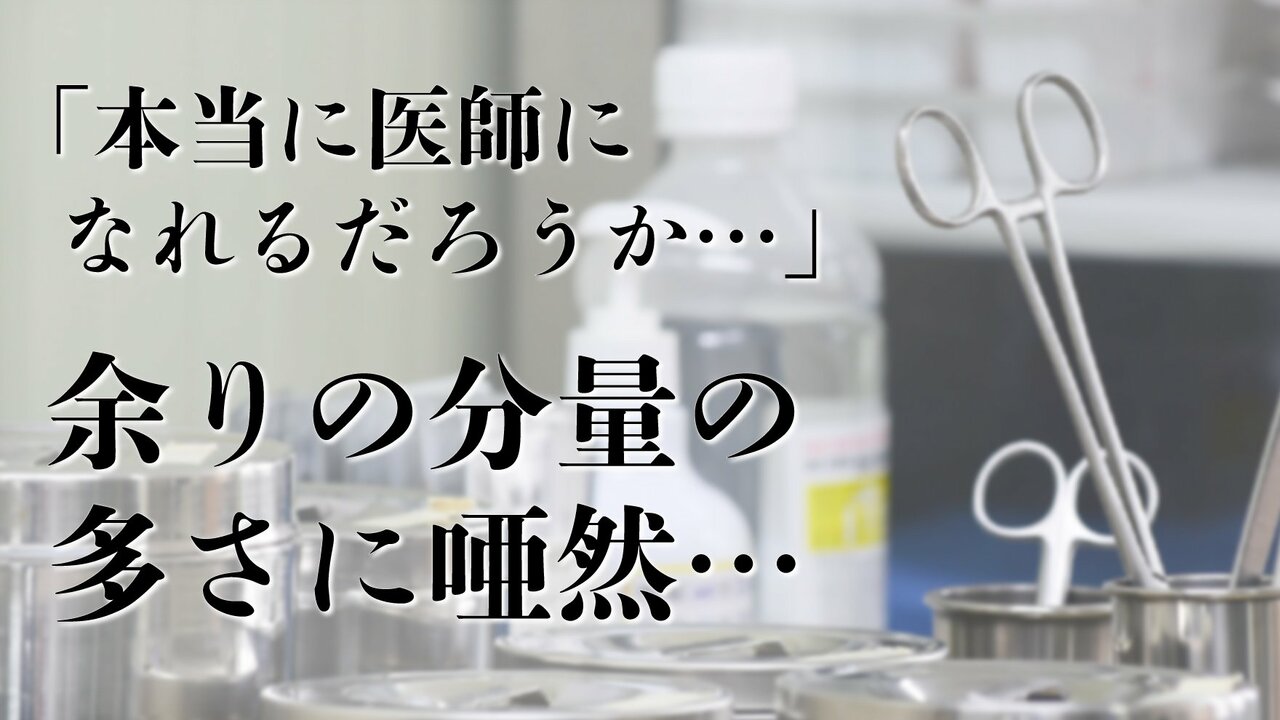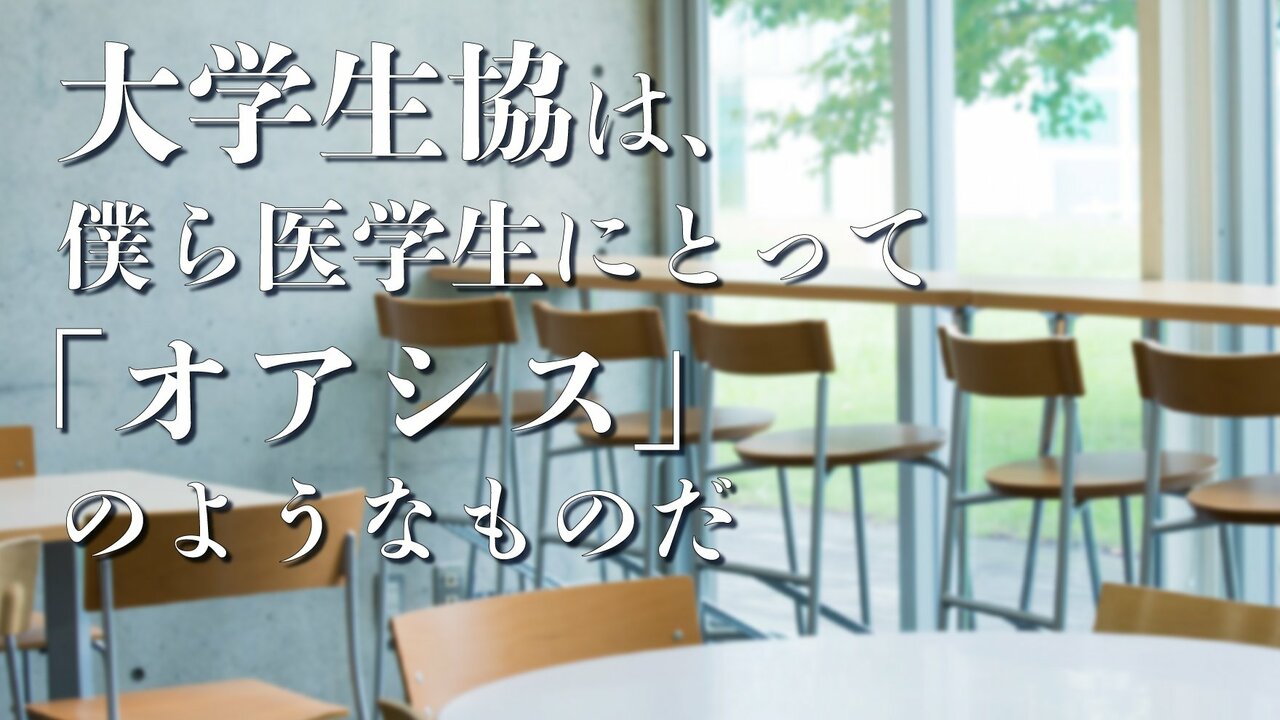生命の崇高と人体構造の神秘を描き切る傑作。
ほぼ100日、約3カ月におよぶ正統解剖学実習。死者と向き合う日々のなかで、医学生たちの人生も揺れ動いていく。目の前に横たわる遺体(ライヘ)は何を語るのか。過去の、そして未来の死者たちへ捧ぐ、医療小説をお届けします。
第3章 上肢をはずす
次に、それまで手袋をして保護していた、いわゆる手の解剖に入る。まず、手背、手の甲から皮切りするのだが、まるで自分の手にメスを入れるようで、吐き気のようなものを感じる。指の皮膚までも剝ぐのだ。
しかも、それまでは切開を入れる具体的な切開線を図示してくれていたテキストに、今回は手がかりが何も無かった。
「どこにどう切開を入れろと言うんだよ」高久が、口を尖らせながら言った。
「適当にやれば良いんじゃないか」田上が半ば冗談のように言った。
「よその班はどうしているか見てみよう」高尾が取りなすように言った。
それとなく隣近所の班の遺体の手を見つめる。表と裏で境を分けているもの、すなわち指の側面に切開を入れている班が大半だった。我々もそれに従う事にした。高久は遠く離れた班にまで行って確かめて来たが、同じだった。ただ、彼はニュースを持ち帰った。
「あのさ、4班は大変らしいよ、竹田が交通事故起こしたもので、今三人でやっているんだって」
ずっと出て来れないのか、と田上が聞く。
「さあ、大事故じゃないらしいから、そのうち復帰すると思うけど、もっと大変なのが13班の紫藤さんの班だよ」
高久は紫藤と高校の同級生だ。
何で? 僕が聞いた。
「紫藤さんが急に休んだんで、ほとんどそれまでブレインとして他の三人が頼り切っていたので、困ってるんだとさ」
僕はちらっと13班のほうへ眼を遣った。白い解剖学実習着に包まれた三人の生徒がテキストを見たり、相談したり、手を動かしたりしている。その姿が何となく寂しそうに見えた。
交通事故の竹田は仕方ないとして、紫藤はどうしたのだろう。
手の甲では、皮を剝がすと、すぐに静脈と神経があらわれる。特に静脈は、自分の手の甲を見ると、皮膚の直下に浮き上がって見えるほど皮が薄いのだから、ちょっとでも深くメスを入れると、たちまち血管も傷つけてしまい、残存していた血液がゆっくりと流れ出てくる。ゴム手袋をしているから、直接自分の指にふれることはないが、気持ちの良いものではない。他のどこでもそうだとは思うが、手は特に生々しい部位だ。