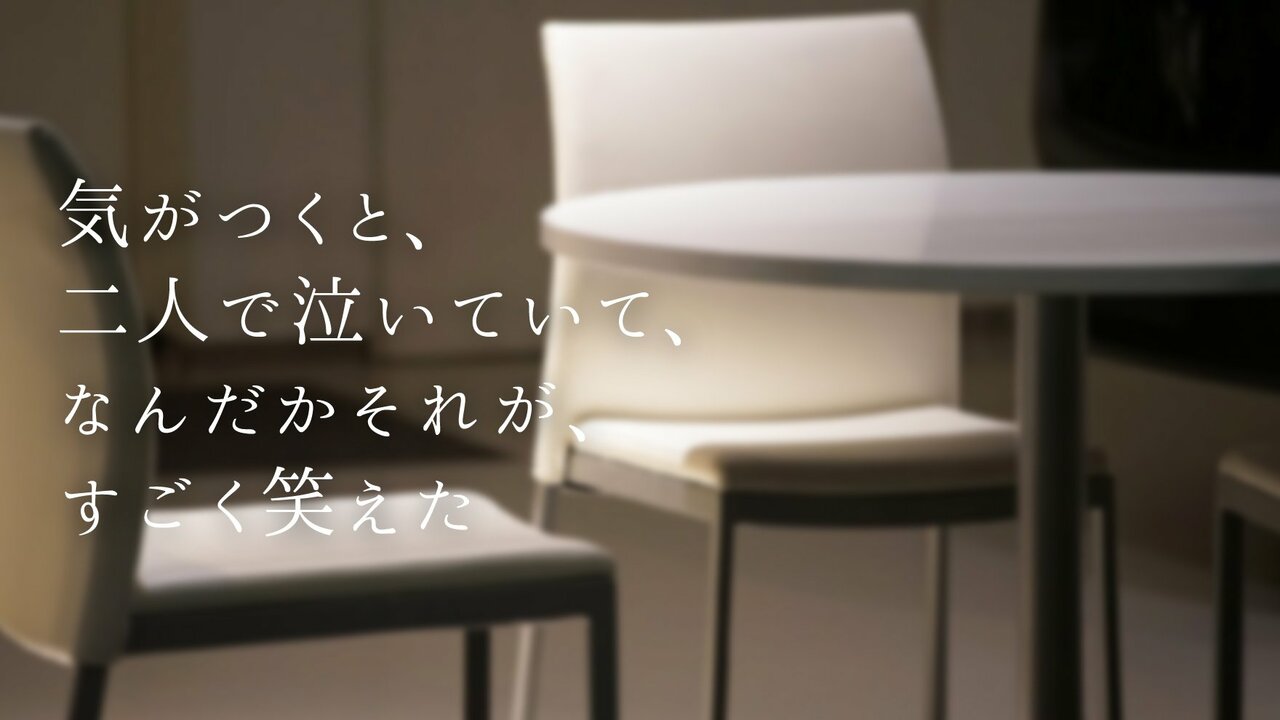「ほぼ。生きられていません。むしろいつも、正しさとは違う方を選んでしまうような気がします。
だからシャツ、私も買わなくちゃですね」
彼は、短い時間に私が見るよりも深く私を見て、そしてゆっくりと微笑んだ。
私には、そう思えた。
私たちは、お互いに、見えないところを見ようとしたように感じた。
目が合うということは、そういうことだ。
その時間がどんなに短くても、二人だけが感じる空気がそこに存在する。
彼はわずかにうつむいて目を閉じて考え、それから白いシャツの棚に向かい、肩に控えめにフリルの付いたブラウスを持ってきた。襟には黒い紐が付いていて、前でリボンに結べるようになっている。
彼が私に合うブラウスを探す間、私はうつむいた時の彼のまつ毛の長さについて考えていた。
「あなたには、これが似合うと思うのですが、どうですか?
もしも間違いをしたら、この黒いリボンを少しきつく結んで、僕が間違いを縛りましょう」
切れ長の目をさらに細くして、にこやかに彼はそう言った。
スタッフは彼が気がきくことを言ったという風に笑ったけれど、私には底のない湖にひたりと足をつけてしまった気がして、笑えなかった。