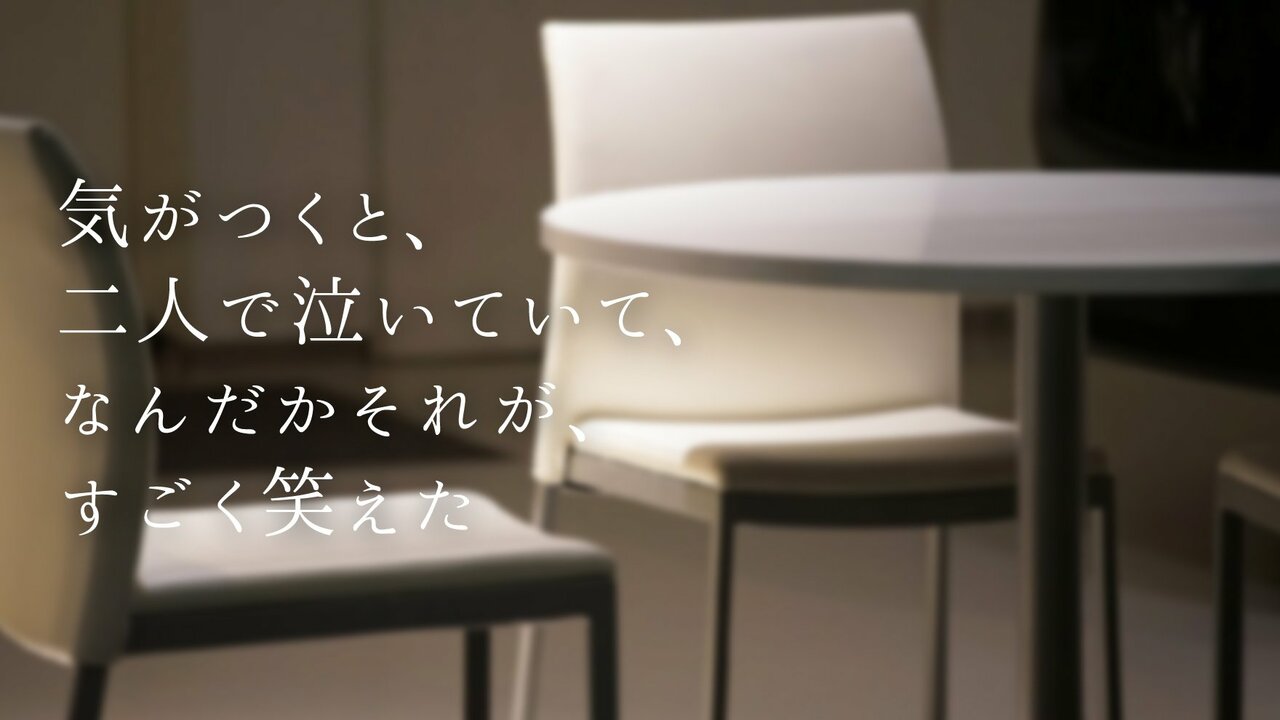【関連記事】「出て行け=行かないで」では、数式が成立しない。
シャツ専門店
私は飲みすぎていたけれど、それでももう少し飲みたくて、同じジントニックを頼んだ。
友人がバーテンダーに、私のジントニックを、少し薄めに作るように言った。
「私は18歳でこの仕事を始めましたが、それまで、ほとんど友達と呼べる人がいませんでした。そしてこのような不規則な世界に入ってしまったので、数少ない友人と会うこともままならず、もちろん新しい友達を作る時間もなかったので、いつの間にか、一人でいるのが平気だと思い込んでしまった」
私がそこまで話すと、カウンターにジントニックが置かれた。
もはや薄く作られているかもわからなかったけれど、グラスに口を付ける。私は友人に美味しい、と言った。彼も置かれたジントニックを、やはり美味しそうに一口飲んだ。
「この店の店主、奏多は私の数少ない親友の一人です」
彼はジントニックをもう一口飲みながら、私がお酒に弱いことも知ってくれている友人の気配りとその仕事ぶりに感心しながら頷いた。
カウンターで忙しく、止まることなく料理を作り続ける奏多はそれでも話が聞こえていたようで、厨房に向かっていた身体を私たちの方に向けて話し出した。
「僕がまだ、別のレストランバーで働いていた頃、こいつは仕事終わりにそのバーに、一人で飲みに来て、一杯飲んで帰っていました。そのバーは彼女の先輩のお店で、たまには飲みにでも来るようにと言われていたみたいで」
「私、そのすぐ近くに住んでいたの。そのバーはすごく流行っていて、いつでも人が多かったけど、私は深夜の生放送をしていたから帰りは深夜2時過ぎで。その時間にはさすがにカウンターは空いていた。友人、奏多は、そのカウンターの奥で料理を作っていたんです」
「最初はね。こいつがいつ来てもなんか、あんまり喋らないから、気になって話しかけたんです。大抵僕の前に座るし、どうしても目が合うから。そしたら僕らは同じ歳で、お互い、空気が似ているなあと。社交場に来ているくせに、人と話そうとはしない。でも、完全に拒絶しているわけではなくて。
僕も料理が好きだから働いていたけれど、決して接客は得意じゃなかった。好き嫌いがはっきりしていたし、失礼だと思う人とは、会話も続かなかった。
でも、美味しい料理をちゃんと作っていれば許されるんじゃないかって思っていたんです。そんな僕から見ても、こいつアンバランスなやつだなあって。本当に、メディアの華やかな仕事なんてできているんだろうかって。それからもう10年以上この関係が続いています」
「奏多は、私がなんでも話せる友人の一人です」
「そう。僕は、彼女と恋愛にはならないのです。僕は、女性は愛せないから。でも彼女のことをとても大切に思っています」
奏多はいつもみたいに優しい顔で、彼にそう言った。私は急に泣きそうになった。悲しみは目に見える。表情や言葉、仕草、距離の置き方、着こなし、目の深さ。私は奏多に悲しみを見た。