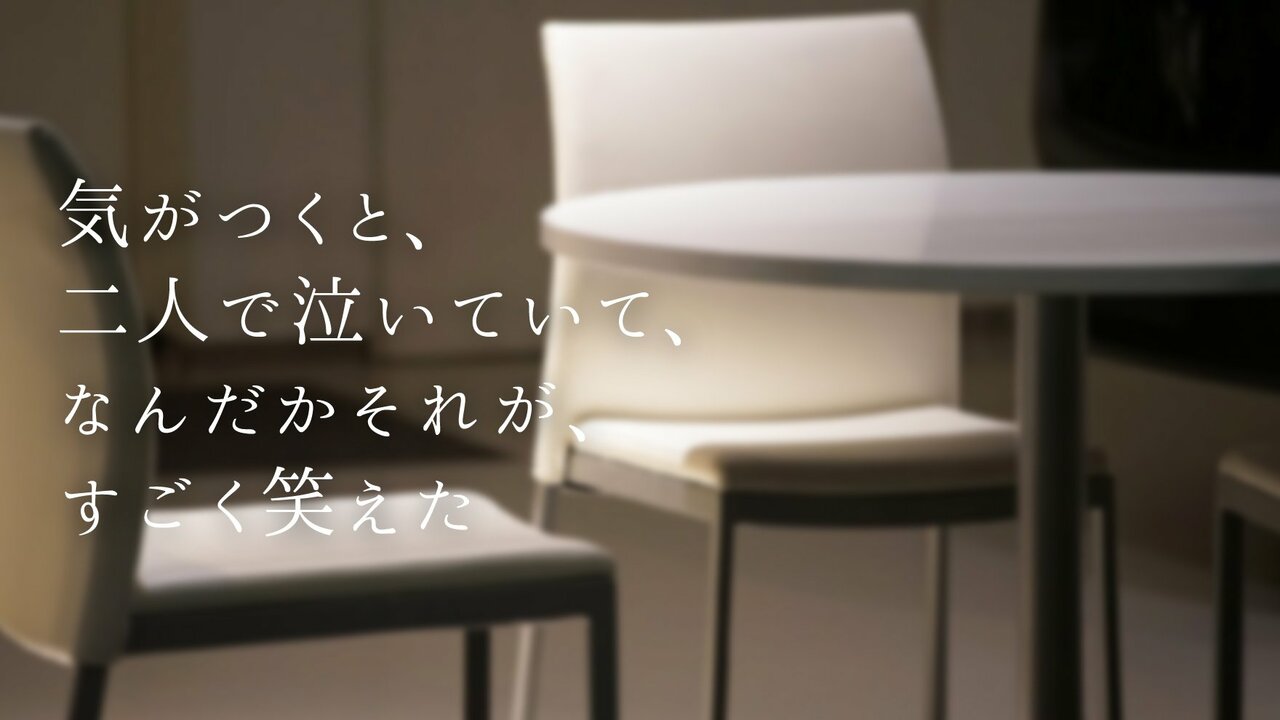シャツ専門店
その夜の私たちは、あっという間にお互いに好意を寄せ合った。
少なくとも私は、言葉も、振る舞いも、好きだという気持ちを抑えることはなかった。
抑えきれなかった。と言うのが正しいかもしれない。
【関連記事】「出て行け=行かないで」では、数式が成立しない。
私はその日、古いビルの3階にある友人のレストランバーを予約した。1階の入り口に小さな灯のつく看板があるくらいで、初めての人にはなかなかたどり着けないお店だった。テーブルが3つとカウンターに10人が座れるくらいのお店で私は大抵一人でその店に行く。
そのお店で、友人が作る、手間のかかった美味しい料理たちを食べながら、店のサイズにしては少し大きすぎる音楽の響きの中で私たちはできるだけ小さな声で話をした。カウンターに座って、私たちの肩は、お互いの声を聞こうとするとわずかに触れ合うことになった。顔を寄せると彼の香水の匂いが僅かに香った。それだけで私は胸がドキドキとした。
肩が触れている時には恥ずかしくて彼の顔をちゃんと見ることができず、なんとなく無言になると、なんだか店中の人が私たちを見ている気がして、私は何事もない風にしてピクルスを頬張った。
それはとても不器用で、笑ってしまうけれど、初恋みたいだった。
彼は、とても落ち着いていて、ごくたまにタバコに火をつけた。
ビールの後にはジントニックを頼み、友人の得意なトマトとナスとアンチョビのパスタをとても美味しそうに食べた。
触れた肩を慌てて離そうとはせず、わずかに触れたままの距離を、もともとそうであったかのように自然に保ってくれた。
言葉はなかったけれど、私に特別な感情をくれているような気がした。そう感じるのに十分なしぐさだった。
「あなたは、不思議なことを、他にも沢山経験してきたのですか?」
しばらくして、彼は彼のお店で話したその続きを私に聞いた。
私はお酒も手伝って、なんだか話してもいい気持ちになっていたから、幼い日々を辿りながら、話をする。
「なんというか、私自身、それが不思議なことだとは思っていないこともあります。今になると不思議なのかもしれないと感じるのだけれど、さっき話したように、様々な私の言動を母は全部、まるで当たり前のことみたいに受け入れてくれていたから、私は自分を否定せずに生きてこられたのです。
さすがに高校生になると、私が信じたものや見えていることをありのままに言うと友人たちに変な顔をされたり、クラスメートに話をしてもらえなくなったりしたので、ああ、やはり私は少し世の中の正しいからズレているのだと、人に本音や、見えたり感じたりすることをそのまま話すことをやめてしまったのです。
あなたのお店に伺ったときにも、私は正しく生きられないと言いました」
「でも、うわべを取り繕うことは、上手になった」
彼は短く言う。