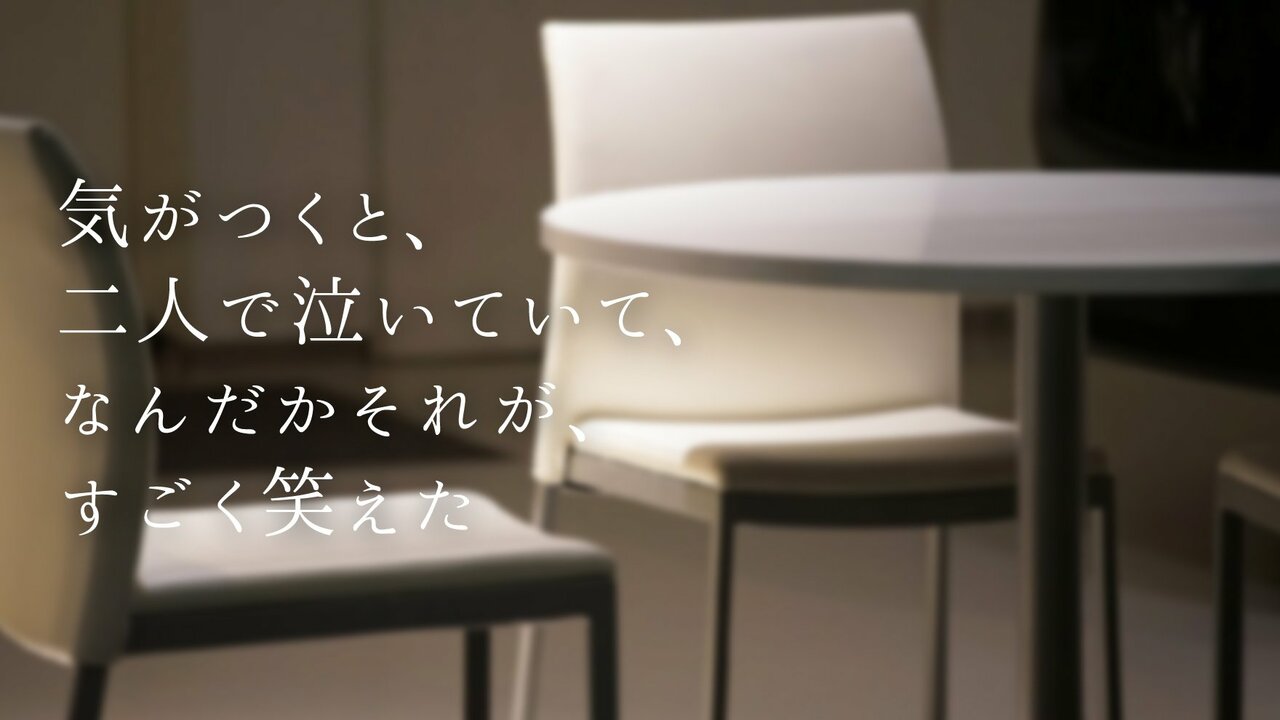出会った頃、少しずつ会話を交わすようになって、奏多は私にうわべでうまく喋った。外側を軽く撫でていくように、窓枠の埃が溜まっていないかと指でなぞるみたいに、力を入れず、私の表面をなぞった。
ずっと目を細めて笑ったまま、ほぼ表情を変えなかった。まるで元からその表情に作られた人形みたいだった。でも、よく見ると、その目は少し潤んでいて、そこには、森の奥にある、湖みたいな、暗い中にある、夜に差し込む月の明かりみたいな、そんな美しさがあった。
この人は、幾度も傷つき、苦しんで、そして表情を変えない方法を学んだ。私と、似ていると思った。でも私と違う奏多の素晴らしいところは、彼は自分が同性愛者だと周りにちゃんと伝えていたことだった。
もしかして人と違うかもしれないという苦悩と恐ろしく長い暗闇のトンネルを抜けて、自分次第で明るく温かな場所へ行けるのだと、自分の足を、現実という大地に下ろすことができた。
私たちはなんでも話すようになり、仕事が休みの日には奏多が私の家で、料理を作ってくれたりした。そんなときには私たちはいつも、大音量で音楽を聴く。
お互いに好きなCDを順番に、時には私の選ぶ曲ばかりを、時には奏多のばかりを聴いた。ある日、私がかける曲が、奏多のお気に入りになった。もちろん私も大好きな曲だったから、とても嬉しかった。
それは、SIONの「夜しか泳げない」という曲だった。
夜しか泳げない
魚は 影を連れて歩かない
だけど 光だけが光じゃないことだけは
太陽より知ってる
私たちはその日、何度もこの曲を聴いた。彼の作った、彼のお母さん直伝の大きな野菜と団子が入ったスープを食べなから、何度も聴いていた。
そして気がつくと、二人で泣いていて、なんだかそれが、すごく笑えた。この人になら、なんでも喋れるような気がした。