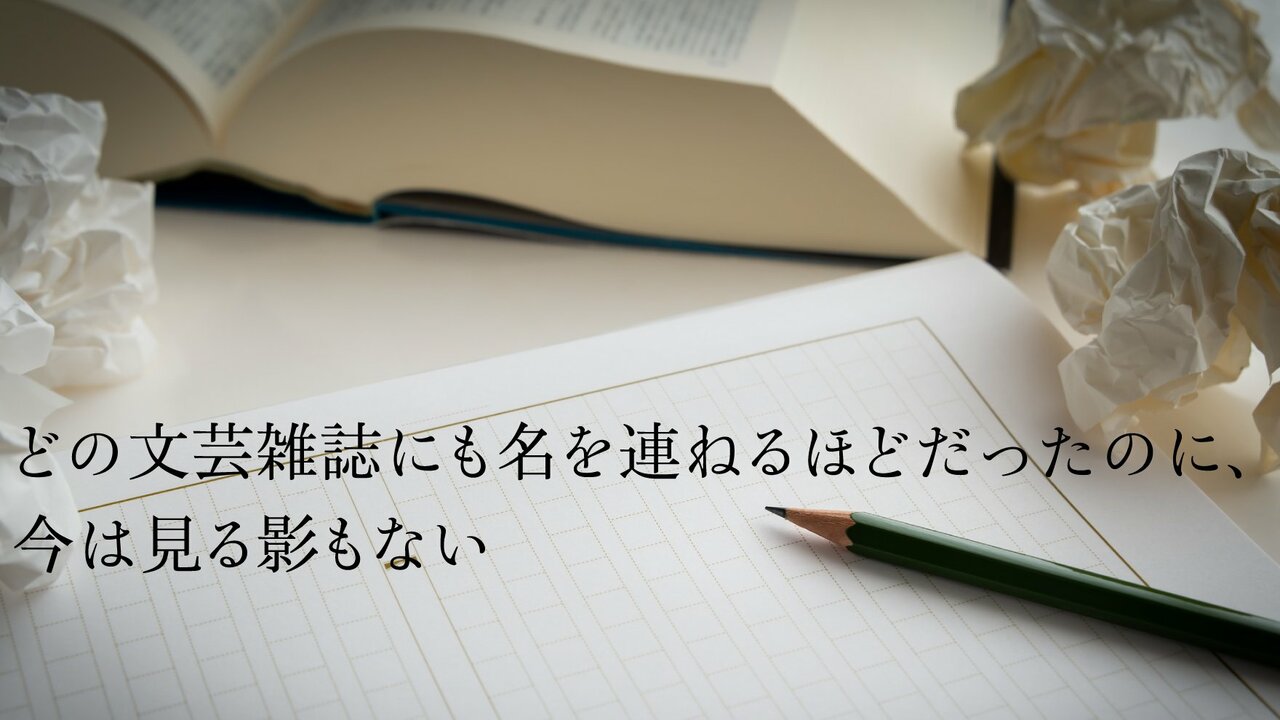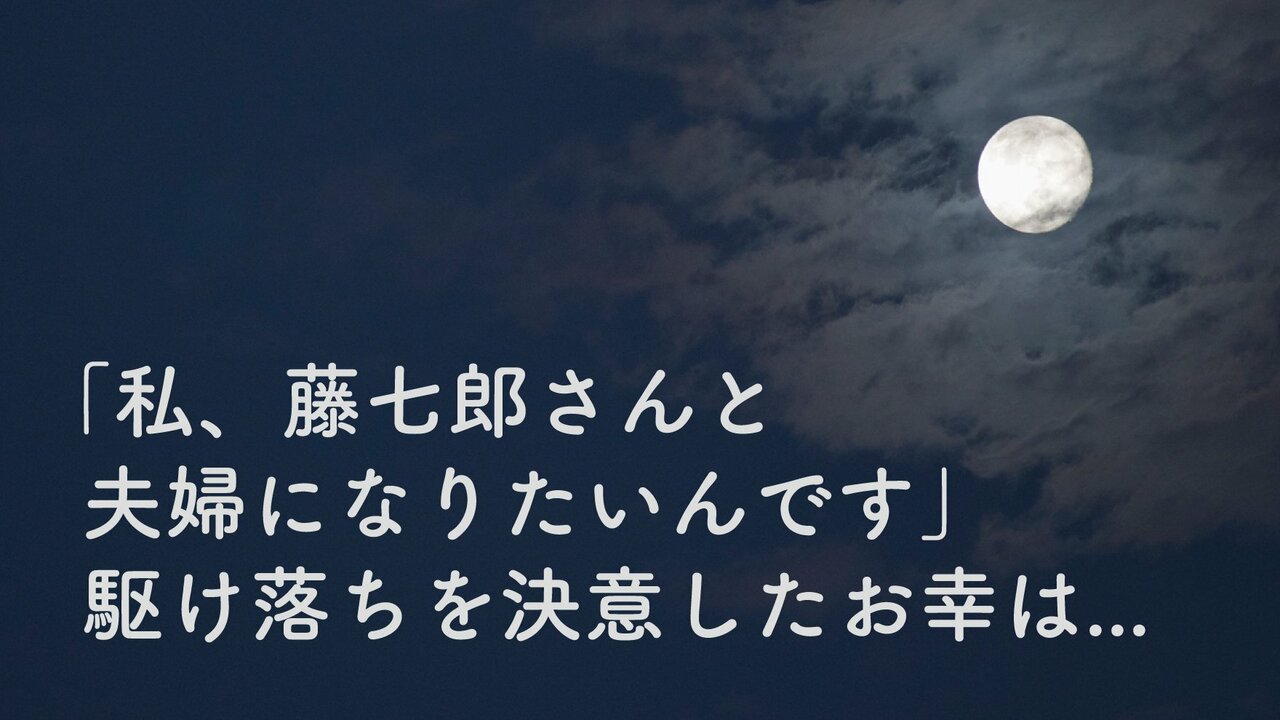夏、だったと思う。はっきりしたことは覚えていないが、あのじめじめした感じはとてもよく覚えている。
私は多汗症の気があるから、もしかしたら夏ではないのかもしれない。そんなどうでもいいことを考えながら、書きかけの原稿用紙に目を滑らせた。
――駄目だ。全然思いつかない。続きが書きたいのに、書けない。
気に入りの万年筆が手に握られたまま、私の汗でぬめりを増すだけで一文字も書けなかった。これがいわゆる“スランプ”というものなのだろう。
齢十八でデビューしたての頃はいろんな出版社に引っ張りだこだった。だが、二十年も経つとその栄光もすっかり輝きを失ってしまっていた。今は小さな出版社で数ヶ月に一度の頻度で雑誌に連載を寄稿している。
昔はいくらでもアイデアが浮かんできたものだが、なかなか昔のようにはいかないことばかりだ。十数年前は『瑞月 真(みづき まこと)』といえばどの文芸雑誌にも名を連ねるほどであったのに、今はもう見る影もない。
「――もうやめた」
三枚程度書いた原稿用紙を丸めてゴミ箱に放り投げる。
今更説明するのもどうかと思うが、私はデビューした頃から小説は全部原稿用紙に書いている。ワープロを使うように勧められていたがどうも私の肌には合わず、ずっと原稿用紙のスタイルを貫いてきた。